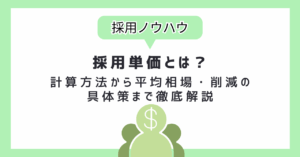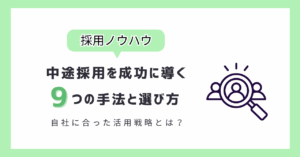ダイレクトリクルーティングは、優秀な人材を求める企業にとって有効な手段の一つです。ただし、個人情報保護法や労働法など、法的リスクも潜んでいます。知らずに対応を誤るとトラブルに発展する可能性も否定できません。
本記事では、ダイレクトリクルーティングにおける法的リスクについて、具体的な事項と企業が取るべき対策を解説します。本記事の内容を参考に、ダイレクトリクルーティングを成功に導きましょう。

エンジニア採用、こんな課題ありませんか?
- 技術力だけでなく、事業理解も必要だけど、見極めが難しい
- 社内システムを支える柔軟な対応力を持つ人材がなかなかいない
- 企業文化にフィットするエンジニアを採用したい
「社内SE転職ナビ」なら、技術×カルチャーの両面からマッチするエンジニアをご紹介できます。エージェントによる丁寧なヒアリングに加え、企業から直接アプローチできるダイレクトリクルーティング機能もご利用可能。貴社の採用スタイルに合わせて、最適な候補者との出会いをサポートします。
ダイレクトリクルーティングとは
ダイレクトリクルーティングとは、企業が採用候補者へ直接アプローチする採用手法です。従来の求人広告や人材紹介サービスといった「待ち」の姿勢の採用手法とは異なり、企業自らで主体的に動く点が特徴です。
従来の採用手法では出会えなかった優秀人材にアプローチできる手法として、ダイレクトリクルーティングは注目を集めています。ダイレクトリクルーティングでは人材データベースを活用し、自社の求めるスキルや経験を持つ人材を能動的に探し出すことができます。特に、特定のスキルや経験を持つ人材を求める企業や、スタートアップ企業にとっては非常に有効な手段といえるでしょう。
ただし、ダイレクトリクルーティングはメリットばかりではありません。法的リスクも伴うため、適切な対策が求められます。
-3-300x157.jpg)
ダイレクトリクルーティングにおける法的リスク
企業が自ら積極的に候補者にアプローチするダイレクトリクルーティングには、考慮すべき法的リスクが存在します。ダイレクトリクルーティングを行う際に気を付けるべき法的リスクは、主に以下の7つです。
- 個人情報の不適切な取得・利用(個人情報保護法違反)
- 労働法
- 雇用差別
- SNS
- オファーメール
- 競業避止義務
- 引き抜き問題
各法的リスクについて詳しく見ていきましょう。
個人情報の不適切な取得・利用(個人情報保護法違反)
個人情報保護法により、候補者の氏名・連絡先・職務経歴などは厳格に保護されています。企業が適切な手続きを踏まずに個人情報を取得・利用すると、違法となる可能性があります。
【違反例】
- 候補者の同意なしにSNSやデータベースから個人情報を収集する
- 採用目的以外で取得した個人情報を他の用途に流用する
- 個人情報の管理が不適切で、情報漏洩が発生する
【想定されるリスク】
- 損害賠償請求や行政処分の対象となる
- 企業の信用が低下し、採用活動に悪影響を及ぼす
候補者の個人情報を取得する際は、必ず事前に明確な同意を得ることが重要です。また、取得した個人情報は採用目的のみに使用し、適切な管理体制を構築して情報漏洩を防ぐ必要があります。社内での個人情報保護ルールを策定し、従業員に対して定期的な研修を行うことで、リスクを最小限に抑えることができます。
求職者への虚偽の労働条件提示(労働基準法・職業安定法違反)
採用活動では、労働基準法や職業安定法などの適用を受けます。求職者に対し、実際とは異なる労働条件を提示すると違法となります。
【違反例】
- 「残業なし」と説明しながら、入社後に恒常的な残業を強いる
- 給与・待遇を実際より高く見せかけ、誤解を招く表現をする
- 「リモートワーク可」と記載しながら、実際にはできない
【想定されるリスク】
- 労働基準監督署の調査や行政指導を受ける
- 求職者とのトラブルが発生し、企業の評判が悪化する
対策
オファーメールや面接において、労働条件を偽って表示したり、実際とは異なる内容を提示したりすると労働基準法違反となる可能性もあります。求職者に対して虚偽の情報を伝えたり、不当な条件を提示したりするのも禁止されています。
そのため労働条件は、求人情報やオファーメールにおいて明確かつ正確に伝えることが重要です。誤解を招くような表現は避け、記載内容と実際の待遇が一致するように管理し、適宜確認を行いましょう。また、採用活動に関わる担当者に対して、定期的に労働法の基礎知識を学ぶ機会を設けることで、違反を防ぐことができます。
雇用差別(男女雇用機会均等法・雇用対策法違反)
年齢・性別・国籍・信条などを理由とした不当な採用基準は、法律で禁止されています。
【違反例】
- 「35歳以下のみ応募可」とする(年齢制限の不当な設定)
- 「女性歓迎」「未婚者のみ」などの条件を記載する
- 特定の大学出身者や特定の経験を持つ人のみを優先的に採用する
【想定されるリスク】
- ハローワークや行政機関からの指導を受ける
- 求職者から訴えられるリスクが発生する
対策
採用基準は業務に必要なスキルや経験に基づいて設定し、特定の属性を理由に求職者を排除しないようにすることが重要です。また、採用担当者向けの差別防止研修を実施し、公正な採用プロセスを維持できる体制を整えましょう。
SNSの不適切な活用(プライバシー権・名誉毀損リスク)
ダイレクトリクルーティングでは、SNSを活用する機会が増えていますが、候補者のプライバシーを侵害しないよう注意が必要です。
【違反例】
- 候補者の許可なしにSNSの投稿内容を調査し、評価に影響させる
- 公開情報とはいえ、SNS上の情報を無断で社内共有する
- 候補者の評判について、不確かな情報を拡散する
【想定されるリスク】
- プライバシー権の侵害や名誉毀損で訴えられる可能性がある
- 企業の信頼が損なわれる
候補者のSNSアカウントは公開されている情報であっても、無断で収集・利用してはいけません。プライバシー権の侵害とみなされるリスクがあるからです。さらに、SNS上の情報に基づいて候補者を評価した際、不当な扱いをしたと判断されれば名誉毀損にあたる可能性もあります。
SNS情報を評価基準としないことが望ましいですが、どうしても必要な場合は、客観的な指標に基づいた判断を行い、不適切な利用を防ぐ仕組みを作ることが重要です。
オファーメールに関する法的リスク(労働契約法・民法違反)
オファーメールは企業と候補者の最初の接点となる重要なツールです。ただし、法的リスクが潜んでいる点には注意しましょう。
【違反例】
- 「内定確約」のような誤解を招く表現を使用する
- 曖昧な表現で、実際とは異なる給与や待遇を記載する
【想定されるリスク】
- 内定取消が難しくなる
- 採用後の条件違いによるトラブルが発生する
オファーメールには、誤解を招く表現を避け、正確な労働条件を記載することが必要です。また、「内定確定」と誤認されるような表現は使用せず、採用プロセスの進行状況を明確に伝えることが重要です。
競業避止義務(不正競争防止法・労働契約法)
競業避止義務とは、退職した従業員が一定期間、競合他社への転職や起業を制限する義務です。前職で競業避止義務を負っている転職者にアプローチする場合、ダイレクトリクルーティングを行う企業は注意が必要です
【違反例】
- 競業避止義務のある人材を知らずに採用し、前職の企業とのトラブルが発生する
- 転職者が前職の秘密情報を持ち込んでしまい、不正競争防止法違反となる
- 前職の顧客リストを利用し、新しい職場で営業活動を行う
【想定されるリスク】
- 企業側も法的責任を問われる可能性がある
- 損害賠償請求を受けるリスクがある
- 企業の信頼が低下し、採用活動に支障をきたす
採用前に、候補者が競業避止義務を負っているかを確認することが重要です。候補者に対して前職の契約内容を確認するよう依頼し、必要に応じて弁護士と相談しながら適切な対応を取ることが求められます。また、入社後に前職の情報を利用しないよう、機密情報の取り扱いに関する誓約書を交わすことで、リスクを低減できます。
引き抜き問題(不正競争防止法・民法違反)
ダイレクトリクルーティングを用いた過度な引き抜きは、法的問題に発展する場合もあります。組織的な引き抜きや、不当な手段を用いた引き抜きは、不正競争防止法や民法上の不法行為に該当する可能性があるからです。
【違反例】
- 競合他社の特定部署の社員に集中的にアプローチする
- 前職の企業秘密を不正に取得・利用して、求職者に有利な条件を提示する
- 退職者に対し、前職の顧客情報を活用するよう指示する
【想定されるリスク】
- 企業が不正競争防止法違反とみなされ、損害賠償請求を受ける可能性がある
- 競合他社との関係が悪化し、ビジネスリスクが増大する
- 企業の採用ブランドが損なわれ、求職者の応募が減る可能性がある
競合他社の従業員を組織的に引き抜く行為は、企業間の公正な競争を阻害する行為として、不正競争防止法違反となる可能性があります。前職の企業秘密を不正に取得したり、前職の顧客情報を不正に利用したりする行為も、同様に違法となるでしょう。引き抜き行為によって、前職の企業に損害を与えた場合、損害賠償責任を負う可能性もあります。
意図する、しないに関わらず客観的に引き抜き行為とみなされる場合には、正しく法律を理解して法的リスクを最小限にしなければなりません。
ダイレクトリクルーティングの法的リスクにおける5つの対策
ダイレクトリクルーティングには法的リスクがつきものではあるものの、正しく対策を行っていれば大きな問題にはなりません。具体的に企業がとるべき対策は、主に以下の5つです。
- 個人情報を適切に管理する
- 利用ガイドラインをつくる
- 差別・ハラスメントを防ぐ
- SNS・オファーメールの適正化
- 候補者の契約内容を確認する
各対策について詳しく解説するので、ダイレクトリクルーティングを検討されている方は最後までご覧ください。
個人情報を適切に管理する
ダイレクトリクルーティングにおける法的リスクを軽減するには、個人情報の適切な管理が不可欠です。
個人情報を適切に管理するには、個人情報の収集・利用に関する明確なルールを策定しなければなりません。収集する情報の種類や利用目的、保管方法、削除方法などを具体的に定め、従業員に周知徹底しましょう。
個人情報を収集する際には、候補者からの同意も必要です。利用目的を明確に伝え、同意を得た範囲内でのみ個人情報の利用が許されます。個人情報の漏洩を防ぐために、セキュリティ対策も必要です。アクセス制限の設定や暗号化、ログの監視など、多角的な対策を講じましょう。
これらの対策によって、個人情報保護法違反のリスクは大幅に軽減できます。
利用ガイドラインをつくる
組織全体で共有できる明確な利用ガイドラインの作成は、法的リスクの軽減に有効です。ガイドラインは、ダイレクトリクルーティングに関わる従業員が法的リスクを理解し、適切な行動を取るための羅針盤となります。
ガイドラインには、ダイレクトリクルーティングの目的や対象となる人材、利用するツールなど、具体的な項目を盛り込みます。個人情報の取り扱いやSNSを利用する際の注意点、オファーメールの作成に関するテンプレートなども、ガイドラインに含めて従業員に周知しましょう。
従業員向けの研修を実施し、ガイドラインの内容を繰り返し周知徹底します。研修では、ガイドラインの内容だけでなく、具体的な事例を交えると効果が高まります。
差別・ハラスメントを防ぐ
差別やハラスメントは、ダイレクトリクルーティングを行う際の重大な法的リスクです。男女雇用機会均等法や雇用対策法などの法律で禁止されており、企業は法的責任を問われかねません。
差別やハラスメントを防止するには、採用基準や選考プロセスを見直し、客観的で公正な評価基準が重要です。応募者の能力や適性のみを評価し、個人的な感情や偏見に基づいた判断を排除しなければなりません。面接時の質問内容にも注意が必要で、プライベートな質問や、差別的な質問は避け業務に必要な情報のみを尋ねましょう。
採用後も見据えて、差別やハラスメントに関する相談窓口を設置しておくのもおすすめです。社内での差別・ハラスメント意識の向上にもつながります。
SNS・オファーメールの適正化
ダイレクトリクルーティングで、SNSやオファーメールを用いる場合、適切な対策が求められます。使い方を誤るとプライバシー侵害や名誉毀損、労働条件の誤認などを引き起こす可能性があるからです。
SNSを利用する際には、候補者のプライバシーを尊重し個人情報の収集は必要最小限にとどめます。客観的な証拠に基づいた判断を心がけ、偏見や先入観にとらわれないように注意しましょう。
オファーメールを作成する際には、表現を明確かつ正確にして、誤解を招くような曖昧な表現は避けなければなりません。詳細な情報を記載し、後々トラブルにならないように対処します。
これらの対策を講じることで、SNSやオファーメールが原因となる法的リスクを最小限に抑えられます。
候補者の契約内容を確認する
ダイレクトリクルーティングでは、候補者が前職と交わしている契約内容を事前に確認することが重要です。特に注意すべきは、「競業避止義務」や「秘密保持契約」に関する条項です。
競業避止義務は、退職後に一定期間、競合他社での勤務や自社と競合する業務を行うことを制限する契約です。採用企業としては、候補者がその義務に違反するリスクがないか、事前に確認しておく必要があります。競業避止義務の有効性や合理性を判断する際は、期間や地域、業務範囲、代償措置の有無などを総合的に検討し、必要であれば弁護士の助言を受けましょう。
また、秘密保持契約によって、候補者が前職で知り得た機密情報を新たな勤務先で不正に使用しないよう義務付けられている場合もあります。これらの契約内容を把握せずに採用を進めると、企業が意図せず法的トラブルに巻き込まれる可能性があります。
採用前に、候補者に前職との契約に関する確認を行い、必要に応じて文書の提出や専門家による確認を行うことが、リスク回避につながります。
ダイレクトリクルーティングに向いている企業
ダイレクトリクルーティングには、優秀な人材を獲得できるメリットがある一方で、リスクや運用コストも伴います。そのため、すべての企業に適した手法とは限りません。ここでは、特にダイレクトリクルーティングと相性が良い企業の特徴を4つ紹介します。
特定のスキルや専門性を求めている企業
高度な専門知識を要する職種、たとえばAIエンジニアやデータサイエンティスト、クラウドインフラエンジニアなどでは、求人広告を出しても母集団形成が難しいことがあります。こうした職種は候補者の数自体が限られており、転職市場に出てこない人材も多いためです。
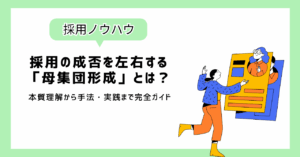
スタートアップで知名度が低い企業
知名度がまだ高くないスタートアップや中小企業にとって、応募を待つスタイルの採用は難易度が高いのが現実です。大手企業と比較されると、給与やブランド力ではどうしても不利になります。
しかし、ダイレクトリクルーティングであれば、候補者に直接アプローチし、自社のミッションや今後の成長性、働き方などを丁寧に伝えることが可能です。求人票だけでは伝えきれない「熱量」や「想い」が候補者に届きやすく、共感してもらえれば応募につながる可能性も高まります。
特に、裁量の大きさやスピード感、組織作りに関われる点を魅力に感じる人材は一定数存在します。そうした層にダイレクトに訴求できるのが、この手法の強みです。
少数精鋭でチームを組みたい企業
少人数のチームで事業を推進している企業では、一人ひとりの採用が業績に直結するため、採用の質が非常に重要になります。
ダイレクトリクルーティングは、単に「経験年数」や「スキルセット」だけでなく、コミュニケーションの雰囲気や価値観、キャリア観などの“相性”を加味したうえで、候補者を選べます。採用担当者が自らアプローチし、対話を通じて関係構築ができるため、入社後のミスマッチも防ぎやすくなります。
少数精鋭を目指す企業にとって、確度の高い候補者だけにリーチできるのは、大きなメリットです。
採用に工数をかけられる企業
最後に見落とされがちなのが「運用体制」です。ダイレクトリクルーティングは、候補者の検索・リスト化・文面作成・やりとりの対応といった一連のプロセスに、一定の時間とリソースが必要です。
人事専任担当者や採用チームがしっかり稼働している企業、あるいは採用責任者が直接スカウトに取り組む余裕がある企業であれば、その投資が成果につながりやすくなります。
逆に、「とりあえずアカウントを作ったけれど、放置してしまっている」「スカウトを送っても返信が来ない」といったケースでは、成果につながらないどころか、企業イメージの毀損につながるおそれもあります。
ダイレクトリクルーティングの活用なら社内SE転職ナビ!

ダイレクトリクルーティングでは、スカウト対象の精度が成果を左右します。社内SE転職ナビには、自社開発や情シスなど“社内で腰を据えて働きたい”志向を持つITエンジニアが多数登録。
特定領域の実務経験を持ち、定着意欲の高い人材と出会えるのが特徴です。取引実績は2,200社以上(2024年時点)。候補者とのコミュニケーション設計や面談調整も専任アドバイザーがフォローするため、工数を抑えつつ精度の高い採用が可能です。まずは一度ご相談ください。
まとめ
ダイレクトリクルーティングは、企業が主体的に人材獲得できる効果的な差言いよう方法です。ただし、本記事で紹介した法的リスクに備えていないと、候補者とのトラブルや訴訟問題に発展する場合もあります。
個人情報の適切な管理や利用ガイドラインの作成、差別やハラスメントの防止といった対策を行い、法的リスクを最小限に抑えましょう。本記事の内容を参考に、ダイレクトリクルーティングを成功させ、理想の人材を獲得してください。
なお、自社だけでダイレクトリクルーティングを導入するのが困難である場合には、社内SE転職ナビのダイレクトサービスの活用をご検討ください。貴社に寄り添い、企業の成長につながる人材獲得をサポートいたします。