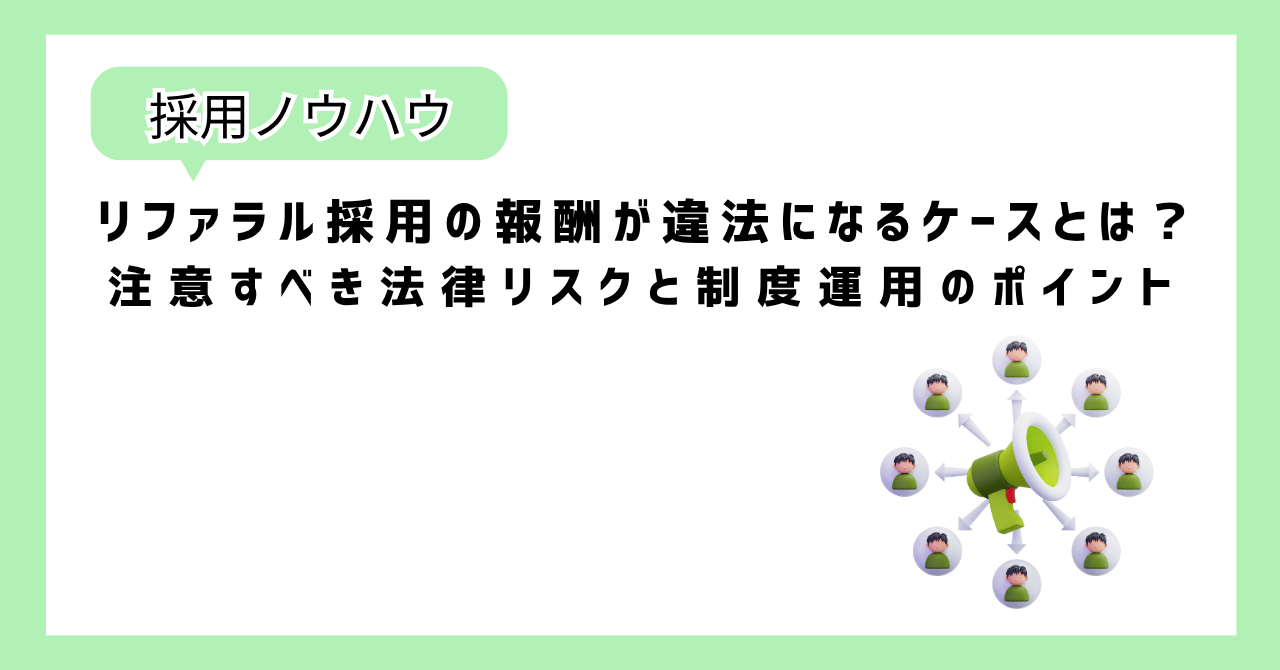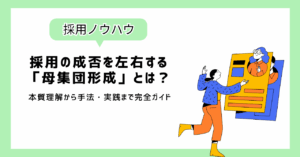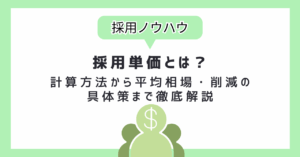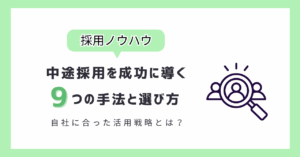リファラル採用に報酬(インセンティブ)を設定する企業は増えていますが、その運用方法によっては「職業安定法」に抵触する可能性があることをご存じでしょうか。
とくに、社員以外への報酬支払いや高額インセンティブの設定は、違法とみなされるリスクがあり、注意が必要です。
本記事では、リファラル採用の報酬が違法になる典型的なケースと、職業安定法に照らした適切な制度設計のポイントを解説します。就業規則や報酬ルールの整備、税務処理など、実務担当者が押さえておきたい観点を網羅的に整理しました。
違法リスクを回避しながら、社員が安心して紹介できる制度を構築するために、ぜひ参考にしてください。
1分でわかる!記事のポイント
- 報酬型リファラル採用は運用次第で職業安定法違反になるリスクあり
- 現職社員以外(元社員・業務委託等)への報酬は原則NG
- 報酬額・支給方法・就業規則への明記など、制度設計と実務運用が重要

エンジニア採用、こんな課題ありませんか?
- 技術力だけでなく、事業理解も必要だけど、見極めが難しい
- 社内システムを支える柔軟な対応力を持つ人材がなかなかいない
- 企業文化にフィットするエンジニアを採用したい
「社内SE転職ナビ」なら、技術×カルチャーの両面からマッチするエンジニアをご紹介できます。エージェントによる丁寧なヒアリングに加え、企業から直接アプローチできるダイレクトリクルーティング機能もご利用可能。貴社の採用スタイルに合わせて、最適な候補者との出会いをサポートします。
リファラル採用とは?報酬が導入される背景
リファラル採用とは、社員や関係者が知人・友人を自社に紹介することで採用につなげる仕組みです。社員が信頼できる人物を推薦するため、ミスマッチが起こりにくく、入社後の定着率も高い傾向があります。
企業側にとっても、採用コストの抑制や、エージェントに頼らない独自の採用チャネルとして活用しやすく、特にIT系企業やスタートアップを中心に広がりを見せています。
また、紹介を促すために報酬(インセンティブ)を用意する企業も増えており、「紹介数や質を高める」施策のひとつとして制度化されるケースが一般的です。

リファラル採用の報酬が違法になるのはどんなとき?【職業安定法の観点から】
リファラル採用で報酬を出すこと自体は、必ずしも違法ではありません。多くの企業が、社員紹介を促す目的で報酬(インセンティブ)を制度として導入しています。
しかしその運用方法によっては、職業安定法に違反する「有償の職業紹介」とみなされる可能性があります。違法とされるリスクがあるのは、たとえば次のようなケースです。
社員以外に報酬を支払うケース
もっとも典型的なリスクが高いパターンは、「現職社員以外」に対して報酬を支払うケースです。具体的には以下のような対象が該当します。
- 退職した元社員(OB・OG)
- パート・業務委託・フリーランスなどの外部人材
- 取引先企業の担当者や顧客
これらの人々に対して金銭や金券などの報酬を渡すことは、厚生労働省の許可を受けずに職業紹介を行ったと見なされる可能性があり、職業安定法第30条・第40条違反に該当する恐れがあります。
職業紹介の「反復継続性」があると判断されるケース
報酬の対象が社員であっても、「反復継続的に紹介行為を行っている」と見なされると、職業紹介事業に近い行為とみなされることがあります。
たとえば以下のような場合は注意が必要です。
- 明確な手数料型の報酬体系(成功報酬として10万円、など)
- 頻繁に紹介を行い、事実上の「社外人材バンク」となっている
- 業務委託契約での紹介が常態化している
報酬額や提供方法に問題があるケース
職業安定法では、「人材のあっせんを業として行い、報酬を受け取ること」は原則禁止とされています。そのため、報酬の額や渡し方によっては「職業紹介に対する対価」と判断されやすくなります。
以下のような設計は特に注意が必要です:
- 一律で10万円以上の高額な金銭報酬
- 商品券・旅行券など金銭に準じる価値のあるものを支給
- 採用に至らなかった場合の「参加賞」などを外部に配布
無許可で「職業紹介」とみなされるケース
職業安定法において、「職業紹介」とは求職者と求人者の間に立って、雇用契約の成立をあっせんする行為と定義されています。このため、紹介によって誰かが採用され、その対価として報酬を支払う仕組みがあると、「有償の職業紹介」とみなされる可能性が生じます。
とくに注意したいのは、以下のようなパターンです。
- 採用が決まった場合に限って報酬が支払われる
- 定着(例:3か月経過)後に高額な成功報酬が発生する
- 継続的に複数の紹介を行い、報酬を得ている
このような構造は、本来であれば職業紹介事業者に限って認められる行為であり、無許可で行うと法律違反になる恐れがあります。人材紹介エージェントなどの有資格事業者が報酬を得て紹介を行うのは、法令に基づいた正当な活動として認められています。両者を明確に区別して設計することが重要です。
報酬の種類(現金・商品券・特典)も注意が必要
「報酬」と聞くと現金が真っ先に思い浮かびますが、実は商品券・旅行券・特別休暇・カタログギフトなど、金銭的価値を持つ特典も“報酬”とみなされる場合があります。
そのため、以下のようなケースでも注意が必要です:
- 採用が成立した紹介者に対して「1万円分の商品券」を渡す
- 成功報酬として「社内表彰+豪華景品」を提供する
- 被紹介者との食事代や体験ギフトを会社負担で進呈する
これらは無償の協力行為の範囲を超えていると判断される可能性があるため、支給対象者・方法・金額のバランスを事前に精査しておくことが重要です。また、こうした報酬は社内規定や福利厚生制度に基づいて処理しないと、税務上の問題に発展することもあるため、注意が必要です。
リファラル採用の報酬に関する4つの注意点
制度設計上は問題なく見えても、実際の運用次第で法的リスクを招くケースがあります。ここでは、リファラル制度を導入・運用する際に注意すべき4つのポイントを紹介します。
社員以外(元社員・業務委託)への報酬
リファラル制度の対象を明確にせず、元社員や業務委託者など「雇用関係にない外部者」に報酬を出してしまうと、職業安定法違反に問われるリスクがあります。雇用関係がない者への謝礼は、無許可の有償職業紹介と見なされる可能性があるため、対象は現職社員のみに限定し、制度として明文化することが重要です。
特に、リファラル制度を「社内だけの仕組み」とせず、元社員のネットワークまで活用したいというケースでは、報酬を出さず感謝のメッセージでとどめる、またはSNS投稿などを促す広報活動にとどめるなど、別のアプローチを検討しましょう。
高額報酬による“紹介ビジネス化”の誤解
紹介報酬の金額設定にも注意が必要です。相場としては5万〜10万円程度が一般的ですが、過度に高額なインセンティブ(20万〜30万円超など)は、外部から見て「紹介ビジネス」と誤認されやすく、制度の健全性に疑問を持たれる可能性があります。
また、社員側でも「報酬目当てで紹介する」といった動機になりやすく、結果的に質の低い紹介や定着率の低下を招くこともあります。報酬設計は、採用部門と労務・法務でバランスを取りながら、社内への意図説明とセットで導入することが大切です。
あっせんと見なされるような継続的な紹介行為
リファラル制度の推進活動に熱が入りすぎると、特定の社員が継続的・反復的に人材を紹介するような事態になる場合があります。このようなケースでは、たとえ社内制度であっても、「報酬を受けて人材を職業として紹介している」と見なされ、職業紹介行為の常態化=許可なしの違法行為と判断されるリスクも否定できません。
制度としてはあくまで任意で一時的な紹介であることを明確にし、反復的な紹介が起きないよう注意喚起することが重要です。
就業規則や賃金規程に記載がない
リファラル報酬を支給する際に見落としがちなのが、「就業規則や賃金規程への反映」です。制度内容や支給タイミング、報酬額が明文化されていない場合、労使トラブルや経理処理上の齟齬が生じるおそれがあります。
また、報酬が「賃金」と見なされる可能性もあるため、税務処理(源泉徴収・所得区分)や社会保険の対象とするか否かについても事前に確認しておく必要があります。社内ポータルなどで制度概要を公開するだけでなく、制度の根拠を就業規則・賃金規程にしっかりと記載することが、法的安定性の担保に不可欠です。

よくある質問(FAQ)
最後に、リファラル採用の報酬に関してよくある質問を回答をご紹介します。
- リファラル採用で報酬を出すのは違法ですか?
-
報酬を出すこと自体が違法ではありません。ただし、対象が「外部の個人(元社員や業務委託など)」である場合、職業安定法に抵触する可能性があります。報酬は現職社員に限定するのが基本です。
- 商品券や特典を渡すのもNGですか?
-
金銭に限らず、商品券・旅行・特典なども「経済的利益」と見なされるため、対象者によっては職業安定法の規制対象になります。報酬の内容ではなく、誰に渡すかが重要です。
- SNSで元社員が求人を拡散し、採用につながった場合も違法?
-
A. 拡散自体は問題ありませんが、「その行為に報酬を出す」となると職業紹介行為に該当する恐れがあります。元社員や社外パートナーに報酬を渡すのは控えましょう。
- エージェントに依頼すれば問題ありませんか?
-
A. 有料職業紹介事業の許可を得ている人材紹介会社(エージェント)であれば問題ありません。本記事で注意すべきは、そうした認可を受けていない第三者への報酬です。
- 社内制度として整えておけば違法にはならない?
-
就業規則や賃金規程に明記することは前提ですが、それだけで適法になるとは限りません。報酬の対象や内容が職業安定法に照らして適切かどうかも判断が必要です。
エンジニア採用なら社内SE転職ナビ

人材獲得競争が激化する中、信頼できるIT人材の採用に課題を感じていませんか?「リファラル制度を導入していても、実際にはなかなか紹介が集まらず、採用につながらない」といった声はよく聞かれます。紹介を待つだけでは難しい今、別のチャネルでの採用活動も重要です。
「社内SE転職ナビ」は、情報システム部門・情シス経験者に加え、開発・インフラエンジニアにも対応した、IT職種専門の転職支援サービスです。職種理解に長けたエージェントが、要件整理から紹介・面談調整までを丁寧にサポート。さらに、企業から直接スカウトを送れる「ダイレクトリクルーティング機能」もご利用いただけます。
リファラルと併用しやすく、即戦力採用にも強い採用チャネルとして、ぜひご活用ください。まずはお気軽にお問合せください。
まとめ
リファラル採用は、信頼性の高い人材を効率よく獲得できる有力な手法です。一方で、報酬の出し方や紹介対象者によっては職業安定法に抵触するリスクもあるため、制度の設計・運用には注意が必要です。
違法リスクを避けるためには、
- 報酬対象者を「現職社員」に限定すること
- 報酬の内容と金額を適正に設計すること
- 社内規定やフローを明文化し、全社員に共有すること
- 制度導入後も継続的に見直し・改善を行うこと
が重要です。
制度として有効に機能させるには、法令対応とあわせて「社員が紹介したくなる導線づくり」も欠かせません。
法的リスクと制度の実効性を両立した設計と運用を心がけ、健全なリファラル採用を実現していきましょう。