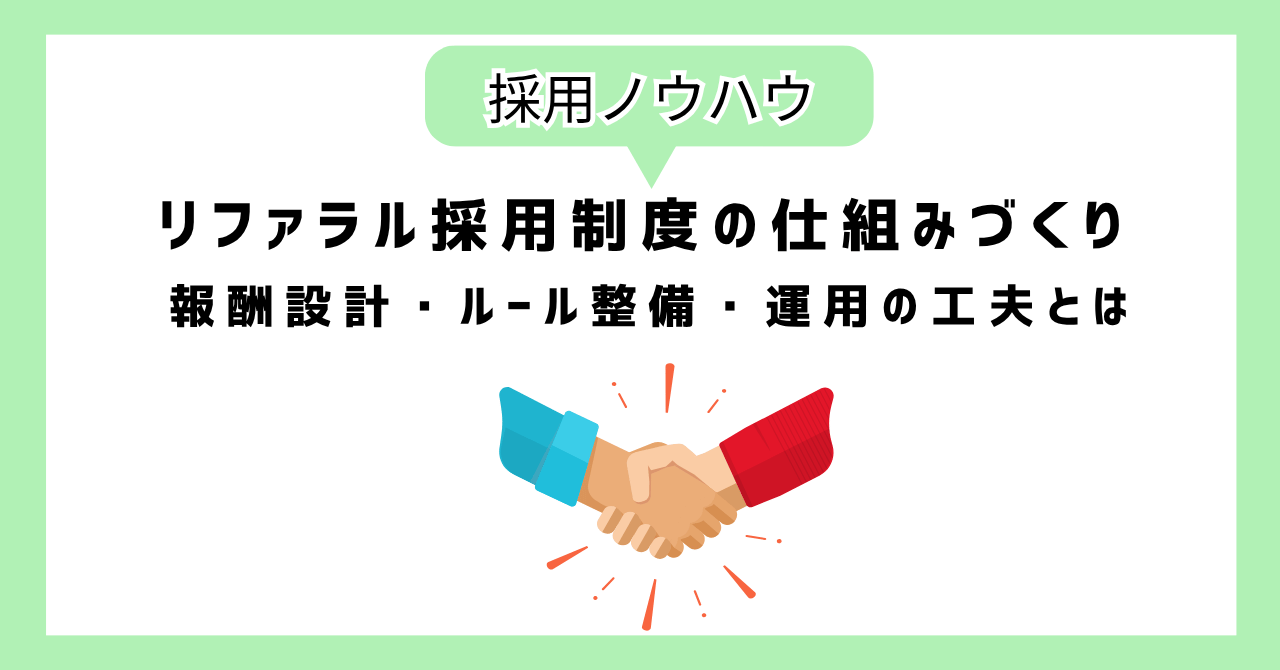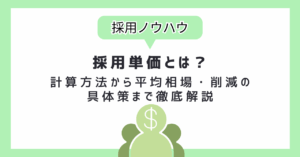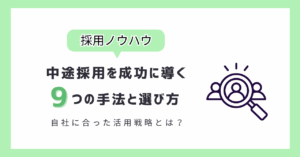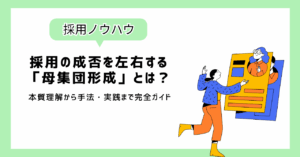「リファラル採用を導入してみたいが、どこから手をつければいいのか分からない」「制度はつくったけど、紹介がまったく集まらない」こうした声は、人事・採用担当者の間で少なくありません。
リファラル採用は、単に紹介してもらう仕組みではなく、制度設計と社内運用の工夫があってはじめて機能します。
この記事では、報酬設計の基本から、紹介ルールの整備、浸透のための運用ポイントまで、リファラル制度を実際に使われる制度にするための視点をまとめました。
制度の検討段階から、すでに導入している企業の見直しまで、幅広く活用いただける内容です。
1分でわかる!記事のポイント
- リファラル採用を機能させるには、報酬だけでなく制度設計と運用の工夫が必要
- 報酬は職種によって異なり、段階的な支給(通過・入社・定着)が一般的
- 紹介者に責任がかからないルールや、申請導線の一本化が制度活性化につながる
- Slackでの事例共有やポータル整備により、紹介のハードルを下げられる

エンジニア採用、こんな課題ありませんか?
- 技術力だけでなく、事業理解も必要だけど、見極めが難しい
- 社内システムを支える柔軟な対応力を持つ人材がなかなかいない
- 企業文化にフィットするエンジニアを採用したい
「社内SE転職ナビ」なら、技術×カルチャーの両面からマッチするエンジニアをご紹介できます。エージェントによる丁寧なヒアリングに加え、企業から直接アプローチできるダイレクトリクルーティング機能もご利用可能。貴社の採用スタイルに合わせて、最適な候補者との出会いをサポートします。
リファラル採用は「制度設計」で成否が分かれる
リファラル採用は、紹介制度を「つくるだけ」では機能しません。報酬を設けても紹介が集まらない、制度が形骸化する。そんなケースの多くは、制度設計に原因があります。
誰を紹介してよいのか、どのタイミングで報酬が出るのか、紹介者はどこまで関わるのか。こうしたルールが曖昧だと、社員は紹介に慎重になり、制度は形だけになってしまいます。紹介することに心理的な負担がある限り、社員は動きません。
逆に言えば、「紹介しても大丈夫」と思える制度になっていれば、自然と制度は社内に浸透していきます。リファラル採用の成否を分けるのは、制度の存在そのものではなく、その中身です。報酬・ルール・運用、それぞれが現場にフィットしているかが問われます。

リファラル採用を成功させる3ステップ
リファラル採用制度を導入する際は、「報酬をどうするか」や「申請フローをどうするか」といった個別の話に入る前に、制度全体の方針と枠組みを明確にする必要があります。以下の3つのステップをもとに制度設計を進めると、形だけで終わらない実践的な制度に仕上がります。
ステップ1:制度の目的とスタンスを決める
まずは「なぜリファラル採用を導入するのか」を言語化しましょう。目的によって、制度の設計は大きく変わります。
たとえば「採用コストの削減」が主な目的なら、広く紹介を募る方向に設計されるでしょう。一方で、「カルチャーフィットした仲間を増やしたい」が目的であれば、紹介の質や対象人材の条件を重視する制度設計が求められます。
例:採用コストの削減を目的とした制度設計
目的: エージェント経由の費用を抑えたい
制度の特徴:
- 紹介対象の職種や部門を広めに設定(全社的に開放)
- 報酬額は一定額でシンプル(例:一律3万円)
- Slackや社内ポータルにバナーを貼り、認知拡大を優先
- 件数ベースで実績共有(紹介数ランキングなど)
例:定着率向上・カルチャーフィット重視の制度設計
目的: 自社の価値観やスタイルに合った人材を増やしたい
制度の特徴:
- 紹介可能なポジションを限定(例:プロダクト開発・情シスなど)
- 社員との関係性や経歴の説明を求める申請フォーム
- 面接では「紹介者がなぜ推薦したか」を一部ヒアリング
- 運用面では「紹介が通らなかった理由」をきちんとフィードバック
ステップ2:紹介の対象と条件を定める
制度の目的が明確になったら、「誰が紹介できるか」「誰を紹介していいか」といった対象範囲を整理します。
たとえば以下のような点を検討します:
- 紹介できるのは正社員だけか?業務委託も含めるか?
- 紹介対象者に現職の知人、家族、学生なども含めるか?
- 入社済み社員が過去に接点のあった人を遡って申告してよいか?
この時点でルールが明確でないと、あとからトラブルにつながる可能性もあるため、制度設計の初期段階でしっかり定義しておくことが重要です。
ステップ3:報酬・申請フローなど制度の中身を設計する
方針と範囲が固まったら、ようやく制度の具体的な設計に入ります。
報酬の相場と職種別の違い
リファラル採用における報酬額は、職種や採用難易度によって幅があります。一般職では3〜5万円程度が相場ですが、エンジニアやコンサルタントなどの専門職では10万円以上が設定されるケースも見られます。
もちろん、高額な報酬を用意すれば紹介が増えるとは限りません。安心して人を紹介できる雰囲気や、制度への信頼があってこそ、制度は機能します。報酬はあくまできっかけの一つであり、本質は「紹介した行動が正当に評価されること」や「制度が公平に運用されていること」です。
支給タイミングの決め方
紹介報酬の支給タイミングは、社員と企業の双方にとって重要な設計要素です。よくあるのは以下のような段階的支給です。
- 書類選考通過時に一部支給
- 入社時に残額の一部支給
- 入社後3か月経過時に全額支給
このように段階を踏むことで、紹介者が「すぐ辞めたらどうしよう」と不安を抱えずに済みます。企業にとっても、定着を前提とした支給であれば費用対効果を見込みやすく、制度の持続性にもつながります。
金銭以外の報酬
紹介に対する報酬は、必ずしも現金だけに限る必要はありません。たとえば「特別休暇を1日付与」「カフェチケットや社食クーポンを支給」「社内イベントや上司との食事会に招待」など、ちょっとしたご褒美でも社員にとっては動くきっかけになります。
特に金額のインパクトではなく、紹介がちゃんと評価される実感が伝わることが重要です。現金報酬ほど税務処理に気を使わずに済むケースもあり、制度導入時のハードルを下げやすいのも利点です。
ただし、見送り理由を共有しないまま「社内表彰だけで終わり」というような制度は、かえって制度への不信感につながることもあります。金銭と非金銭のバランスをとりつつ、自社に合った「続けやすい仕組み」として設計するのが現実的です。
社員が安心して紹介できるリファラル制度とは?
ここでは、社員が安心して紹介に踏み切れるようにするためのポイントを、制度運用の観点から具体的に解説します。紹介ルールの明文化から、導線の整備、紹介後のトラブル防止まで、実践的な視点で見ていきましょう。
紹介ルールを明文化する
紹介制度を利用してもらうには、「誰をどう紹介できるのか」「その後どう関わるのか」といった不安を払拭するルール設計が不可欠です。ここでは、制度運用時に必ず決めておくべき具体項目を整理します。
リファラル採用のルール例
- 前職の同僚や知人はOK
- SNSでつながった相手でも、一定の接点(会話やプロジェクト経験など)があればOK
- 転職意向のない人に無理やり声をかける行為は禁止
- 家族や血縁関係者は除外(公平性の観点から)
曖昧な基準のまま進めると、紹介の質にもばらつきが出ます。リストや事例を社内FAQで共有すると、より動きやすくなります。
導線は1本に統一する
紹介の流れが面倒だと、制度は形だけになります。以下のように、導線を1本に絞るのが効果的です。
- 専用フォーム(Googleフォームや採用管理ツールなど)を用意
- 必要項目は「紹介者名・被紹介者の氏名・連絡先・軽い経歴やコメント」程度にとどめる
- 手続きが終わったら自動で受付通知が届く仕組みを整備
メールでの口頭連絡、Slack経由、個人宛DMなどバラバラに受付けると管理が煩雑になるため、窓口は一本化することをおすすめします。
紹介者の心理的ハードルを下げる
「もし採用されなかったら気まずい」「うまく定着しなかったら申し訳ない」と社員が感じてしまうと、紹介のハードルは上がります。そのため、以下を明確に伝えることが大切です。
- 選考は通常通り行う。紹介者は評価や決定に関与しない
- 不採用時の連絡はすべて人事部が対応。紹介者が断る必要はない
- 定着・活躍の責任は会社にあり、紹介は“協力行動”として扱う
社内イントラや制度ガイドラインにこの点を明記し、「紹介=責任」にならない空気をつくることが制度活性化のカギです。

トラブル防止のルールを整備する
たとえば以下のような事態への対応方針を、制度スタート時にあらかじめ設けておきましょう。
- 同一人物を複数人が紹介した場合は、受付順で優先(または連名で報酬を分ける)
- 被紹介者がすでに応募済みだった場合は紹介対象外
- 詐称・虚偽があった場合は報酬対象外とし、不正事案として報告義務あり
制度の信用性を守るためにも、「どうするか決めておく」ことが何より重要です。

紹介後の対応フローを明確にする
紹介後に「その後どうなったのか何も知らされない」「採用されなかったことを自分で伝えた」というケースは、制度への信頼を大きく損ないます。
不採用時の通知ルール(人事が代行して伝える等)や、紹介者と候補者の関係性を尊重した連絡フローを設けておくことで、トラブルを防げます。また、虚偽の経歴紹介や、紹介報酬を目的とした不適切な推薦などが起こらないよう、ガイドラインを作っておくと安心です。

リファラル制度を活用してもらうための運用と浸透策
社員が「制度を理解している」「紹介しても問題なさそうだ」と思えたとき、はじめて制度は動き始めます。ここでは、リファラル制度を社内に浸透させ、使われる仕組みにするための実践ポイントを紹介します。
導入時は「全社向け」に正式リリースする
制度を本格的に活用してもらうには、全社への正式な説明を行いましょう。朝会や全社会議などの場で、制度の目的や背景、紹介の流れ、報酬条件などを具体的に伝えます。
あわせて、現場マネージャーには事前に制度の概要と導入意図を共有しておくと、部下からの相談にもスムーズに対応できます。
特に「誰を紹介すべきか迷っている」といった場面では、マネージャーの一言が背中を押す場面も少なくありません。制度の理解者を現場に置くことで、紹介の芽が拾われやすくなります。
制度を社内に根づかせるには、「本気で始める」というメッセージが必要です。全社MTGや朝会などの場で、制度の目的・対象職種・紹介方法をまとめて共有することで、社員全員に同じ理解が行き渡ります。
社内ポータルやFAQで情報を見える化する
導入後に「どこを見れば紹介できるのか」が分かりやすくなるよう、社内ポータルなどに制度専用ページを用意しましょう。制度概要・紹介手順・報酬条件・よくある質問をまとめておくことで、社員が自分のペースで情報にアクセスできます。
紹介申請のフォームはシンプルな構成にし、入力の手間を最小限に抑えることもポイントです。面倒さが先に立つと、紹介そのものが敬遠されてしまいます。
どこを見て、どう申請すればいいかが一目でわかる状態をつくりましょう。導線はシンプルに、フォームは最小限に。迷いと手間をなくすことがポイントです。
活用状況の見える化と定期モニタリング
制度を「放置しない」ためには、活用状況の可視化が不可欠です。以下のような指標を月次・四半期単位で集計し、定期的に社内で共有しましょう。
- 紹介件数
- 書類選考通過率
- 採用決定数
- 入社後3ヶ月の定着率
- 紹介から内定までの平均日数
これらをスプレッドシート等で運用し、月報や四半期ごとの制度レビューに使えば、改善の方向性が明確になります。「報酬額を上げるべきか」「もっと対象職種を広げるか」といった意思決定がしやすくなります。
また、制度の利用状況を可視化して社内に共有すれば、「制度はちゃんと動いている」という印象が伝わり、関心を保ちやすくなります。月1回の簡単なレポートやSlack投稿だけでも効果があります。
偏りや課題をチェックするモニタリングの仕組み
紹介が「一部の部署に偏っている」「特定の職種ばかりが紹介されている」といった兆候は、制度がうまく機能していないサインかもしれません。以下のような分析をして、偏りの背景を可視化しておきましょう。
- 部署別の紹介件数
- 紹介された職種・勤務地・属性の偏り
- 紹介している社員の年次や役職
たとえば若手社員からの紹介が多く、ベテラン層が動いていない場合は「制度を知らない」「紹介対象が思いつかない」などが想定されます。その場合、ミドル層に向けて「紹介しやすい職種一覧」や過去の成功事例をピンポイントで配信すると反応が変わることがあります。
リファラル制度を含む「全体採用戦略」の整理
リファラル制度に頼りすぎると、紹介が集まらなかったときの反動が大きくなります。制度疲れや現場の不信感を避けるためにも、「他のチャネルとの使い分け」を明確にしておきましょう。
- エンジニア・コーポレート部門 → リファラルやダイレクトが有効
- マネジメント層 → リファラルだけでは候補が足りないためエージェント併用
- 緊急性が高い案件 → 求人媒体で母集団形成+並行してリファラルも動かす
採用チャネル別に「どこで何を狙うか」を整理しておけば、リファラル制度に過剰な期待がかかることも防げます。人事内でチャネルごとの使いどころを共有し、制度をチーム全体で位置づけられている状態を目指すことがポイントです。
リファラル採用制度の設計時に確認したい10のポイント
制度を作っても「動かない」「紹介が集まらない」とならないために。制度設計の段階で、以下の項目が満たされているかを確認してみてください。
- 報酬の金額と支給タイミングが明確である
- 金銭以外の報酬(休暇、チケット、表彰など)も検討している
- 「誰を紹介してよいか」の基準が明文化されている
- 紹介者が責任を感じずにすむ運用(不採用連絡は人事など)が整っている
- 紹介の方法が一本化されている(例:専用フォーム経由のみ)
- 重複紹介や虚偽情報に関するルールが整備されている
- 社内向けのFAQやガイドラインが用意されている
- 社内ポータルやSlackに専用の告知・相談チャンネルがある
- 紹介件数や内定実績など、制度の運用状況を社内で定期的に共有している
- 制度の見直しと改善サイクル(例:半年に1回)が明確になっている
制度の成否は「報酬」よりも「仕組みと安心感」が握っています。まずはこの10項目から、自社の制度を見直してみてください。
よくある質問(FAQ)
最後に、リファラル採用の制度を導入するにあたり、よくある質問と回答をご紹介します。
- リファラル制度はどの職種にも適用すべきですか?
-
必ずしもすべての職種を対象にする必要はありません。採用ニーズの高い職種や、社内に該当人材とのつながりがありそうな領域からスタートすると効果的です。
- 金銭報酬は必須ですか?どの程度が妥当ですか?
-
必須ではありませんが、行動喚起の観点からインセンティブは有効です。金額の相場は5万〜10万円程度が多く、内定・入社・定着など段階的に支給する企業もあります。ただし、金銭に偏りすぎない報酬設計(休暇や社内表彰など)も検討しましょう。
- 法的に気をつけるべきポイントはありますか?
-
雇用関係がない第三者からの紹介に報酬を支払う場合、職業安定法に抵触する可能性があります。
紹介者を「現職社員・元社員」に限定し、社内規定として明文化することが必要です。また、報酬の課税対象や経費処理についても社労士や税理士に確認しておくと安心です。 - 社員が紹介しやすくなるために必要なことは?
-
「誰に、どんなタイミングで紹介すればいいのか」が明確であることが重要です。制度の概要、対象職種、紹介の流れを分かりやすく整備し、いつでも確認できるよう社内ポータルやSlackチャンネルで公開しておきましょう。成功事例の共有も有効です。
- どのくらいの頻度で見直しが必要ですか?
-
半年〜1年に1回程度の定期的な見直しをおすすめします。紹介数や採用数のデータ、社員からの声をもとに、対象職種や報酬設計のチューニングを行いましょう。制度が止まっている印象を与えないよう、アップデートの内容も都度社内へ周知するのがポイントです。
エンジニア採用なら社内SE転職ナビ

「社内SE転職ナビ」は、3,000社以上との取引実績をもとに、正社員・フリーランスの両軸でエンジニア採用を支援できるサービスです。情報システム部門やコーポレートエンジニアはもちろん、開発・インフラ領域など幅広いスキルを持つ即戦力人材との出会いを実現します。
自社の魅力を直接伝えられるダイレクトリクルーティング機能もご利用可能で、採用コストを抑えつつ、カルチャーに合う人材との接点を生み出せます。求人広告やリファラル採用だけでは届かない層にリーチしたい企業様にとって、選択肢を広げる有効な手段となります。制度設計から活用支援まで含めた柔軟なご提案も可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
まとめ
リファラル採用は、制度設計と社内への浸透が成果を左右します。制度の目的とルールを明確にし、報酬は金銭に限らず社風に合った形での設計が効果的です。
また、制度を日常の中に置く運用が重要で、社内ポータルやSlack活用、成功事例の共有が浸透を後押しします。
さらに、導入後も紹介実績の可視化や定期的な制度の見直しを行うことで、社員の関心を維持しやすくなります。リファラルだけに依存せず、全体の採用設計の中で活用するようにしましょう。