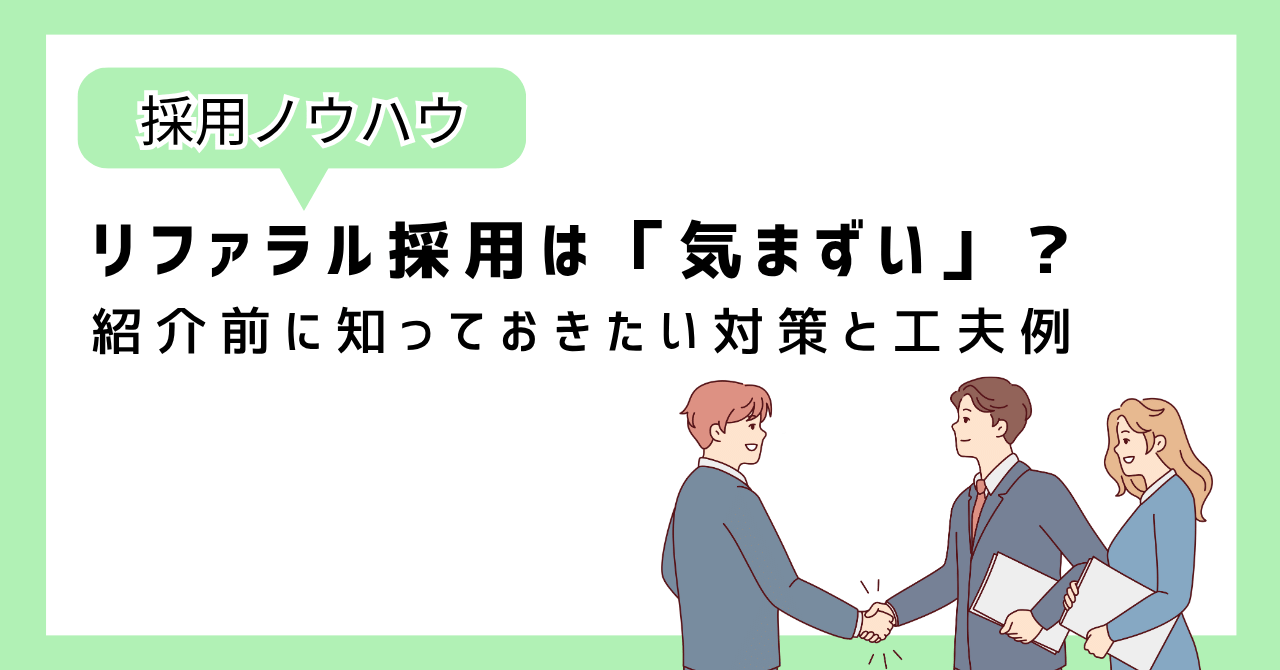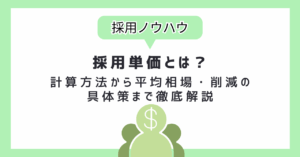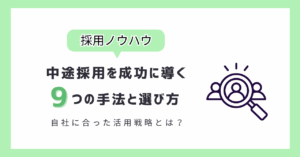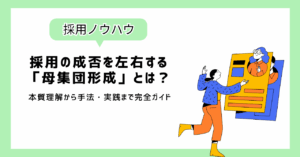リファラル採用はコストを抑え、マッチ度の高い人材を集めやすい手法として注目されています。しかし実際には「紹介したのに不採用で気まずい」「辞めたいのに辞めづらい」など、人間関係のトラブルにつながることも。
この記事では、リファラル採用が気まずくなりやすい理由と、事前にできる対策・運用上の工夫をわかりやすく解説します。
1分でわかる!記事のポイント
- リファラル採用は、紹介者と候補者の心理的ハードルが高く、気まずさが起こりやすい
- 「紹介=選考のきっかけ」と線引きし、情報共有や連絡の役割分担を明確にすることが重要
- 面談や社内見学で事前に“肌感”をすり合わせ、紹介者に負担をかけずに判断できる場をつくる

エンジニア採用、こんな課題ありませんか?
- 技術力だけでなく、事業理解も必要だけど、見極めが難しい
- 社内システムを支える柔軟な対応力を持つ人材がなかなかいない
- 企業文化にフィットするエンジニアを採用したい
「社内SE転職ナビ」なら、技術×カルチャーの両面からマッチするエンジニアをご紹介できます。エージェントによる丁寧なヒアリングに加え、企業から直接アプローチできるダイレクトリクルーティング機能もご利用可能。貴社の採用スタイルに合わせて、最適な候補者との出会いをサポートします。
なぜリファラル採用は気まずくなりやすいのか
リファラル採用は、信頼できる人材と出会える手法として多くの企業に広まっていますが、運用の仕方によっては「気まずい」と感じる場面が生まれやすい制度でもあります。
その理由の多くは、紹介というプロセスに人間関係が強く絡むことにあります。
紹介者と候補者のあいだに私的なつながりがあることで、通常の採用とは異なる心理的なプレッシャーが発生します。たとえば、次のようなケースが挙げられます。
- 紹介した相手が不採用になり、関係がぎくしゃくする
- 入社後にミスマッチが起き、紹介者が責任を感じてしまう
- 周囲から「身内びいき」や「コネ入社」と見られ、本人も気まずさを感じる
- 候補者が「断りづらい」「辞めづらい」と感じ、判断が鈍る
制度そのものに問題があるわけではありません。ただ、感情や関係性が絡みやすい構造だからこそ、誤解や負担が生まれやすいのです。こうした「気まずさ」があることを前提に、制度をどう運用するかが問われています。

「紹介した側」「された側」それぞれの気まずさ
リファラル採用における「気まずさ」は、紹介した側とされた側の両方に起こり得ます。それぞれの立場で感じやすいプレッシャーや不安を見てみましょう。
紹介する側の不安やプレッシャー
紹介者は、「紹介した手前、結果がどうであれ自分に何か影響があるのでは」と不安を抱えがちです。
- 選考に落ちたとき、相手との関係がぎこちなくなるのではと心配になる
- 入社後にすぐ辞められた場合、「なぜこの人を紹介したの?」と社内で問われるのではと感じる
- 「紹介者としての責任感」に縛られすぎて、候補者との関係性が負担になることもある
紹介自体は善意の行動でも、結果次第で紹介者の立場が微妙になる可能性があるため、慎重になる人も少なくありません。
紹介される側の心配や迷い
一方で、紹介される側にも、紹介だからこそ感じる独特のプレッシャーがあります。
- 落ちた場合、「紹介してくれた人に申し訳ない」と感じてしまう
- 入社後に「ちょっと合わないかも」と思っても、辞めにくくなる
- 本音で会社の話をしてくれているのか、多少“盛られて”いないかという不安がある
紹介という関係性があることで、「断りにくい」「辞めにくい」と感じてしまい、判断を鈍らせてしまうケースもあります。
 エージェント・Hongo
エージェント・Hongoリファラル採用は、紹介者と候補者の関係が近いぶん、ちょっとした行き違いがあとあと気まずさにつながるケースもあります。お互いに悪気がないからこそ、制度や運用でそれをカバーする設計が求められると感じます。
気まずくならないために紹介前にできること
リファラル採用をうまく機能させるには、「紹介の仕方」そのものに一工夫が必要です。ただ声をかけるだけでは、お互いに余計な気遣いや誤解が生まれやすくなります。紹介する前にどんな話をしておくか、どんな伝え方をするか。そこに少し気を配るだけで、関係性がぎくしゃくするリスクは大きく減らせます。
あくまで“選考”であることを強調する
紹介するときに忘れがちなのが、「これはあくまで選考だ」という前提を共有することです。声をかけただけで「ほぼ内定」と受け止められてしまうと、万が一落ちたときにお互い気まずくなります。
「自分は推薦するけど、選考は会社が判断するから、そこはフラットに見てもらうことになるよ」そんな一言を添えておくだけでも、後からの関係性に無駄な重圧がかかりにくくなります。
社内の情報は“良い面も悪い面も”共有する
紹介したい気持ちが強いと、つい「働きやすい」「人がいい」といったポジティブな側面だけを伝えてしまいがちです。
でも、入社後にギャップを感じて「話と違った」となれば、それこそ紹介した自分との関係が気まずくなります。
たとえば、
- 繁忙期にはかなり忙しくなる
- 部署によって雰囲気が違う
- 技術環境がやや古い部分がある
といった要素も、正直に話しておくほうが安心です。良い面とあわせてリアルも伝えておけば、候補者の判断もブレにくくなります。
紹介相手の希望をあらかじめ確認する
そもそも、「今はまだ転職を考えていない」「興味はあるけど選考には進みたくない」という人もいます。こちらとしては善意で声をかけたつもりでも、本人が断りにくさを感じてしまうと、それ自体がストレスになってしまいます。
いきなり会社の話を始めるよりも、まずは何気ない会話の中で、
- 転職のタイミングについてどう考えているか
- どんな働き方に関心があるか
- 会社に対してどんな印象を持っているか
といったことを探っておくとスムーズです。そのうえで「もし気になるようなら、紹介してみようか?」という自然な流れをつくれば、相手にプレッシャーをかけずに済みます。



紹介するとき、「どのくらい本気で転職を考えているのか」を軽く確認しておくだけでも、お互いに気を遣いすぎずに済むことが多いです。紹介者自身も、自信を持って声をかけられるようになります。
ミスマッチを防ぐコミュニケーション方法
リファラル採用で後から「こんなはずじゃなかった」となるのは、選考前に十分な接点や情報のすり合わせができていない場合がほとんどです。
紹介された側にとっては、紹介者がどんなに信頼できる人でも、会社そのものが自分に合うかどうかは話を聞いただけでは判断できません。紹介後すぐに選考へ進めるのではなく、その前段階としてのコミュニケーションの場を丁寧に設けることが、ミスマッチを防ぐ鍵になります。
カジュアル面談で「雰囲気のすり合わせ」を
選考とは切り離した“カジュアル面談”は、紹介された側が企業とフラットに話せる貴重な機会です。
履歴書やスキルの話に偏らず、雰囲気や考え方のすり合わせを目的とすることで、候補者自身も「合う・合わない」を判断しやすくなります。紹介者が同席するかどうかはケースバイケースですが、気まずさを避けたい場合は「会社側だけで実施する」ほうが無難です。
紹介者の顔を立てるための場ではなく、候補者が自由に質問できる空気をつくることが大切です。
イベント・オフィス見学で空気感を伝える
「この会社、自分に合いそう」と感じてもらえるかどうかは、実際の空気感や人の雰囲気を通じて判断されるものです。
一方で、面接だけでは会社の実像が見えづらく、入社後に「想像と違った」となるリスクがあります。そうしたミスマッチを防ぐには、選考に入る前段階で、候補者が職場に自然に触れられる機会を設けることが効果的です。たとえば、次のような方法があります。
社内勉強会やランチ会に参加してもらう
あくまで参加自由・聴講型で、「この会社ではどんな会話が交わされているのか」「どんな知識や価値観を共有しているのか」を肌感覚でつかめます。社内の温度感や知的好奇心のレベルを知るにはぴったりの場です。
チームの雑談や業務の合間に自然と混ざってもらう
業務のすき間時間に、雑談レベルで話す相手がいるだけで、「この職場ってこういう感じなんだな」という安心感が生まれます。カジュアルな場だからこそ出る空気が、候補者の印象を大きく左右します。
たとえば、ランチのあとにオフィスを案内しながら「このあと少し話せる人がいるんだけど、顔合わせてみる?」と軽く声をかけるだけでも、自然な流れで雑談に加わってもらえます。候補者にとっても“見られている場”ではない分、本音で話しやすくなりますし、社員側も「素を見てもらう場」として構えずに済みます。
少人数での見学ツアーや1on1の対話機会をつくる
オフィスのレイアウトや働き方を直接見てもらうことで、候補者の“想像の中の会社”が“実在する場所”へと変わります。さらに現場メンバーと一対一で話す機会があれば、自分がその場にいる姿をより具体的に想像できるようになります。
こうした接点は「入社を前提とした場」ではないため、候補者側の心理的ハードルも低く、リファラル特有の“断りにくさ”を和らげる効果もあります。



カジュアル面談やオフィス訪問は、候補者にとっても企業にとっても有効です。選考とは別の場で、雰囲気やスタンスの確認ができると、「入ってから違った」というミスマッチを減らすことができます。
気まずさを避けるための工夫例
リファラル採用は制度として魅力的である一方、ちょっとしたすれ違いや誤解が「気まずさ」につながりやすいのも事実です。紹介する側・される側のどちらかが気を遣いすぎたり、役割の線引きが曖昧なまま進んでしまうと、あとから関係性にモヤモヤが残ってしまいます。
ここでは、そうした事態を避けるために、実際の運用で取り入れやすい工夫を紹介します。
紹介者と会社の役割を分けておく
「紹介=責任」になってしまうと、紹介者はプレッシャーを感じてしまいます。制度として重要なのは、「紹介はきっかけにすぎず、選考や判断は会社が行う」という立て付けを明確にしておくことです。
たとえば、
- カジュアル面談や選考の場には紹介者を同席させず、会社が主導する
- 不採用時の連絡やフォローは会社が責任をもって行う
- 紹介者に「合否の共有」や「理由の説明」を求めない運用ルールにしておく
こうした分離によって、紹介者は「ただの案内役」でいられ、紹介される側も余計な気遣いをせずに済みます。
紹介者・候補者の関係性に配慮した連絡の工夫
リファラル採用では、誰が誰に何を伝えるかによって、空気感が大きく左右されます。とくに落選時の連絡や、入社後の評価が絡むフィードバックはセンシティブな場面です。たとえば、
- 不採用の場合、紹介者ではなく候補者本人に会社側から直接伝える
- フィードバックを紹介者に伝えるかどうかは、本人の同意を得たうえで判断する
- 入社後のフォローは人事や上司が担い、紹介者に頼りきらない
こういったルールを事前に設けておけば、紹介者・候補者の双方にとって心理的な負担が少なくなります。
制度設計で“紹介しやすさ”を後押しする
紹介者が「変に気を遣うから紹介したくない」と感じる背景には、制度そのものへの不安やモヤモヤがあることも少なくありません。そのため、制度設計の段階で“紹介しやすさ”を意識することが大切です。
- インセンティブの支給は「入社後〇ヶ月の定着」を基準にすることで、紹介者に過度な責任がかからない
- 紹介しても報酬がもらえなかった、という誤解が生まれないよう、ルールを文書化して社内に共有する
- 「どんな人を紹介すればいいか」がわかるように、対象ポジションや求める人物像を明文化しておく
制度が曖昧なままだと、紹介自体が敬遠されてしまいます。紹介者に「安心して声をかけられる環境」を整えることが、制度を継続的に回すうえで欠かせません。



「紹介したけれど、選考の進み方がわからず気を遣った」といった声は一定数あります。紹介後の流れを会社主導で進めることで、紹介者・候補者のどちらもストレスを感じにくくなります。


リファラル採用を気まずくしないために企業側ができること
リファラル採用で気まずさが生まれる背景には、紹介する人・される人だけでなく、企業側の設計や運用の“空気”が影響しているケースも少なくありません。
制度そのものは良くできていても、ちょっとした伝え方や運用の仕方ひとつで、社員が紹介に二の足を踏んだり、関係性がこじれるような状況をつくってしまうことがあります。
だからこそ、企業・人事としてできることは意外と多くあります。
紹介者に過度な期待をかけすぎない
まず大切なのは、「紹介してくれた人が、結果まで背負う必要はない」という空気を社内に根づかせることです。
「紹介したのにすぐ辞めた」「なんでこの人を?」といった声が紹介者に向いてしまうと、次の紹介がしにくくなります。
制度としても、文化としても、「紹介はあくまで機会づくり」という認識を明確にし、責任の所在は会社側にあることを強調する姿勢が大切です。
トラブル時の対応フローを事前に決めておく
不採用時や、入社後のトラブルが起きたときの対応が曖昧だと、気まずさはより深まります。たとえば「不採用の連絡が紹介者からだった」「辞めた理由を紹介者が聞かされた」など、誰がどこまで関わるべきかを整理しておかないと、当事者間で火種が残りかねません。
以下のような点を、あらかじめ制度の一部としてルール化しておくと安心です。
- 不採用時の連絡は必ず会社側が行う
- フィードバック共有は、本人の同意を得た場合に限る
- 入社後のフォローは紹介者ではなく、現場上司・人事が行う
紹介者・候補者に気を遣わせない仕組みをつくることが、制度を長く続けるための土台になります。


制度の目的を正しく伝え、社内理解を深める
制度そのものがうまくできていても、「なぜリファラル採用をやるのか」が共有されていないと、社内で誤解が生まれやすくなります。「インセンティブ目当てで人を連れてくるんじゃないか」といった声が出てしまうと、制度への信頼も薄れてしまいます。
制度導入時や更新時には、
- 採用におけるリファラルの意義(会社にとって、社員にとって)
- 想定している紹介のスタンス(強制ではないこと)
- 不採用・早期退職も想定内という前提
などを、社内説明資料や定例ミーティングなどで丁寧に伝えることが大切です。社員の理解度や納得感が高まることで、「紹介しても大丈夫」「断られても問題ない」という心理的安全性が社内に広がっていきます。



紹介者が制度にプレッシャーを感じすぎると、次の紹介につながりにくくなります。紹介しただけで責任につながるような空気は避け、会社として紹介しやすい環境を整えることが大切です。
エンジニア採用なら社内SE転職ナビ


リファラル採用だけでは出会えない即戦力人材にアプローチしたい人事担当者様へ。「社内SE転職ナビ」では、正社員・フリーランス両方の採用支援が可能です。また、3,000社以上との取引実績を活かし、ダイレクトリクルーティングによる自社採用もご支援しています。
貴社の魅力を直接伝え、カルチャーに合うエンジニアとつながる場としてご活用いただけます。採用コストを抑えつつ定着率を高めたい企業様は、ぜひご相談ください。
まとめ|リファラル採用は「制度と配慮」でうまくいく
リファラル採用が気まずくなるのは、人間関係が近いからこそ。でも、紹介前のひと言や制度の設計次第で、関係がこじれるリスクはぐっと減らせます。紹介する側・される側の心理に配慮し、企業としての運用ルールも整えていくことで、「紹介してよかった」と思える仕組みがつくれます。