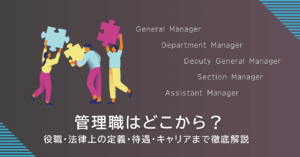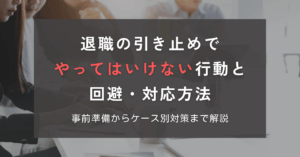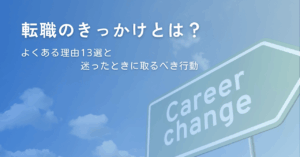各企業のIT化やDXが進む一方で、問題になっているのが情報システム部門で働くIT人材の不足です。現場からは「専門的な知識を持つ人材を採用できない」といった声もあがっています。近年、情シスのIT人材不足を解決する手段として注目されているのが「アウトソーシング」です。
本記事では、情シス業務をアウトソーシングするメリット・デメリットや、おすすめのサービスなどについて解説します。アウトソーシングを検討している情シス部門の方は、ぜひ最後までご覧ください。
情シスのアウトソーシングとは
情シスのアウトソーシングとは、社内の情報システムに関する業務を、外部の専門的な知識や技術を持つ企業に委託することです。企業のIT化やDXが加速する一方で、深刻な問題となっているIT人材の不足を解消するために、アウトソーシングを採用するケースが増えています。
委託対象の主な業務は以下のとおりです。
- PCの初期設定(キッティング)
- 社員からの問い合わせに対応するヘルプデスク業務
- サーバーやネットワークの構築・運用・保守
- セキュリティ対策の監視・運用
企業は、外部のプロフェッショナルに業務を任せることで、人材不足の解消やコスト削減などの課題を解決します。大企業だけでなく、専任の担当者を置くことが難しい中小企業にとっても、事業成長を支える強力な選択肢となるでしょう。
情シスをアウトソーシングするメリット
情シス業務のアウトソーシングを検討するには、具体的にどのようなメリットが得られるのかを知る必要があります。なかには自社だけで解決できるものもあるかもしれません。ここでは、アウトソーシングがもたらす主なメリットを3つ紹介します。
専門知識とノウハウを即戦力として活用できる
アウトソーシングサービスを利用する最大のメリットは、ITに関する高度な専門知識と豊富な経験を持つプロフェッショナル集団を、即戦力として活用できる点です。
IT技術の進化スピードは速く、クラウド技術やセキュリティ分野を中心に、新しい脅威やサービスが登場します。最新情報を社内の限られた人員だけで常にキャッチアップし、適切な対策を講じ続けるのは困難です。
外部の専門家に委託すれば、社内では対応が難しかったハイブリッドクラウド環境の構築や、巧妙化するサイバー攻撃への防御策などの高度な課題にも対応できます。社内システムの安定性が向上するだけでなく、社員が安心して業務に取り組めるIT環境が構築され、企業全体の生産性向上にも貢献するでしょう。
人件費や採用コストを削減できる
情シス担当者を正社員として1名雇用すると以下のようなコストが必要となります。
- 給与・賞与
- 採用活動にかかる広告費や人材紹介会社への手数料
- 選考に関わる社員の時間的コスト
- 入社後の社会保険料や福利厚生費
- 業務に必要なPCやソフトウェアの費用
- 継続的な研修費用
アウトソーシングを活用すれば、採用活動や人材育成に関連するコストが一切不要です。必要なスキルセットを持つ人材を、必要な期間・必要な業務量に応じて柔軟に利用できるため、人件費を「変動費」として扱えます。
事業の拡大・縮小や、季節的な業務量の変動が激しい企業には、経営の安定化に直結するメリットです。採用や教育に費やしていた費用と時間を、戦略的な分野へと投資できるようになるのです。
情シス人材の育成が不要
アウトソーシングを導入すれば、自社で情シス人材を育成する必要がなくなります。
IT人材の採用競争が激化しているなか、多くの企業は優秀な人材の確保に苦戦しています。未経験者や若手を採用したとしても、プロとして通用する情シス担当者となるまでには、教育コストと時間が必要です。
業務を外部に委託すれば、契約後すぐに、高度なスキルと豊富な経験を持つプロフェッショナルチームに仕事を任せられます。自社で情シス人材を育成せずとも、大企業と遜色のない質の高い情シス機能を維持・運用可能です。
また、担当者の急な退職や休職による「業務ブラックボックス化」や「業務停滞」といった経営リスクを軽減できる点も、見逃せない大きなメリットです。
情シスをアウトソーシングするデメリット
アウトソーシングには多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。メリットだけに目を向けていては、導入後に「こんなはずではなかった」と悔やみかねません。事前にデメリットを正しく理解し対策を講じましょう。
社内にITノウハウが蓄積しにくい
情シス業務を外部へ委託した場合、日々の業務で得られるはずの経験(ノウハウ)が社内に蓄積されない点がデメリットです。業務プロセスが委託先の中で完結してしまうため、発生した問題や解決方法を社内の誰も把握していない、という「業務のブラックボックス化」に陥る危険性があります。
将来的に「契約を終了し内製化(自社運用)に切り替えたい」「より良いサービスを提供する別の委託先に変更したい」と考えた際に、社内に必要なノウハウが全くなければ、システムの引き継ぎは困難です。スムーズな移行が不可能になりかねません。
業務の属人化を防ぐためにアウトソースした結果、かえって特定の業者に縛られてしまうという事態には注意しましょう。
スピーディな対応が難しいケースもある
アウトソーシングは、契約時に交わすSLA(Service Level Agreement:サービス品質保証)に基づいてサービスが提供されます。SLAには、対応時間や対応範囲、問題解決までの目標時間などが定められており、委託先は契約の範囲内で業務を遂行します。
契約範囲外の突発的なトラブルや、深夜・休日に発生した緊急性の高いシステム障害、契約書に記載のない新規の作業依頼などが発生した場合は、すぐには対応してもらえません。
また、委託先の担当者は社内に常駐しているわけではないため、現場の状況を直接目で見て確認できません。そのため、物理的・心理的な距離が、対応の障壁となるケースも想定しておく必要があるでしょう。
情報漏洩リスクが増す
アウトソーシングを利用する際には、自社の業務データや顧客情報、取引先の情報といった機密性の高い情報を外部の業者に預けなければなりません。どれだけ対策を講じても、情報漏洩のリスクは高まります。
委託先の管理体制に不備があったり、セキュリティ意識が低かったりした場合、情報漏洩事故による企業の社会的信用の失墜や、多額の損害賠償にもつながりかねません。
最悪の事態を回避するには、委託候補先のセキュリティポリシーや情報管理体制を、第三者の視点で徹底的に調査・確認しましょう。「プライバシーマーク」などの認証や、従業員への教育体制といった確認すべき点は多岐にわたります。また、契約後も、定期的な監査の実施や報告を義務付けるなど、継続的な管理体制の構築が重要です。
アウトソーシングしやすい情シスの業務
情シスの業務には、アウトソーシングしやすい領域と、社内で担うべき領域があります。
なかでも外部委託に適しているのは、以下の2パターンの業務です。
- 作業が定型化されており、一定の品質で再現しやすい業務
- 高い専門性が求められ、自社内で常時対応するのが難しい業務
たとえば、パソコンのキッティングやヘルプデスクのように手順が明確な業務、あるいはセキュリティ監視のように高度な知識と24時間体制が必要な業務が該当します。
ここでは、多くの企業が実際にアウトソーシングしている代表的な3つの業務を紹介します。
ヘルプデスク業務
社員から寄せられる「パソコンが起動しない」「メールが届かない」などの問い合わせに対応するヘルプデスク業務は、外部委託しやすい代表的な業務のひとつです。
難易度自体は高くないものの、問い合わせの件数が多く、対応に多くのリソースを割かれるため、情シス担当者の業務を圧迫しがちです。
外部に委託する際は、問い合わせ内容に応じた対応フローや、FAQの整備・共有が欠かせません。事前にナレッジをしっかり用意しておけば、一定水準以上の品質を担保したまま、社外に業務を移行できます。
問い合わせ対応を手放すことで、社内の情シス担当者は戦略的なIT企画や改善業務に時間を使えるようになり、組織全体の生産性や従業員満足度の向上にもつながります。
クラウド・サーバーの運用保守
企業の基幹システムを支える物理サーバーや、AWS・Azureなどのクラウド環境の運用・保守も、アウトソーシングが進んでいる領域です。
これらは24時間365日安定して稼働させる必要があり、高度な専門知識と継続的な注意力が求められるため、社内リソースだけで対応し続けるのは現実的ではありません。
外部委託では、パフォーマンス監視や定期バックアップ、パッチ適用、障害対応などを専門業者に任せることで、自社で同様の体制を構築するよりもコストや人材負荷を抑えながら、高いレベルでの安定運用を実現できます。
技術のアップデートも頻繁に求められる領域なので、最新環境への対応力という意味でも、専門パートナーとの連携は有効です。
セキュリティ対策の運用・監視
情報漏えいやサイバー攻撃から企業を守るセキュリティ対策は、もはや経営課題のひとつです。
中でも、運用・監視といった実務部分はアウトソーシングが有効に機能する領域です。
ファイアウォールやWAFなどのセキュリティ機器の設定・運用管理、不審な通信やアクセスのログ監視、PC端末の動作をチェックするEDRによる監視、インシデント発生時の初動対応などは、専門知識と継続的な対応体制が必要です。
特に、攻撃手法が日々進化しているなかで、外部のセキュリティベンダーは世界中の脅威情報をリアルタイムで分析しているため、最新の防御策を迅速に取り入れやすい点もメリットです。
社内で判断を下すべき部分を明確にしつつ、常時対応が求められる領域は外部に任せることで、セキュリティレベルを維持しながら負担を分散できます。資と言えるでしょう。
情シスのアウトソーシングにオススメのサービス
情シスのアウトソーシングを検討するにしても、「何を基準に選べば良いのかわからない」という方もいるでしょう。ここでは、多くの企業から支持されている代表的な3つのサービスをピックアップし、特徴を紹介します。自社に合ったサービスを見つける判断材料としてください。
情シス代行パック(エイネット株式会社)
エイネット株式会社が提供する「情シス代行パック」は、柔軟性が特徴のサービスです。顧客企業の状況やニーズ、予算に応じて、専門のITエンジニアが常駐する「常駐型」と、リモートでサポートを提供する「リモート型」が選択できます。
サポート範囲も広く、以下のような業務の対応が可能です。
- 社員からの問い合わせ対応
- PCのセットアップ
- IT資産台帳の管理
- ソフトウェアライセンスの最適化
- IT戦略の立案やIT予算の策定支援
「まずはヘルプデスク業務からスモールスタートしたい」という企業から、「経営層の右腕となるIT戦略パートナーが欲しい」という高度なニーズを持つ企業まで対応できます。あらゆるフェーズの企業課題に寄り添ったソリューションを提供できる点が大きな魅力です。
クラウド゙SE(株式会社Gizumo)
株式会社Gizumoが提供する「クラウドSE」は、クラウド環境の構築・運用に特化したサービスです。市場をリードするAWSやMicrosoft Azure、GCPといった主要なパブリッククラウドに精通したプロフェッショナルなエンジニアによる支援が受けられます。
単なるサーバーやネットワークといったインフラの構築・運用保守にとどまりません。次のような高度で先進的な領域までサポート可能です。
- アプリケーションの開発とインフラの運用の連携
- ビジネスの変化に迅速に対応していく「DevOps」の導入支援
- セキュリティリスクを洗い出して堅牢なセキュリティ体制の構築
クラウドを戦略的に活用し、DXを加速させたい企業に最適なパートナーです。
ヘルプデスク・社内SE代行 | 株式会社Gizumo – 人の未来を創る –
情シスSAMURAI(クロス・ヘッド株式会社)
クロス・ヘッド株式会社が提供する「情シスSAMURAI」は、30年以上の実績と信頼性の高いノウハウを基盤とした、情シス業務全般のワンストップ代行サービスです。以下のような業務をカバーしています。
- 日々のヘルプデスク対応
- サーバー・ネットワークといったインフラの24時間監視
- PCやソフトウェアといったIT資産の管理
企業の事情や要望に応じて、サービス内容を柔軟にカスタマイズできる点が魅力です。「週に1回の定期訪問サポートから試してみたい」「全社的なPCリプレイスのプロジェクトだけを期間を区切って手伝ってほしい」といったニーズにも応えてくれます。
初めてアウトソーシングを検討するという企業でも、安心して第一歩を踏み出せるサービスです。
情シス アウトソーシングなら|短期で課題解決 – 情シスSAMURAI|クロス・ヘッド株式会社
“丸投げ”では成り立たない。情シスは自社にも一定の機能を
アウトソーシングは、情シス業務の一部を効率化する有効な手段です。しかし、外部に任せるだけでIT運用全体がうまく回るわけではありません。委託先のマネジメントや、社内事情を踏まえた判断・調整は、やはり社内にいなければできないからです。
外注を活かすにも、「内側にいる人」が必要です。ここでは、なぜ自社に情シス機能を一定程度持つことが前提になりつつあるのかを掘り下げていきます。
社内の複雑な事情を把握して判断できるのは、社内の人間だけ
どれだけ高品質な外注先でも、会社の業務フローや現場の細かい制約、部署間の力関係までは把握できません。「何が最適か」は技術的な話だけではなく、組織全体の力学を見たうえで判断されるべきです。
現場の社員は「なぜその対応が必要か」をいちいち言語化してはくれません。ちょっとした空気感や文脈の読み取りが必要で、そこを理解しないまま提案や改善策を出しても、現場に刺さらない。だからこそ、内側にいて、日々のやりとりや温度感を肌で感じている人間が必要です。
委託先を動かすにも、社内で“手綱を握る人”がいるかどうか
「外注する=手放す」ではありません。現場で発生する問い合わせ、障害、改善要望などに対して、**「これはどこまで任せてよいのか」「何を優先すべきか」**といった判断が日々求められます。これを誰も担っていない状態では、委託先も動きようがありません。
また、SLAやKPIをもとにした定例報告があっても、それを読み取って次の打ち手に変換する人材が社内にいなければ、単なる“報告会”で終わります。外注のパフォーマンスを引き出すには、内部に一定のIT知見を持つ人が不可欠です。
ハイブリッド体制なら取り入れやすい
セキュリティ監視やサーバー保守など、技術的に高度で、かつ定型的な業務は外部に委ねる。それ以外の判断や方針策定、業務調整は社内で行う。そうした分担を前提とした“ハイブリッド型”の体制が、現実的かつ持続可能なスタイルになっています。
外注先はパートナーであって、指揮官ではありません。全体像を理解し、判断軸を持っている人間が社内にいることで、ITの方向性がぶれずに済むのです。
情シス業務のアウトソーシングなら社内SE転職ナビ

情シス業務のアウトソーシングが進む中でも、企業がすべてを外部に任せきれるわけではありません。社内IT環境を理解し、外部ベンダーと社内の現場をつなぐ存在は、今も求められ続けています。
そんな背景から、情シス経験者や社内ITに強い人材へのニーズは高まっています。特に、運用・保守だけでなく、社内の課題に寄り添いながら改善を提案できるような“自社常駐型”のポジションは、企業にとって欠かせない役割です。
社内SE転職ナビでは、取引企業3,300社以上・公開求人数7,000件以上(2025年6月時点)という実績をもとに、情シス・社内SEに特化した求人を豊富に取り扱っています。企業との距離が近く、腰を据えて働けるポジションに出会いたい方は、ぜひ一度チェックしてみてください。
まとめ
本記事では、現代の企業が抱えるIT人材不足を解決する一手として、情シス業務のアウトソーシングについて解説しました。メリット・デメリットや委託に適した業務内容、信頼できるおすすめのサービスまで掘り下げてきました。
アウトソーシングは、企業経営に多くのメリットをもたらす一方で、ノウハウの希薄化や情報漏洩のリスクなどのデメリットも忘れてはいけません。
全ての業務を丸投げするのではなく社内にもITを理解する担当者を置き、アウトソーシングを併用することをおすすめします。
目の前の課題解決だけでなく、長期的なIT戦略を構築したうえで適切な体制を構築しましょう。本記事で紹介した内容を参考に、上手くアウトソーシングを活用してください。