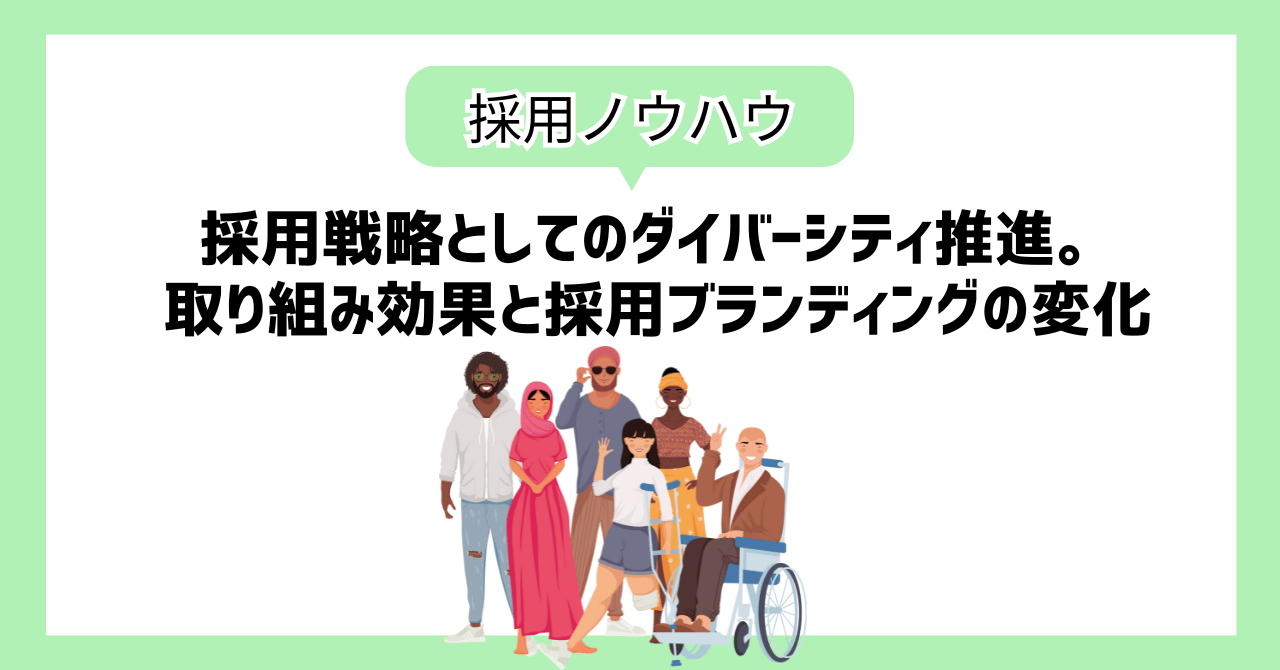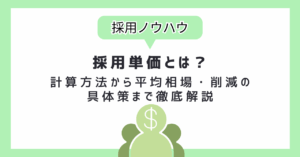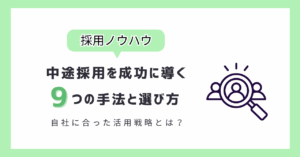近年、企業の成長戦略として注目されているのが「ダイバーシティ(多様性)推進」です。特にエンジニア採用においては、多様なバックグラウンドを持つ人材を積極的に受け入れる姿勢が、採用の質と量の両面で成果を上げ始めています。
本記事では、エンジニア採用におけるダイバーシティ推進の背景、具体的な効果、推進方法、そして先進企業の事例までを解説します。

エンジニア採用、こんな課題ありませんか?
- 技術力だけでなく、事業理解も必要だけど、見極めが難しい
- 社内システムを支える柔軟な対応力を持つ人材がなかなかいない
- 企業文化にフィットするエンジニアを採用したい
「社内SE転職ナビ」なら、技術×カルチャーの両面からマッチするエンジニアをご紹介できます。エージェントによる丁寧なヒアリングに加え、企業から直接アプローチできるダイレクトリクルーティング機能もご利用可能。貴社の採用スタイルに合わせて、最適な候補者との出会いをサポートします。
エンジニア採用でダイバーシティが推進されている理由
エンジニア採用の現場では今、ダイバーシティ(多様性)への取り組みがより戦略的に重視されるようになっています。背景にあるのは、グローバル化やテクノロジーの急速な進化だけではありません。高度なITスキルを持つ人材の獲得競争が激化していること、イノベーション創出や海外展開に柔軟な組織体制が求められていることが、ダイバーシティ推進の必要性を高めています。
性別、国籍、年齢、価値観といった多様なバックグラウンドを持つ人材を受け入れることは、単なる理念の話ではなく、現実的な採用課題への対応であり、将来の企業成長にも直結する取り組みです。ここでは、ダイバーシティが注目される具体的な理由を見ていきます。
優秀な人材の確保につながるから
IT人材そのものは年々増加している一方で、企業が本当に求める「高度IT人材」は慢性的に不足しています。経済産業省のIT人材需要に関する調査によれば、2030年には最大で約79万人のIT人材が不足する可能性があるとされており、特にAI、IoT、クラウドなどの分野では質の高い人材の確保が難航しています
このような中、従来の採用基準にとらわれず、性別や国籍、ライフスタイルの多様性を尊重することで、採用可能な人材の母集団を拡大し、希少なスキルを持つ人材との出会いの機会を増やすことができます。
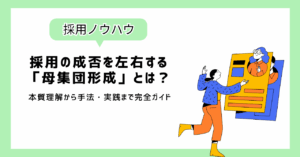
実際に、楽天グループでは社内公用語として英語を導入し、現在では100以上の国・地域から多様なバックグラウンドを持つ人材が在籍しています。外国籍エンジニアの比率が高い部門では、英語でのコードレビューや開発体制が標準となり、国籍を問わずスキル重視の採用が実現しています
また、メルカリでは「Inclusion & Diversity」ポリシーを掲げ、50ヵ国以上の人材が在籍。LGBTQ+への配慮や、リモートワーク、時短制度といった柔軟な勤務環境を整備し、多様なライフスタイルを持つエンジニアの活躍を後押ししています。
このように、ダイバーシティ推進は単なる「採用枠の拡大」にとどまらず、希少価値の高い人材が力を発揮できる環境づくりとして、採用力と開発力の両面に好影響をもたらしています。

グローバル市場への対応力が向上するから
海外展開を視野に入れる企業が増える中、エンジニア採用においても多様な文化や言語背景を持つ人材を受け入れることの重要性が高まっています。グローバル市場で通用するプロダクトを設計・開発するためには、現地の商習慣やユーザー感覚に対する理解が欠かせません。そのため、社内に多国籍なメンバーが在籍していることは、設計・UI・表現などの初期段階で“文化的なズレ”を検知し、開発効率と品質の両面を高める要因になります。
たとえば、英語を共通語とすることで、設計ドキュメントの国際標準化が進み、海外拠点や外部パートナーとの連携もスムーズになります。また、異なる視点を持つメンバーが加わることで、「なぜこの仕様にするのか」「どの市場を優先するか」といった議論が構造化されやすくなり、チーム内の意思決定プロセスや顧客視点の解像度も高まります。
実際に経済産業省の「高度外国人材研究会報告書(2024年)」では、
海外からの投資や人材を受け入れることは、新たなアイデアやノウハウの導入を通じたイノベーションの発揚に加え、時代の変化に即応した新たな経営モデルの確立、働き方改革や労働市場改革を含めた旧来型の日本の経済構造の改革などにつながる効果が期待できる。
出典:高度外国人材研究会報告書
と明記されており、高度外国人材の活躍がイノベーションの創出や経済成長につながることが政策的にも期待されていることが示されています。
このように、多様なバックグラウンドを持つエンジニアを受け入れることは、グローバル化に伴う戦略的な体制強化と位置づけることができます。単なる人員補充ではなく、海外展開を前提とした設計力や顧客理解、組織の柔軟性を高めるために、多様な人材の受け入れはますます重要になっています。
企業ブランドが向上するから
ダイバーシティに取り組む企業は、求職者から「働きやすそうな会社」という印象を持たれやすくなります。とくにエンジニア職では、業務の成果が重視される一方で、「自分の価値観や働き方を尊重してくれる環境かどうか」を重視する人も少なくありません。
また、ダイバーシティに関する取り組みが「心理的安全性」や「発言しやすさ」につながると認識されていることも、エンジニアのような知識集約型職種では大きな意味を持ちます。このため、「性別や国籍に関係なく自分らしく働ける環境かどうか」は、少なくとも一定のエンジニアにとって応募や入社後の定着に影響する要素のひとつになっていると考えられます。
さらに、こうした姿勢は社外だけでなく社内のエンゲージメントにも良い影響を与えます。誰もが公平に扱われる環境が整っていると、社員の帰属意識や紹介意欲が高まり、結果として採用ブランディングが自然と強化されていくのです。
-24-300x157.jpg)
ダイバーシティ推進によるエンジニア採用への効果
エンジニア採用においてダイバーシティを意識した取り組みを行うことは、採用広報や母集団形成、さらには定着の面でもさまざまな効果をもたらします。ここでは、実際に企業の採用活動や組織運営で得られている代表的な効果を紹介します。
採用ブランディングの向上
ダイバーシティを打ち出すことで、企業としてのスタンスや働き方の柔軟性が可視化され、候補者に安心感や共感を与えやすくなります。採用サイトで多様な働き方の事例や社員インタビューを掲載したり、採用イベントで外国籍社員の登壇機会を設けたりすることで、「自分に合った職場かもしれない」と思ってもらえる導線を増やすことができます。
また、同じ業界・ポジションの求人が並ぶ中で、「誰もが働きやすい環境づくりに本気で取り組んでいる会社」という印象は、他社との差別化ポイントとして機能しやすく、特にミドル〜シニア層や転職経験者から高く評価される傾向もあります。
若手・女性・外国籍人材の応募増加
これまで自分には関係がないと感じていた人材層が、「この会社なら自分の背景や価値観も尊重してくれそう」と感じられるだけで、応募のハードルは大きく下がります。
たとえば、育児中の女性エンジニアが実際にフルリモートで活躍している、外国籍エンジニアがプロジェクトマネージャーとして評価されているなど、具体的な事例や顔が見える形で発信されている企業には、属性にとらわれず幅広い人材からの応募が集まりやすくなります。
その結果、年齢・性別・国籍に偏らないバランスの良い採用が実現し、特定の属性に依存しない安定した採用体制を築くことができます。
定着率の改善
多様な価値観や働き方を認める職場では、社員一人ひとりが「自分らしく働けている」と感じやすくなります。こうした環境では、発言しやすさや協働のしやすさが高まり、心理的安全性が保たれやすくなるため、孤立や離職のリスクが軽減されます。
また、マネジメント層も多様な働き方やキャリア観を理解し、個々の状況に応じたサポートができるようになることで、「この会社なら長く働ける」と感じる社員が増える傾向にあります。ダイバーシティ推進は採用の入り口だけでなく、組織の安定化や生産性の向上にも寄与する中長期的な施策として定着しています。
エンジニア採用でダイバーシティを推進する方法
ダイバーシティ推進は理想論ではなく、現場で機能する仕組みとして定着させることが重要です。表面的なスローガンに終わらせず、経営の意思決定・制度設計・社内外への伝え方まで含めて丁寧に取り組むことが、エンジニア採用の現場でも効果を発揮します。
①経営戦略としての明確な位置づけ
ダイバーシティは採用部門や人事だけで完結する話ではありません。たとえば「ジェンダー比率の目標設定」や「外国籍人材の登用方針」といった具体的な方針を経営方針や中期経営計画に組み込むことで、現場も優先度を正しく認識できるようになります。
エンジニア部門にとっても、「これは全社的な取り組みである」と理解されることで、協力姿勢が生まれやすくなり、制度導入や評価制度の見直しにも現実的な推進力が働きます。
②制度・体制・文化の整備
ダイバーシティは「受け入れる意思」だけでなく、具体的に働きやすい仕組みがあるかどうかが問われます。たとえば以下のような制度設計が実際に効果を上げています。
- フルリモート/一部リモートなど柔軟な勤務制度
- 時短勤務、フレックス、副業可など多様な働き方の選択肢
- 宗教・文化的配慮に基づいた休暇制度や就業ルール
- 社内の問い合わせ対応に英語を併記したヘルプデスク
これらは単なる「福利厚生」ではなく、組織として多様な人材を迎え入れる準備ができているかを示すメッセージにもなります。
③社内外への情報発信
社内での取り組みを外に向けて伝えることで、「実態としてどう取り組んでいるか」を候補者に判断してもらいやすくなります。採用サイトに制度の紹介だけでなく、実際にその制度を活用している社員の声や働き方の例を掲載すると、よりリアルに伝わります。
また、取り組みを継続的に発信しているかどうかも信頼性を左右します。制度導入時のリリースで終わらせず、半年後・1年後の活用状況や改善プロセスを共有していくことが、「形だけではない」ことの証明になります。
ダイバーシティ推進を発信する際のポイント
ダイバーシティへの取り組みは、どれだけ社内で進んでいても「社外から見えなければ評価されない」側面があります。とくに採用活動においては、候補者が安心して応募できるかどうかが、発信の内容と質に大きく左右されます。以下のような点を意識することで、伝わる情報発信につながります。
社員インタビューを活用する
社内制度や方針だけでは、実際の働き方や雰囲気までは伝わりません。そこで効果的なのが、実際に働いている社員の声を紹介するコンテンツです。
性別・年齢・国籍・ライフステージの異なるメンバーが「どのように働いているか」「どんな不安があり、どう乗り越えたか」を語ることで、候補者が自分を重ねやすくなり、エントリーの後押しになります。特にエンジニアは「現場の声」を重視する傾向が強いため、形式ばらないリアルな語り口が効果的です。
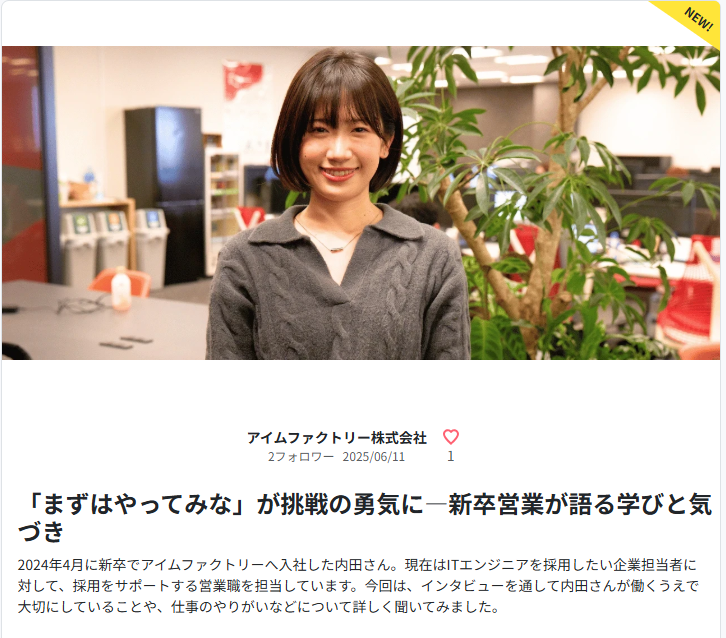
エンジニア目線での「働きやすさ」を可視化する
「開発者として快適に働ける環境かどうか」は、エンジニアが応募を決める大きな判断材料です。以下のようなポイントを具体的に伝えることで、他社との差別化や安心感の提供につながります。
- 選べる技術スタックやフレームワーク
- コードレビューやペアプロの文化
- リモート勤務/フレックスタイムなど勤務の柔軟性
- 副業可、育児・介護中の稼働配慮の実例
単なる「制度一覧」ではなく、どう使われているか・どのように機能しているかまで言及することで、働きやすさのリアリティが増します。
DEI(多様性・公平性・包摂性)を継続的に発信する
一度だけの制度導入やメッセージ発信では、候補者に「アピール目的では?」と受け取られるリスクがあります。信頼を得るためには、継続的にアップデートを共有し、“今も取り組みを進めている”という姿勢を伝えることが大切です。
たとえば、
- 半期ごとのD&Iレポート発行
- 社内の当事者インタビューの定期掲載
- 経営層からのメッセージや実施施策の進捗公開
など、“取り組みの現在地”を示す情報があることで、候補者からの信頼度が高まり、他社との比較においても優位性が生まれます。
ダイバーシティ推進の企業事例
実際にダイバーシティを採用戦略に組み込んでいる企業では、制度整備だけでなく、社員の声や文化づくりを通じて組織全体を変えていく取り組みが進んでいます。ここでは、国内の代表的な事例を3社紹介します。
日産自動車株式会社
日産自動車では、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DEI)を経営の重要テーマと位置づけ、性別、国籍、年齢、性的指向、障がいの有無などにかかわらず、多様な社員が活躍できる職場づくりを進めています。CEOが議長を務める「グローバルDEIカウンシル」を設置し、地域ごとのDEIカウンシルとも連携しながら、戦略の立案から実行までを組織的に推進しています。
特に女性活躍の分野では、キャリアアドバイザー制度、層別研修、メンタリングなどを通じて、着実に女性管理職比率を向上させており、国内では2004年の1.6%から2022年には10.3%、グローバルでは同期間で6.7%から14.9%に上昇しています。
LGBTQ+に関しても、全社員対象のeラーニングやセミナーを継続的に実施し、同性婚・事実婚に対する福利厚生制度の改定も行っています。これらの取り組みが評価され、LGBTに関する社外評価「PRIDE指標」では5年連続で最高位のゴールドを獲得しています。
また、柔軟な働き方の推進にも力を入れており、フレックス勤務、リモートワーク、育児・介護支援制度の充実に加え、復職支援プログラムや両立支援セミナーの実施を通じて、多様なライフステージに対応した就労環境を整備しています。
日産は、制度や方針だけでなく、それを現場で実践する仕組みと文化づくりに力を入れており、組織全体で多様性を受け入れ、活かす体制を築いています。
参考:ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン | サステナビリティ | 日産自動車企業情報サイト
ヤマトホールディングス株式会社
ヤマトホールディングスでは、性別や国籍、年齢、障がいの有無、性的指向などにかかわらず、すべての社員がいきいきと働ける環境づくりを進めています。とくに外国籍社員に対しては、約8,000人が在籍している現状をふまえ、作業マニュアルや雇用契約書の多言語化、英語・ネパール語・ベトナム語での相談窓口設置、社員意識調査の多言語対応など、実務面での支援を強化しています。
また、LGBTQ+の理解促進にも取り組んでおり、社外の専門相談窓口と連携し、当事者が安心して相談できる体制を整備。こうした多様な背景を持つ社員の存在を前提とした職場づくりを進めています。
さらに、女性活躍の面では、営業所長を目指す女性社員への育成プログラムを提供し、異業種研修への参加機会も拡充。実際の登用実績も着実に増加しています。障がい者雇用にも注力しており、2024年3月時点での雇用者数は2,873名、雇用率は3.14%と、法定水準を大きく上回っています。地域単位での採用や定着支援も行われており、制度面だけでなく運用面でもきめ細かな配慮がなされています。
このようにヤマトホールディングスは、国籍や属性にとらわれず、「誰もが働きやすい職場」を実現するための施策を、制度・文化・実務の三面から具体的に展開しています。
参考:人権・ダイバーシティ | ヤマトホールディングス株式会社
ITエンジニアの採用なら社内SE転職ナビ!

開発もインフラも、今求められているのは「自社の業務を理解し、内製で支えられるエンジニア」。私たち『社内SE転職ナビ』は、そうした“企業内エンジニア”を目指す人材と、必要としている企業様をつなげる支援を行っています。
「情シスだけでなく、開発寄りの人材が欲しい」「社内ITの運用保守を任せられるインフラ人材が足りない」そんなお悩みにも、実務に即したマッチングでお応えします。
掲載型では出会えない、エージェントだからこそ届く人材に。ご相談は1ポジションから、貴社の課題にあわせてご提案します。
まとめ
ダイバーシティは、これからの採用競争における「前提条件」です。とくにスキル重視が進むエンジニア採用では、性別・国籍・ライフスタイルにとらわれず、多様な人材を迎え入れる姿勢そのものが企業の魅力を左右します。
ダイバーシティの推進は、単なる理念ではなく、採用ブランディングや職場環境の競争力を高める実践的な取り組みです。制度の整備や発信の工夫を通じて、“選ばれる企業”への進化がはじまります。