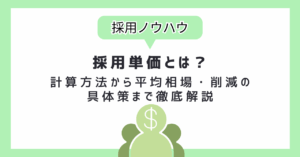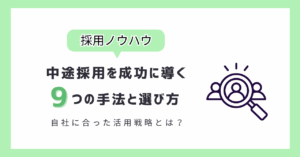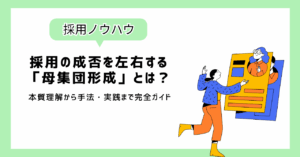近年の労働市場の変化に伴い、多くの企業が新人育成や従業員の定着率向上に力を入れています。なかでも、オンボーディングへの注目が高まっています。ただし、「オンボーディングとは具体的に何なのか?」と疑問に思う方も少なくありません。
この記事では、オンボーディングの基本的な定義から、目的、導入ステップ、成功のポイントまでを解説します。記事の内容を参考にして、オンボーディングの全体像を理解し、自社の人事戦略に取り入れてください。

エンジニア採用、こんな課題ありませんか?
- 技術力だけでなく、事業理解も必要だけど、見極めが難しい
- 社内システムを支える柔軟な対応力を持つ人材がなかなかいない
- 企業文化にフィットするエンジニアを採用したい
「社内SE転職ナビ」なら、技術×カルチャーの両面からマッチするエンジニアをご紹介できます。エージェントによる丁寧なヒアリングに加え、企業から直接アプローチできるダイレクトリクルーティング機能もご利用可能。貴社の採用スタイルに合わせて、最適な候補者との出会いをサポートします。
オンボーディングとは何か?定義と注目される背景
オンボーディングとは、新しく加わった従業員が、早期に職場環境や業務に慣れて能力を発揮し、組織に定着できるよう支援する一連の取り組みや制度です。言葉の語源は「船や飛行機に乗っている」という意味の「on-board」に由来し、企業という乗り物の一員としてスムーズに航海(業務)を始められるようにサポートするイメージを表しています。
オンボーディングが注目される背景にあるのが、働き方の多様化や人材の流動化です。現代社会では、終身雇用制度が過去のものとなり転職が一般化しています。このような環境の中で企業は、採用した人材にいかに早く組織に馴染んでもらい、戦力として定着してもらうかという課題を抱えているのです。
入社直後は新しい環境への不安や業務上の困難から、従業員のエンゲージメントが低下しやすく、早期離職につながるケースも少なくありません。オンボーディングは、入社初期のギャップや従業員が抱える不安を解消するうえで、非常に重要な役割を担います。
単なる業務研修だけでなく、企業文化の共有や人間関係の構築支援、期待する役割の明確化などを実施します。質の高いオンボーディングプログラムが構築できれば、従業員は早期に組織に溶け込み、自らの能力を最大限に発揮できるでしょう。さらに、企業の生産性向上や成長に大きく貢献します。多くの企業でオンボーディングの導入が進んでいるのは、こうした戦略的な価値が認識されているからです。
オンボーディングはOJTやOff-JTと何が違う?
オンボーディングと混同されがちな手法に、OJT(On-the-Job Training)やOff-JT(Off-the-Job Training)があります。いずれも従業員を対象とした取り組みですが、目的と範囲が違います。
OJTは、実際の業務を通じて、先輩社員や上司が仕事の進め方やスキルを指導する手法です。実践的なスキル習得に優れているものの、指導担当者のスキルや経験に依存しやすく、体系的な知識の習得には限界がある場合もあります。
Off-JTは、主に職場を離れて行われる研修やセミナーを指します。ビジネスマナーや業界知識、専門スキルなどを体系的に学ぶ場であり、均質な知識を得られる点がメリットです。
オンボーディングは、OJTやOff-JTを包含する、より包括的なサポートプログラムです。最大の特徴は、業務スキルの習得だけでなく以下の内容も長期間(一般的には3ヶ月〜1年程度)でサポートする点にあります。
- 企業文化や価値観への適応
- 社内での人間関係構築
- キャリアプランの共有
OJTやOff-JTが「業務遂行能力の向上」をメインとするのに対し、オンボーディングは「組織への適応と定着、そして活躍」という、広いゴールを目指す取り組みなのです。
オンボーディングの主な目的と企業が導入すべき理由
オンボーディングは、単なる新人研修にとどまらず、企業の持続的な成長に不可欠な戦略的な取り組みです。目的が明確になれば、自然と自社でも導入すべきだと考えるようになるでしょう。ここではオンボーディングの主な目的と、企業が導入すべき理由について、以下の3つの視点で解説します。
- 即戦力化を早めるため
- 早期離職を防ぐため
- エンゲージメントを高めるため
説明する内容を参考に必要性を理解して、自社の取り組みにご活用ください。
即戦力化を早めるため
オンボーディングを導入する大きな目的のひとつは、従業員の即戦力化を加速させることです。新しい環境では、どれだけ優れたスキルや経験を持つ人材でも、企業独自のルールや業務の進め方、使用ツールに慣れるまでには時間がかかります。
オンボーディングを通じて、入社後の早い段階で必要な知識やスキルを体系的に提供し、業務プロセスへの理解を促すことができれば、従業員が独り立ちできるまでの期間を短縮できるでしょう。
誰に何を聞けばよいのかが明確になる関係性も構築できるため、不明点をすぐに解消し、業務の停滞を防ぐことにもつながります。従業員自身の成長を促すだけでなく、担当する先輩社員や上司の教育工数を削減し、全体の生産性向上にも役立ちます。

早期離職を防ぐため
早期離職の防止にもオンボーディングは効果的です。入社直後に以下のような考えを抱いてしまうと、従業員は今後も働き続けるべきか疑問をもってしまうでしょう。
- 思い描いていた業務内容とのギャップ
- 職場での人間関係に対する不安
- 組織内での孤立感
オンボーディングを活用すれば、このような不安や孤立感を解消できます。定期的な1on1ミーティングやメンター制度を通じて、従業員が気軽に相談できる環境を提供し、精神的なサポートを行いましょう。
企業のビジョンや文化、期待する役割を丁寧に伝えれば、入社後のミスマッチを防ぎ、「この会社で働き続けたい」という納得感につながります。結果として、従業員の定着率が向上し、採用活動にかかったコストが無駄になることを防ぎます。
エンゲージメントを高めるため
オンボーディングは、従業員のエンゲージメント、すなわち「企業への愛着や貢献意欲」を高めるうえで効果的です。プログラムを通じて、企業の理念やビジョン、大切にしている価値観を共有することで、従業員は自身が組織の一員であるという自覚と誇りを持ちやすくなります。
歓迎の意を示すウェルカムイベントや他部署のメンバーとの交流機会を設ければ、組織全体で受け入れられているという安心感も生まれるでしょう。このようにして築かれたエンゲージメントは、単に業務をこなすだけでなく、より主体的に仕事に関わり、組織へ貢献しようという意欲につながります。高いエンゲージメントは、短期的なパフォーマンス向上だけでなく、中長期的な人材定着と企業の持続的な成長に不可欠です。
オンボーディング導入の3ステップ
オンボーディングを自社で採用しようとしても、具体的な手順がわからなければ導入は困難です。適切な手順で運用しなければ、狙った成果につながらない可能性もあります。オンボーディングを自社に導入する場合は、以下の3ステップで進めると良いでしょう。
- 目標設定とスケジュール作成
- 担当者と関係部門への共有・準備
- 実行と振り返りの仕組みを作る
各ステップでの取り組み方法について、詳しく見ていきます。
1. 目標設定とスケジュール作成
オンボーディング導入の最初のステップは、明確なゴール設定です。「新しく入った従業員に、入社後どのような状態になってほしいか」を具体的に定義します。
たとえば、「入社1ヶ月後には、主要ツールを一人で操作でき、簡単なタスクを自走できる」「3ヶ月後には、チームの一員として主体的に意見を発信できる」といった内容です。
次に、目標を達成するための期間(例:3ヶ月間)と、具体的なアクションプランを時系列で設計します。入社前、入社初日、1週目、1ヶ月目といった節目ごとに、「何を」「誰が」「どのように」教えるのかを詳細なスケジュールに落とし込み、ロードマップを作成することが成功の鍵です。
2. 担当者と関係部門への共有・準備
目標設定とスケジュール作成を終えたら、必ず現場の上司やメンター、IT部門、総務部門などの関係者全員に事前に共有し、協力を仰ぎましょう。オンボーディングは人事部だけで完結するものではなく、配属先の部署や関連部門を巻き込んだ全社的な取り組みです。目的を共有すれば、受け入れ側の当事者意識が高まり、より質の高いサポートが期待できます。
また、物理的な準備も不可欠です。入社日までにPCや業務用アカウントの準備、名刺の手配、座席の確保などを完了させておけば、新しい従業員は初日からスムーズに業務を開始できます。こうした細やかな準備は、「歓迎されている」というメッセージとして伝わり、従業員の安心感につながるでしょう。
3. 実行と振り返りの仕組みを作る
担当者と関係部門への共有・準備を終え、計画を実行に移した後は、効果の測定と改善が不可欠です。オンボーディング期間中は、計画通りに進んでいるかを確認するために、従業員と定期的なコミュニケーションの場を設けましょう。
週に一度の1on1ミーティングなどの機会を活用して進捗状況を確認し、困っていることや不安な点をヒアリングします。計画と実態に乖離があれば、柔軟なスケジュールやサポート内容の調整が求められます。
オンボーディングプログラムが完了した後には、本人や受け入れ部署の担当者からフィードバックを収集し、プログラム自体の評価と見直しを行ってください。振り返りのサイクルにより、オンボーディングの質が継続的に向上し、組織全体の育成力強化につながります。

オンボーディングを成功させる5つのポイント
オンボーディングは新メンバーをスムーズに戦力として迎え入れる方法です。手順や仕組みといったルールだけでは人の心は動かせません。オンボーディングを成功させるには、以下の5つのポイントを押さえておきましょう。
- 人事が事前にコミュニケーションを取る
- 周囲の巻き込みとサポート体制の整備
- 1on1や小さな目標で定着を支援
- 評価・フィードバックを仕組みにする
- リモート環境でも柔軟に対応する
各ポイントについて説明します。
人事が事前にコミュニケーションを取る
オンボーディングのスタートは入社日ではなく、内定承諾後であると認識しましょう。入社を控えた内定者は、「新しい環境に馴染めるだろうか」「どんな人たちがいるのだろう」といった不安を抱えているものです。この不安を軽減するために、人事担当の積極的なコミュニケーションが不可欠です。
- 具体的なコミュニケーション例は以下のとおりです。
- 入社数週間前にウェルカムメールを送る
- 入社初日の流れや準備物、チームメンバーからの歓迎メッセージなどを伝える
- オンラインでの個別面談を実施する
- 期待する役割を伝えたり、疑問や懸念点を解消したりする
こうした積極的なコミュニケーションによって、「あなたを待っている」というメッセージが伝わり、スムーズなスタートを後押しするのです。
周囲の巻き込みとサポート体制の整備
新しく迎えた従業員の育成は、直属の上司や人事部だけの仕事ではありません。部署のメンバーはもちろん、他部署の同僚や先輩、メンターなど、組織全体でサポートする体制を築くことが不可欠です。多様なメンバーと関われば、企業文化や社内の暗黙知を多角的に理解し、社内ネットワークを早期に構築できるからです。
具体的な仕組みとしては、業務の相談役であるOJTトレーナーとは別に、精神的なサポートや会社生活の相談役となるメンター制度の導入が有効です。また、気軽に質問できるよう、チーム内に専用のチャットグループ(例: Slackのチャンネル)を作成し、部署のメンバー全員でフォローする体制を作るのも良いでしょう。
1on1や小さな目標で定着を支援
入社直後の従業員に、いきなり大きな成果や完璧なパフォーマンスを求めるのは現実的ではありません。高い目標はプレッシャーとなり、かえって成長を阻害してしまいます。そこで重要になるのが、スモールステップでの目標設定です。
たとえば、最初の1週間は「社内ツールのアカウント設定を完了し、操作に慣れる」、最初の1ヶ月は「簡単な実装タスクに挑戦し、レビューを依頼する」など、達成可能な小さな目標を段階的に設定しましょう。週に1回程度の1on1ミーティングで、目標の達成度を確認し、できたことを具体的に褒め、次の目標を設定する、というサイクルを回します。この小さな成功体験の積み重ねが、新入社員の自信とモチベーションを高め、着実な成長と定着につながります。
評価・フィードバックを仕組みにする
入社したばかりの従業員は、「自分の仕事ぶりは期待に応えられているか」「何をどう改善すれば良いのか」といった点について不安を感じています。不安を解消し、成長を促すためには、評価とフィードバックの機会を仕組みとして提供することが重要です。
具体的には、オンボーディング期間専用の評価シートを作成し、「企業文化への理解度」「チーム内でのコミュニケーション」「担当業務の進捗」など、見るべきポイントを明確にします。1ヶ月ごとや3ヶ月後といった節目にレビュー面談を実施し、評価シートを基にフィードバックを行います。
良かった点と今後の期待・改善点を具体的に伝えれば、自身の現在地を客観的に把握できるため、次のアクションにつながります。
リモート環境でも柔軟に対応する
リモートワークが普及した現代において、オンボーディングも環境に合わせた工夫が不可欠です。オフィス勤務と比べて、リモート環境では偶発的なコミュニケーションが生まれにくく、従業員が孤立感や疎外感を抱きやすいという課題があるからです。
意図的にコミュニケーションの機会を設計して、課題を解決しましょう。例えば、業務連絡はチャットツール(Slackなど)で行い、表情が見えるビデオ会議(Zoom、Google Meetなど)での週次進捗共有ミーティングを定例化するのがおすすめです。
業務以外の接点を作ることも重要で、バーチャル空間での雑談タイムを設けたり、オンラインランチ会を企画したりすれば、チームの連帯感につながります。

オンボーディングの成功事例
実際にオンボーディングを導入して、成功している企業ではどのような取り組みを行っているのでしょうか。実際に成功している事例を参考にすれば、自社での導入イメージも拡がるでしょう。ここではオンボーディングの成功事例として、以下の4社の取り組みを紹介します。
- サイボウズ
- LINEヤフー株式会社
- 株式会社アカツキ
- 株式会社ディー・エヌ・エー
順番に見ていきましょう。
サイボウズ
「チームワークあふれる社会を創る」を理念に掲げるサイボウズでは、新卒とキャリア入社者それぞれに最適化されたオンボーディングを実施しています。必要な情報はkintoneアプリに集約し、誰がどのようなプロセスを進めているかが可視化されているため、入社者は迷うことなくプログラムに取り組めるでしょう。
期待する役割を明確にする個別の「チームオンボーディングプラン」や、飲食費を補助する「ウェルカムチーム制度」で理念の理解と関係構築の両面から、従業員がスムーズにチームの一員となれるようサポートしています。
参考:オンボーディングと学習制度 | 採用情報 | サイボウズ株式会社
LINEヤフー株式会社
LINEヤフー株式会社では、新入社員が早期にパフォーマンスを発揮できるよう、入社者と受け入れ部門の双方をサポートするオンボーディングが特徴です。入社者にはオリエンテーションやeラーニング、フォローアップアンケートを提供し、効率的な知識習得と定着を促します。
同時に、受け入れ部門側にもOJT担当者向けのトレーニングやメンター向けの手引きを配布し、組織全体で質の高いサポート体制を構築しています。また、先輩社員との交流を促す「シャッフルランチ施策」のように、業務外での自発的な関係構築のきっかけ作りにも力を入れており、組織への早期適応を後押ししているのです。
株式会社アカツキ
株式会社アカツキでは、人材育成の現場で使われている「ロミンガーの法則」に基づきオンボーディングのプロセスを重視しています。この法則では、「現場の経験」が70%、「人から受けるアドバイスや影響」が20%、「研修」が10%の割合で人の成長に影響を与えるとされています。そのため、実地で学べるプロセスが組み立てられました。
全体で50人以上の大規模チームでは、各セクションの夕会に新メンバーを混ぜ、相互の自己紹介を行う手法を取り入れ、関係性の構築につなげている例もあります。
参考:アカツキゲームスの産学連携で見えてきた“即戦力”の育て方。ゲームプランナーとして活躍するための3つの要素|Akatsuki VOICE(アカツキ ボイス)
株式会社ディー・エヌ・エー
DeNAでは、多彩な経歴を持つ入社者向けに「DOP(DeNA Onboarding Program)」と呼ばれる手厚いプログラムを提供しています。そのコンセプトは、いつでも帰って来られる「ホームベース」のような、部署を超えた横のつながりを作ることです。
特徴的なのは、プログラムを定型化せず、参加者アンケートを頻繁に行い、常に内容を改善し続けている点です。オフラインでゲームをするなど、コミュニケーションをデザインしたユニークなワークショップを通じて、リモートワーク環境でも孤立しない、強固なコミュニティ形成を促し、入社者が早期に活躍できる土台を築いています。
引用元:DeNAの中途入社者がフルスイングするための“ホームベース”に。「オンボーディング」プログラム始動中 | フルスイング by DeNA
社内SEの求人なら社内SE転職ナビ

オンボーディングの成功には、スムーズにプロジェクトを進められる即戦力のエンジニアの存在が欠かせません。エンジニアファクトリーは、フリーランスエンジニアとのマッチングを通じて、貴社のチームを強力にサポートします。
当社は、業界最高水準の 継続率95.6% を実現しており、長期的なプロジェクト参画を希望するエンジニアが多数登録しています。また、 公開案件数8,000件以上 を誇る豊富なネットワークにより、貴社の求めるスキルと志向性を持つ人材を迅速にご提案可能です。
オンボーディングを円滑に進め、プロジェクトの成功を加速させるために、ぜひフリーランスエンジニアの活用をご検討ください。初回相談は無料。まずはお気軽にお問い合わせください。
まとめ
本記事では、オンボーディングの定義から目的、具体的な導入ステップ、そして成功のためのポイントまでを詳しく解説しました。
オンボーディングは、単に業務を教えるだけの新人研修ではありません。新入社員が組織文化に馴染み、人間関係を築き、安心して能力を発揮できる環境を企業全体で計画的に提供する包括的なサポートプログラムです。効果的なオンボーディングは、新入社員の即戦力化を促し、入社後のギャップによる早期離職を防ぎます。
働き方の多様化が進む現代において、人材の獲得と定着は企業の競争力を左右する重要な経営課題です。本記事で紹介した内容を参考に、ぜひ自社に最適化されたオンボーディングの仕組みを構築してください。