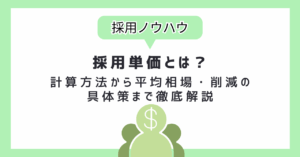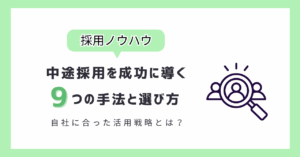「エンジニアの採用が、なぜこんなにも難しいのか」と頭を抱える企業の採用担当者の方も少なくないでしょう。IT技術の急速な発展とDX推進の波に乗り、エンジニアの需要は増す一方です。従来の採用手法では優秀なエンジニアに出会うことすら困難になっています。
この記事を読めば、エンジニア採用が難しい根本的な理由から、採用成功に向けた具体的な準備、明日から実践できる7つの施策まで網羅的に理解できます。エンジニアの採用が難しいと悩んでいる方は最後までご覧ください。

エンジニア採用、こんな課題ありませんか?
- 技術力だけでなく、事業理解も必要だけど、見極めが難しい
- 社内システムを支える柔軟な対応力を持つ人材がなかなかいない
- 企業文化にフィットするエンジニアを採用したい
「社内SE転職ナビ」なら、技術×カルチャーの両面からマッチするエンジニアをご紹介できます。エージェントによる丁寧なヒアリングに加え、企業から直接アプローチできるダイレクトリクルーティング機能もご利用可能。貴社の採用スタイルに合わせて、最適な候補者との出会いをサポートします。
エンジニア採用が難しい3つの理由
エンジニア採用が難しい理由はさまざまで、これさえ解決すれば採用できるという万能薬はありません。
複合的な要因が存在しており、単に「人がいない」というだけでなく、市場の変化や採用プロセスの課題、そして候補者との関係性の変化が絡み合っているのです。ここでは、多くの企業が直面する「なぜ採用が難しいのか」という理由を以下の3つの視点から解説します。
- 即戦力の人材不足と需給ギャップ
- 技術力と“活躍可能性”の見極めが難しい
- 候補者が企業を見る目を持っている
順番に見ていきましょう。
1. 即戦力の人材不足と需給ギャップ
エンジニア採用の難しさの根底には、深刻な人材不足、特に「即戦力となるエンジニア」の需給ギャップがあります。最新の調査では、IT技術関連職の有効求人倍率は3倍を超え、他職種の平均を大きく上回る状況です。これは、ひとりの求職者に対して3社以上が採用を競っていることを意味します。
特に現場が求めるのは、単にコードが書ける人材ではなく、要件定義や設計、技術選定といった上流工程を担える高度なスキルを持つエンジニアです。市場では未経験層や経験の浅い層の求職者が増加傾向にあるものの、即戦力層は極端に不足しているのが現状です。企業は、厳しい競争環境の中で、数少ない優秀な人材をいかにして惹きつけるかという課題に直面しています。

2. 技術力と“活躍可能性”の見極めが難しい
企業が「エンジニア採用が難しい」と感じるふたつ目の要因は、候補者の技術力と入社後の“活躍可能性”を見極める難しさが挙げられます。特に、面接官が人事担当者や非エンジニアである場合、技術的なスキルに対する深掘りができないまま判断してしまいがちです。
「技術試験が、実際の業務内容と乖離している」「自社で活躍するために必要なスキルセットの評価基準が言語化されていない」といった失敗例は後を絶ちません。
重要なのは、「コードが書けること」と「事業に貢献できること」はイコールでないという点です。技術力はもちろん、設計能力や課題解決能力、チームで円滑に業務を進めるためのコミュニケーション能力といった、数値化しにくいスキルも重要です。
これらの非定量的スキルを見極めるのは非常に困難です。しかし、「見極めが難しいから仕方ない」と諦めることなく、評価軸のすり合わせや外部評価の活用などのアクションを通した改善が求められます。

3. 候補者が企業を見る目を持っている
現在のエンジニア採用市場は、圧倒的な売り手市場です。優秀なエンジニアほど多くの企業から声がかかるため、彼らは選ばれる側であると同時に、シビアな目で企業を選ぶ側でもあります。提示される給与額だけで転職を決める時代は終わり、候補者は多角的な視点で企業を評価しています。
候補者が評価している具体例は以下のとおりです。
- どのような技術スタックを導入しているか
- 開発プロセスはアジャイルか、ウォーターフォールか
- リモートワークは可能か、フレックスタイム制度はあるか
- どのようなカルチャーで、どんな人たちと働くのか
これらの情報が求人票や採用サイトで不明瞭だったり、面接官の説明が曖昧だったりすると、候補者からすぐに見切られてしまうでしょう。

採用活動を始める前にやるべき準備
やみくもに求人を出しても、優秀なエンジニアの採用にはつながりません。エンジニア採用は、事前の“採用設計”が成否を分けます。「なぜ採用するのか」「どんな人に来てほしいのか」という土台が曖昧なままでは、候補者の心をつかむことは不可能です。採用活動を始める前に、以下の3つの準備に取り組みましょう。
- 採用の目的と人材像の明確化
- 社内にエンジニアがいない場合の対処法
- 技術環境・制度の棚卸し
それぞれ詳しく解説します。
採用の目的と人材像の明確化
エンジニア採用を成功させるための最初の準備は、採用目的と人材像を徹底的に明確化することです。この二つの軸がブレていると、求人票・スカウトメール・面接での評価基準がバラバラになってしまいます。
特にエンジニアは、業務内容・技術領域・志向性で大きくタイプが分かれるため、「人手不足だから、とにかく1人増員したい」といった曖昧な状態では、採用のミスマッチや早期離職を招いてしまうでしょう。
「新規事業を牽引してくれる、アジャイル開発経験が豊富なサーバーサイドエンジニア」のように、ペルソナレベルまで解像度を高く設定しなければなりません。その結果、社内の関係者間の採用に対する認識が統一され、一貫したメッセージを届けられるのです。
社内にエンジニアがいない場合の対処法
社内に技術的な知見を持つエンジニアがいない場合、スキルレベルの見極めは困難です。しかし、外部の専門知識をうまく活用すれば、この課題は乗り越えられます。
副業エンジニアや技術顧問に、求人票の技術要件のレビューや書類選考、技術面接などで協力を依頼することをおすすめします。また、エンジニア採用に強い人材エージェントに相談し、面接に同席してもらうといった支援を受けるのも良いでしょう。
GitHubのコードや個人ブログ、ポートフォリオサイトなどを活用して、候補者のアウトプットを事前に評価する仕組みも効果的です。技術的な視点をどのように組み込むかをあらかじめ設計しておけば、採用担当者に依存しない安定した選考フローを構築できます。
技術環境・制度の棚卸し
エンジニアが、転職先を選ぶ際に重視する情報に「どのような技術環境で、どういった働き方ができるのか」という点があります。求人票や企業サイトから読み取れなければ、候補者は応募をためらってしまうかもしれません。
自社の現状を正確に把握し、以下の視点で棚卸しを行いましょう。
- 技術スタック:使用言語・FW・ツールなど
- 開発体制:アジャイルかウォーターフォールか
- 開発環境:使用マシン、コミュニケーションツールなど
- 働き方:リモート可否・勤務時間の柔軟性など
上記の情報を具体的に洗い出し、候補者に提示できるように準備しておくことが重要です。また、福利厚生や社内制度も、導入の背景や意図まで説明できれば、候補者との情報格差をなくし、入社後のミスマッチを防ぐ効果が期待できます。
エンジニアに刺さる7つの採用施策
エンジニア採用において、数を打てば当たるという時代は終わりました。大切なのは、小手先のテクニックではなく、企業側の魅力の伝え方と候補者一人ひとりへのリスペクトです。ここでは、エンジニアに刺さる以下の7つの採用施策について解説します。
- 自社サイトの整備
- スカウト文面の見直し
- フリーランスからの転換を提案する
- 面接構成の工夫(技術・カルチャー分担)
- 採用広報の活用(ブログ・SNS)
- エンジニア面接官の“活かし方”で差がつく
- リファラル制度の導入
詳しく見ていきましょう。
自社サイトの整備
企業の採用サイトは、候補者が最初に訪れる会社の顔です。単に募集要項を掲載するだけでなく、エンジニアが働くイメージを持てるようなコンテンツを充実させましょう。
おすすめは、エンジニア向けの技術ブログや社員インタビューです。技術ブログでは、現場で直面した課題をどう乗り越えたか、新しい技術をどう導入したかといったリアルな情報を発信して、企業の技術レベルや開発文化を伝えます。社員インタビューでは、在籍するエンジニアの生の声を通して、チームの雰囲気や働きがいを示しましょう。
これらのコンテンツは一度作って終わりにするのではなく、継続的に更新し、情報の鮮度を保たなければなりません。常に最新の情報を届け、候補者の信頼感を醸成することが理想的です。
-24-300x157.jpg)
スカウト文面の見直し
多くのエンジニアは、日々大量のスカウトメールを受け取っています。大量のメールに埋もれないためには、一目で「自分だけに向けられたメッセージだ」と感じさせる工夫が不可欠です。誰にでも送れるようなテンプレート感のある文面はもってのほかです。
反応率を高める鍵は、個別最適化です。「なぜ、あなたに連絡したのか」「あなたのキャリアやスキルのどこに魅力を感じ、共感したのか」を具体的に伝えなければなりません。候補者の職務経歴書を読み込むだけでなく、GitHubやQiita、個人ブログなどで公開されているアウトプットにも目を通しましょう。
候補者の具体的な活動に触れれば、その他大勢のメールから一線を画し、候補者の心に響く特別な一通となるはずです。
-12-300x157.jpg)
フリーランスからの転換を提案する
転職市場には現れにくい潜在層としてフリーランスエンジニアが挙げられます。彼らは自身のスキルを武器に独立して働く一方で、「大規模なプロジェクトに携わりたい」「安定した環境で新しい技術を学びたい」といったニーズを抱えているケースも少なくありません。
ただし、単に正社員としての安定性を訴求するだけでは不十分です。「あなたのその高いスキルを、当社のこの事業でなら最大限に活かせます」といったように、候補者が「やりたいこと」を実現できる環境を具体的に提示する必要があります。
フリーランス経験者は、自己管理能力や課題解決能力に長けていることが多いため、即戦力を求める企業にとって魅力的な人材です。彼らの心に響くメッセージを届けて、思わぬ即戦力人材を発掘しましょう。
面接構成の工夫(技術・カルチャー分担)
1回の面接で、候補者の全てを判断しようとすると、評価が中途半端になり見極めるべきポイントを見逃してしまいがちです。選考の質を高めるには、面接の役割分担が重要です。
「一次面接は現場のエンジニアが担当し、技術的なスキルや開発経験を深掘りする」「二次面接では、CTOやチームメンバーがカルチャーフィットやチームで働くうえでの価値観を確認する」といったように、面接官ごとに評価の観点を分けるのです。
このアプローチを成功させるためには、事前のすり合わせが欠かせません。各面接で「何を評価するのか」「合格の基準はどこに置くのか」といった評価項目を言語化し、面接官全員で共有しましょう。一貫性のある、質の高い選考プロセスの構築につながります。
採用広報の活用(ブログ・SNS)
採用広報とは、求人広告を出すだけでなく、自社の魅力を継続的に発信していく活動を指します。エンジニア採用においては、現場のエンジニアによる情報発信が候補者の共感を得るうえで有効です。
会社の公式ブログ(noteなど)で開発チームが技術的な挑戦について語ったり、X(旧Twitter)で現場のエンジニアが業務で感じたことや学びをカジュアルに投稿したりします。無理に会社の宣伝をしようとせず、仕事の楽しさや直面している課題、会社の文化や価値観をありのままに語る方が候補者には魅力的に映るでしょう。
すぐには応募につながらないものの、継続することで企業のファンを増やし、「この人たちと一緒に働いてみたい」という感情を育んで、質の高い応募へとつながるのです。
エンジニア面接官の“活かし方”で差がつく
「エンジニアが面接をしています」といっても、採用におけるアピールポイントにはなりません。候補者に「この会社で働きたい」と思わせるためには、「誰が面接に出るか」だけでなく、「どのように候補者と関わるか」という“活かし方”の設計が重要です。
候補者は、面接官であるエンジニアを通じて、その企業の技術レベルや開発文化を判断しています。対等な立場で技術的なディスカッションを楽しんだり、自社の事業や開発の魅力を熱意をもって語ったりすることで、候補者の心を動かすのです。
事前に面接官の役割を明確化し、確認すべき質問項目や評価のポイントをすり合わせておきましょう。選考の精度が向上するだけでなく、候補者は「自分という個人に真剣に向き合ってくれている」と感じ、企業への信頼度と志望度を高めるはずです。
リファラル制度の導入
リファラル採用は、自社の社員に知人や友人を紹介してもらう採用手法です。この制度がうまく機能すれば、カルチャーフィットしやすく、質の高い人材の効率的な採用につながります。
成功の鍵は、金銭的なインセンティブではありません。最も重要なのは、社員が心から紹介したくなるような、魅力的な組織文化や働きがいのある環境を整えることです。リファラル制度の成功は、現在働いている社員の満足度や定着率の高さが前提条件となります。
「紹介してくれ」とただ依頼するのではなく、社員が自社の魅力を語れるように情報提供をしたり、紹介してくれた社員への感謝を伝えたりする文化を作り出さなければなりません。社員満足度を向上させて、リファラル採用という強力な採用チャネルを構築しましょう。
エンジニア採用の失敗あるあると対策
エンジニア採用では、多くの企業が同じような失敗のパターンに陥りがちです。ここでは、そんな「ありがちだけど見落としがちな落とし穴」を整理し、事前に課題への対策を打てるように4つのポイントを解説します。自社の採用活動が同じ轍を踏まないよう、チェックしてみてください。
- なんとなくで始めて迷走する
- 求人票に具体性がなく応募が来ない
- 面接で判断基準がバラバラ
- クロージングが遅く他社に流れる
各ポイントについて詳しく見ていきましょう。
なんとなくで始めて迷走する
エンジニア採用における典型的な失敗例が、「採用すること」自体が目的化し、「どんな人材が必要なのか」という根本的な議論がなされないままスタートしてしまうケースです。
「人手不足で困っているから、とりあえず採用しよう」という曖昧な動機で始めると、採用活動の全てのプロセスで軸がブレてしまいます。ターゲットが不明確なため、誰にも響かない求人票になり、スカウトを送る相手も定まりません。面接に来てもらえても、現場と採用担当者、経営層で求める人物像が異なっているため、評価の基準がそろわず誰も採用できないといった事態に陥りがちです。
採用活動を始める前に必ず採用の背景と求める人物像を徹底的にすり合わせ、採用プロセスを設計しなければなりません。
求人票に具体性がなく応募が来ない
候補者が応募をためらう求人票の書き方には、共通の原因があります。それは、具体性の欠如です。「自社サービス開発をお任せします」「Webアプリケーションの開発経験者募集」といった抽象的な表現では、候補者が会社で働くイメージができないのです。
エンジニアが求める以下の情報を具体的に伝えなければなりません。
- 具体的な業務内容:どのようなプロジェクトをどこまで担当するか、など
- 技術スタック:開発言語やシステム環境など
- 開発体制:開発手順やチームの人数など
日々のタスクが目に浮かぶレベルまで具体的に記載できれば、候補者は自分のスキルや経験が活かせるかどうかを判断できます。安心して応募してもらうには、抽象的な言葉を避け、具体的な事実を並べることが重要なのです。
面接で判断基準がバラバラ
面接官ごとに重視するポイントや質問内容がバラバラだと、選考の信頼性が著しく低下してしまうケースがあります。担当した面接官との相性だけで合否が決まってしまい、本来採用すべき優秀な人材を逃してしまうことになりかねません。候補者にとっても、「面接官によって言うことが違う」と感じれば、その企業に対する不信感につながるでしょう。
この問題を防ぐためには、面接を始める前に評価基準を明確に定義し、全社で統一することが不可欠です。「技術スキル」「カルチャーフィット」「ポテンシャル」といった大きな評価軸を設け、採点基準を事前に明文化して面接官に共有しておくのです。選考のブレがなくなり、客観的で公平な採用判断が可能となります。
クロージングが遅く他社に流れる
優秀なエンジニアほど、複数の企業から同時に内定を得ています。最終的に入社する企業を決める際、候補者はシビアな目で各社の対応を比較するでしょう。クロージングが遅いと、候補者の志望度は一気に下がり、あっという間に他社に流れてしまいます。
「最終面接から内定通知が出るまでに1週間以上かかる」「内定後のフォロー連絡が一切ない」といったスピード感の欠如は致命的です。候補者に不安を抱かせる原因にもなります。
最終面接から内定通知までのフローを見直して、リードタイムは可能な限り短縮してください。採用活動の最終盤における、スピード感と候補者への真摯な向き合い方が、最後の勝敗を分けるといっても過言ではありません。
中途エンジニア採用の成功に向けたチェックリスト
ここまでエンジニアの中途採用に関して、採用施策や失敗と対策について解説しました。これらの内容を現場で活用していただくために、チェックリストを用意しました。各項目を点検し、採用活動の質をさらに高めるためのヒントとしてご活用ください。
- 採用の背景と目的が言語化されているか?
- 求める人物像が明確になっているか?
- 求人票に具体的な業務内容や開発環境が記載されているか?
- 候補者ごとに合わせた対応ができているか?
- 面接の流れや評価基準が社内で統一されているか?
- 内定後の連絡やクロージングがスムーズに行えているか?
各チェック項目について詳しく説明します。
採用の背景と目的が言語化されているか?
採用担当者のみならず、経営陣や現場のエンジニアまで、全社で「なぜ、今このタイミングでエンジニアを採用するのか?」という問いへの答えが統一されているでしょうか。
明確な言葉で採用目的が示されていなければ、求人票やスカウトメール、面接での確認事項など、担当者ごとでバラバラなメッセージを届けてしまいかねません。候補者に対して一貫したメッセージを届けるためにも、採用の背景と目的の言語化は不可欠なのです。
求める人物像が明確になっているか?
求める人物像は、単に必要なスキルや経験年数をリストアップするだけでは不十分です。どのような志向性を持ち、どのような価値観を大切にする人物に来てほしいのかまで具体化できていないと、入社後のカルチャーミスマッチを引き起こす原因となります。
チームの文化に合わずに早期離職となってしまっては、コストと時間が全て無駄になってしまいます。人柄や価値観の解像度をペルソナレベルまで高めて、候補者と企業の双方にとって幸福なマッチングを実現しましょう。
求人票に具体的な業務内容や開発環境が記載されているか?
候補者が応募ボタンを押す前、最も目にするのが求人票です。ここに「具体的な業務内容」や「使用技術(技術スタック)」、「チーム体制」「働き方」などのリアルな情報が記載されていないと、候補者は働く姿をイメージできず、応募をためらってしまいます。
日々の業務が目に浮かぶレベルで具体化すれば、候補者は魅力的な情報として受け取るでしょう。適切な情報開示は、応募率を高めるのはもちろん、マッチング率の向上にもつながるのです。
候補者ごとに合わせた対応ができているか?
テンプレートのスカウト文面や、マニュアル通りに進める面接は、「その他大勢の一人に過ぎない」という印象を与え、興味を失わせてしまいます。毎日のように届くスカウトメールに埋もれないためには、徹底した「個別最適化」が不可欠です。
具体的な根拠に基づいたコミュニケーションが、候補者との信頼関係を築き、接点の質を劇的に向上させます。「あなただから連絡した」という特別感は、多忙な候補者の心を動かし、「話を聞いてみよう」と思わせる重要な一歩となるのです。
面接の流れや評価基準が社内で統一されているか?
面接官によって質問内容や重視するポイントが全く異なると、選考プロセス全体の信頼性や公平性が損なわれます。ある面接官は技術的な深掘りをし、別の面接官は人柄の話ばかり…という状況では、候補者は強い不安と不信感を抱きかねません。企業側にとっても、候補者を客観的に比較検討できなくなるという大きなデメリットを生みます。
これを防ぐためには、評価軸を事前に明確に定義し、評価基準や確認すべき質問項目を言語化した「評価シート」を準備すると良いでしょう。
内定後の連絡やクロージングがスムーズに行えているか?
採用活動の最終局面は、候補者からの選考を受ける企業側の最終試験とも言えます。この段階での対応の遅れは致命的です。最終面接から内定通知までのスピード、そして内定後の丁寧なフォローは、候補者の入社意欲を維持・向上させるうえで重要です。
連絡が遅いと、候補者はネガティブな憶測を巡らせ、より対応の早い他社への入社を決めてしまうでしょう。スピード感のある意思決定と、熱意を伝える誠実なコミュニケーションが採用競争の勝敗を分けるのです。
エンジニア採用が難しいときに検討したい媒体・手法の選び方
エンジニア採用が難しいときには、採用媒体の検討が不可欠です。しかし、自社に合った採用手法を見つけるためには、各手法の特徴と使いどころを理解しなければなりません。そのうえで、自社の採用要件やリソース状況に応じて賢く使い分ける必要があります。ここでは、以下の採用手法を比較し、その選び方について解説します。
- 人材紹介(エージェント)を活用するメリット
- ダイレクトリクルーティングの使い分け
- 媒体別の特徴と選び方(type, Green, Forkwellなど)
人材紹介(エージェント)を活用するメリット
人材紹介(エージェント)サービスは、単に候補者を紹介してくれるだけでなく、企業の採用活動全体をサポートしてくれる心強いパートナーです。特に、社内にエンジニア採用の知見が少ない、あるいは採用担当者のリソースが限られている企業にとってなくてはならない存在です。
専門のエージェントに相談すれば、自社の曖昧な採用要件を言語化する「要件整理」の段階から支援を受けられます。候補者との面接日程の調整から、年収交渉、内定後の入社意思の確認(クロージング)まで、手間のかかる実務を代行してくれます。
初めてエンジニア採用に取り組む企業や、採用活動に多くの工数を割けない企業にとって、エージェントは設計段階から伴走してくれる頼れる存在となるはずです。
ダイレクトリクルーティングの使い分け
ダイレクトリクルーティングは、企業が直接アプローチできる攻めの採用手法です。データベースから自社の要件に合う人材を探し出し、個別にスカウトを送ることで、従来の「待ち」の採用では出会えなかった優秀な人材にアプローチできる可能性があります。
一方で、候補者の選定やスカウト文面の作成、送付後のやり取りなど、運用には相応の手間と時間がかかります。特にエンジニアは日常的に多くのスカウトを受け取っているため、魅力的なスカウトを設計しなければ見向きもされません。
「リソースは十分にあるか」「自社の魅力を言語化できているか」といった点を踏まえ、戦略的に導入することが重要です。リソースと戦略が伴えば、ダイレクトリクルーティングは有効な一手となるでしょう。

媒体別の特徴と選び方(type, Green, Forkwellなど)
求人媒体と言っても、それぞれに特徴や強みがあり、登録しているユーザー層も異なります。例えば、typeやGreenは登録者数が多く、幅広い業種・職種のエンジニアが登録しているため、広く母集団を形成したい場合に適しています。一方で、より専門性の高いエンジニアにアプローチしたい場合は、Forkwellや転職ドラフトといった特化型の媒体が有効です。
また、LAPRAS SCOUTやGitTapのようなサービスは、GitHubなどのアウトプットからプロフィールが生成されるため、積極的に自己PRをしていない潜在層にもアプローチが可能です。
どの手法や媒体も万能ではないため、採用の目的を明確にし、自社のリソース状況に応じて比較検討し、最適な組み合わせを選びましょう。
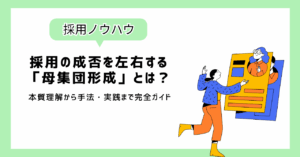
よくある質問(FAQ)
エンジニア採用に関して多くの企業様から寄せられる質問にお答えします。
- なぜエンジニア採用は他職種と比べて難しいのか?
- 中途エンジニア採用の成功企業にはどんな共通点がある?
- なかなか決まらない場合、どこから見直すべき?
- 即戦力を採用したい場合、どのチャネルが向いていますか?
- 未経験可とすると母集団は増える?
なぜエンジニア採用は他職種と比べて難しいのか?
エンジニア採用が他職種に比べて難しい理由は、主に以下の3つの要因が絡み合っているためです。
- 市場全体でIT人材の需要が供給を上回っており、人材不足に陥っていること
- 候補者の技術力評価が難しく、面接官に専門知識が求められること
- 候補者の企業を見る目が厳しく、給与だけでなく開発環境や企業文化などもシビアに比較検討されること
人材不足、面接官の専門知識、候補者のシビアな目の3点を克服する必要があるため、エンジニア採用は他職種と比べて難しいといわれるのです。
中途エンジニア採用の成功企業にはどんな共通点がある?
中途エンジニアの採用に成功している企業には、以下のような共通点が見られます。
- 求める人物像(ペルソナ)が明確で、社内で共有されている
- 個別最適化されたスカウト文面によるアプローチを行っている
- 技術面接とカルチャー面接で役割分担するなど面接体制が整備されている
- 選考から内定通知までのクロージングのスピードが速い
上記のポイント以外にも、一度設計した採用プロセスを都度見直して、改善に力を入れている点も共通しています。
なかなか決まらない場合、どこから見直すべき?
エンジニアの採用が難航している場合、まずは基本的なプロセスから見直しましょう。
最初にチェックすべきは求人票です。業務内容や技術スタックが具体的に書かれているかをチェックしてください。スカウト文面がテンプレートではなく、なぜその人に声をかけたのかが伝わる内容になっているかも重要です。さらに面接の評価基準は明確で、全社で統一されているでしょうか。最後に候補者への連絡がスムーズに行えているかレスポンス速度にも目を向けます。
即戦力を採用したい場合、どのチャネルが向いていますか?
即戦力となるハイスキルなエンジニアを採用したい場合、一つの有効な手段は、エンジニア領域に特化した専門性の高い人材紹介エージェントの活用です。彼らは独自のネットワークを持ち、転職市場には出てこない優秀な人材を推薦してくれます。
また、企業の側から候補者に直接アプローチできるスカウト型サービスも有効です。GitHubの情報などと連携したサービスを使えば、実績のあるエンジニアに直接コンタクトできます。
未経験可とすると母集団は増える?
求人票に未経験可と記載すれば、ターゲットとなる層が一気に広がるため、応募者の数(母集団)は間違いなく増加します。ただし、これは必ずしも良いことばかりではありません。応募者が増える分、書類選考や面接にかかる工数は大幅に増加します。
また、採用後には一人前のエンジニアとして活躍してもらうための育成コストや教育体制の整備が不可欠です。これらの負荷を考慮した上で、長期的な視点から戦略的に判断する必要があります。
エンジニア採用を成功させるなら社内SE転職ナビ

エンジニア採用の課題を感じている企業の皆さま、エンジニアファクトリーはフリーランスエンジニアとのマッチングを通じて、採用活動の新たな選択肢をご提供します。
当社では、業界トップクラスの 継続率95.6% を誇り、多くの企業でプロジェクト成功に貢献してきました。特に、エンド直案件が多数を占めるため、高スキルのエンジニアと直接つながることが可能です。さらに、 公開案件数8,000件以上 のデータベースから、貴社のニーズに合った人材を迅速にご紹介。これにより、案件参画を通じた柔軟なチーム強化を実現します。
エンジニア採用の難しさを感じている今こそ、フリーランスという選択肢を検討してみませんか?採用の一歩を後押しするためのご相談を、ぜひお気軽にお問い合わせください。
まとめ
本記事では、エンジニア採用が難しいと言われる理由から、採用活動を始める前の準備、具体的な施策、そしてよくある失敗例まで、多角的に解説してきました。
エンジニア採用の成功は、小手先のテクニックに頼るのではなく、いかに候補者の視点に立ち、誠実なコミュニケーションを積み重ねられるかにかかっています。本記事で紹介した内容を参考にして採用プロセスの設計を行い、難しいエンジニアの採用を成功させましょう。