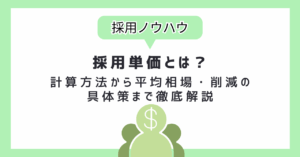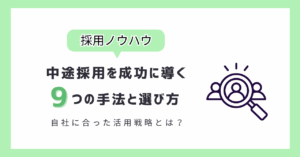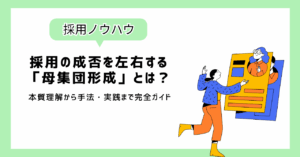DXに取り組む企業が増える一方で優秀なエンジニアの数は不足しており、中途採用に苦戦している企業も少なくありません。しかし、エンジニアの中途採用の難易度は高くなっている傾向にはあるものの、現状を理解し、適切な準備・施策を打てばまだまだ可能性はあります。
この記事ではエンジニアの中途採用を成功させるための準備や施策、媒体選びについて解説します。エンジニアの中途採用に苦戦している担当者の方は、ぜひ最後までご覧ください。

エンジニア採用、こんな課題ありませんか?
- 技術力だけでなく、事業理解も必要だけど、見極めが難しい
- 社内システムを支える柔軟な対応力を持つ人材がなかなかいない
- 企業文化にフィットするエンジニアを採用したい
「社内SE転職ナビ」なら、技術×カルチャーの両面からマッチするエンジニアをご紹介できます。エージェントによる丁寧なヒアリングに加え、企業から直接アプローチできるダイレクトリクルーティング機能もご利用可能。貴社の採用スタイルに合わせて、最適な候補者との出会いをサポートします。
エンジニアの中途採用が難しい理由
「応募が来ない」「内定を出しても辞退される」といった声は、エンジニアの中途採用において頻繁に耳にする悩みです。特に優秀なエンジニアとなると、複数の企業から声がかかるため、より採用が困難になります。
エンジニアの中途採用が難しい理由として、IT人材不足という構造的な背景が挙げられます。経済産業省の調査でも、2030年には最大で79万人ものIT人材が不足すると予測されており、エンジニアは常に「売り手市場」の状態です。この状況下で、企業は限られたパイを奪い合うことになっており「中途採用が難しい」という声が多くあがっているのです。
また、候補者側の「選別意識」の高まりも中途採用を難しくしています。エンジニアは、単に条件の良い企業を選ぶだけでなく、「成長できる仕事か」「働きやすい環境か」といった点を重視します。企業は、候補者の声をキャッチして「選ばれる」存在でなければなりません。
-24-300x157.jpg)
さらに、企業側の採用要件が高度化しすぎている点も問題です。即戦力として、特定の技術スタックや経験を持つエンジニアを求めるあまり、要件が細かくなりすぎ、結果的に該当する人材が極めて少なくなるケースが見られます。現実的な要件設定ができていないと、せっかくの求人も機能しません。
こうした構造を理解せずに採用活動を進めてしまうと、いくら時間やコストをかけても中途採用は難航するばかりです。自社を取り巻く環境と候補者の視点を深く理解して、成功への一歩を踏み出しましょう。
採用活動を始める前にやるべき3つの準備
エンジニア採用を成功させるには、活動を始める前の入念な準備が不可欠です。ここでは、特に重要な3つの準備について解説します。
- 採用の目的と人材像の明確化
- 社内にエンジニアがいない場合の対処法
- 技術環境・制度の棚卸し
採用の目的と人材像の明確化
最初のステップは、採用目的の明確化と人物像設計です。「なぜ今、エンジニアを採用するのか」という根本的な問いに向き合い、その目的を社内で具体的に共有することから始めましょう。採用目的が曖昧なままだと、採用設計全体がブレてしまい、結果として求めるスキルや経験を持ったエンジニア像も不明確になってしまいます。
社内の課題と、エンジニアに期待する点をすり合わせれば、精度の高い人物像を具体化できます。単に技術スキルだけでなく、ペルソナを設定するように、エンジニアの志向性や価値観、将来的なキャリアパスまで踏み込んで検討することが大切です。採用目的と具体的な人物像を設定し、一貫性のある採用活動を展開しましょう。
社内にエンジニアがいない場合の対処法
エンジニアの採用において、技術スキルの見極めは不可欠です。しかし、情シス部門がない企業や、人事単独で採用を進める場合、採用担当側に技術的な知見が不足しているケースもあります。「面接官不在だから採用できない」という状況を脱するためには、以下のような代替手段が有効です。
まず、候補者とのやりとりの中で、これまでの経験してきた技術領域や開発環境を定性的に確認する時間を設けましょう。面接では、具体的なプロジェクト内容や担当範囲、直面した課題とその解決策などを深く掘り下げて聞くことで、技術的な背景を推測できます。

また、あらかじめ想定した質問をテンプレート化しておくことも有効です。これにより、質問漏れを防ぎ、ある程度の技術レベルを判断する材料にできます。
さらに、エージェントとの連携も非常に効果的です。エージェントは、候補者の技術スキルや経験について事前に詳しくヒアリングしており、企業側の要件と照らし合わせてくれます。技術チェックの体制が整っていない企業こそ、「何を聞けばいいのか」といった初歩的な部分から相談できるエージェントと連携して、ミスマッチのリスクを減らし、効率的に採用を進めていきましょう。
技術環境・制度の棚卸し
エンジニアが応募を検討する際、重視する情報のひとつが、入社後の「開発環境」です。そのため、技術スタックや開発体制、コード管理のやり方、使用ツール(例:Slack、Notion、Jiraなど)といった業務環境の実態を具体的に棚卸ししましょう。エンジニアが日々の業務を行う上で直接的に関わる部分であり、自身のスキルや志向に合致するかどうかを判断する重要な材料となります。
また、リモートワークの可否や裁量労働制の有無、貸与されるPCのスペック、評価制度など、働き方や制度面の基本情報も、選別意識の高いエンジニアにとって重要な情報です。これらの情報が社内で言語化されていないと、求人票に具体的に記載できず、結果として候補者との間でミスマッチが生じる原因になりかねません。
可能であれば、実際に開発チームにヒアリングを行い、リアルな情報をまとめておくことをおすすめします。現場の生の声は、求職者の心を動かす情報であり、企業文化やチームの雰囲気を伝える上で効果的です。詳細な情報提供によって、エンジニアは入社後の自分を具体的にイメージでき、安心して応募へと踏み切ることができます。
エンジニアに刺さる7つの採用施策
ここからは、エンジニアの心に響き、応募や入社意欲を高めるための7つの採用施策を紹介します。
- 自社サイトの整備
- スカウト文面の見直し
- フリーランスからの転換
- 面接構成の工夫
- 採用広報の活用
- エンジニアが面接官を担当
- リファラル制度の導入
自社サイトの整備
求人媒体に掲載する情報だけでは、企業の魅力や働く環境を十分に伝えることは困難です。そこで重要になるのが、自社サイトにおける採用ページの改善です。特にエンジニア向けには、開発組織の体制や具体的な技術スタック、社員の働き方や文化が掲載されたページを持つことが効果的です。
たとえば、技術ブログを併設し、日々の開発の様子や技術的な知見を発信すれば、エンジニアは会社への理解を深め、自身のスキルやキャリアプランとの適合性を判断できます。
求人票の情報に加えて、これらの情報が補完的に提供されれば、応募の心理的ハードルが下がり、内定承諾までの離脱率低減につながります。自社サイトを整備し、企業のリアルな姿を伝える重要なメディアとして活用しましょう。
スカウト文面の見直し
スカウトメールの文面は、企業が直接エンジニアにアプローチするダイレクトリクルーティングにおける返信率に影響を及ぼします。「テンプレ感」や「誰にでも送っている感」のあるNG文面は、候補者に「自分には関係ない」と判断されかねません。
返信率を高めるためには、「なぜあなたにこのスカウトを送っているのか」を具体的に書くことが不可欠です。候補者の公開情報を読み込み、自社のどのような点が候補者のスキルや経験、志向性に合致すると考えたのかを具体的に記述してください。
成功するスカウト例文は、一方的な「自社の魅力」を語るのではなく、「あなたに合う」という候補者目線でのメッセージが明確です。パーソナライズされたメッセージを作成し、候補者の返信を促しましょう。
フリーランスからの転換
「正社員は重いけれど、安定した案件には入りたい」と考えるフリーランスが増えています。フリーランス側のライフスタイルの変化に着目し、正社員登用を提案する動きが採用戦略の一つとして注目されています。
まずは業務委託としてプロジェクトに参画してもらい、現場感やカルチャーフィットを確認する期間を設けましょう。企業側は候補者のスキルや人物像を深く理解でき、候補者側も企業の雰囲気や働き方を実際に体験できます。現場感が合致すれば、フリーランスから正社員への転換は非常にスムーズに進みます。
フリーランスの採用はミスマッチのリスクを低減しながら優秀な人材を確保できる有効な手段です。柔軟な働き方へのニーズに応え、新たな採用チャネルを確立しましょう。
面接構成の工夫
面接は、エンジニアのスキルやパーソナリティを見極めるだけでなく、企業と候補者の相互理解を深める機会です。特にエンジニア採用においては、技術面接とカルチャーマッチ面接を分離するなど、目的ごとにフェーズを分けると、評価の精度が向上します。
たとえば、一次面接で技術的なスキルや経験を深掘りし、二次面接ではチームへのフィット感や価値観のすり合わせに重点を置くといった形が考えられます。評価が曖昧になりがちな「チームでやっていけそうか」といった判断も、技術面とは切り離して専門の面接官が担当すれば、客観的かつ深い評価が可能です。
明確な評価軸に基づいた面接構成は、採用の質を高めるだけでなく、候補者にとっても納得感のある採用体験を提供できます。
採用広報の活用
採用広報は、企業の文化や働き方を発信し、エンジニアの志望動機を促す施策です。特にnoteやX(旧Twitter)などのSNSを活用し、社内のエンジニアの声や日常、技術的な取り組みなどを積極的に発信することは、潜在層にリーチする上で非常に効果的です。
たとえば、開発チームのランチ風景や勉強会の様子などを写真や短い記事で紹介すれば、求人票だけでは伝わらないリアルな雰囲気を発信できます。候補者は入社後の自身の姿を具体的にイメージしやすくなるため、親近感や信頼感を抱きやすくなるでしょう。
積極的にエンジニアの採用情報を発信して、転職を積極的に考えていない「転職潜在層」にアプローチを行えば、将来的な採用ターゲット層を広げることにもつながります。
エンジニアが面接官を担当
採用担当者だけでは見えにくい「技術的な深掘り」や「価値観の近さ」を測る上で、現場のエンジニアが面接官を担当することは有効です。同じエンジニア同士だからこそ理解できる専門的な質問や、共感できる技術的な課題の話は、候補者にとって「この会社で働きたい」という強い動機付けになります。
特に専門性の高い技術面接では、現場のエンジニアが社内面接官となることで、候補者の具体的なスキルや経験をより正確に評価可能です。面接を通じて候補者は、入社後に一緒に働く可能性のあるメンバーと直接対話できるため、チームの雰囲気や働き方をよりリアルに感じられます。エンジニア同士の対話によって信頼関係が生まれ、最終的な内定承諾率の向上にもつながるでしょう。
リファラル制度の導入
リファラル制度は、縁故採用とも言われ、社員からの紹介によって人材を獲得する仕組みです。現場の社員が信頼する人物を紹介するため、ミスマッチが少なく、定着率が高いという傾向があります。採用コストを抑えられる点もメリットです。
ただし、紹介制度を設けるだけでは機能しません。紹介者への丁寧なフォローアップや、適切なインセンティブ設計が成功の鍵です。たとえば、紹介者への感謝の意を明確に伝えるためのインセンティブや、候補者がスムーズに選考に進めるようなサポート体制を整えることが求められます。
社員が「この会社に知人を誘いたい」と思えるような、魅力的な組織文化を作り上げることも、リファラル制度を活性化させる上で不可欠です。
採用チャネルの種類と選び方【比較表付き】
エンジニア採用の成功には、自社に最適な採用チャネルの選択が求められます。主な採用チャネルは、大きく分けて以下の5つです。
- 求人媒体(例:Green、Wantedlyなど)
- 人材紹介(社内SE転職ナビ等、エージェント経由)
- ダイレクトリクルーティング(社内SE転職ナビ、LAPRASなど)
- イベント(転職フェア、技術カンファレンス)
- 自社採用サイト・SNS経由
以下は、各チャネルの強みと弱みを比較した表です。
| 採用チャネル | 強み | 弱み |
|---|---|---|
| 求人媒体 | 幅広い層にリーチしやすく、多数の応募獲得が期待できる | 他社との競争が激しく、埋もれやすい |
| 人材紹介 | 専門家が最適な人材を厳選するため、質の高いマッチングが可能 | 成功報酬が高額になりがちで、採用コストが増加する |
| ダイレクトリクルーティング | 企業から能動的にアプローチでき、潜在層にも接触可能 | スカウト文面の工夫や運用に手間がかかり、ノウハウが必要 |
| イベント | 候補者と直接交流し、企業の魅力や雰囲気を伝えやすい | 参加人数が限定的で、多くの候補者にリーチしにくい |
| 自社採用サイト・SNS経由 | コストを抑えつつ、自社のブランドや文化を自由に発信できる | 集客力確保に時間がかかり、コンテンツ作成や運用に工数がかかる |
どの採用チャネルにも強み・弱みがあるため、「これだけをやればいい」という手法はありません。自社の採用目的とターゲットに合わせ、複数のチャネルを組み合わせて効率的な採用活動を実現していきましょう。
エンジニア採用の失敗あるあると対策
多くの企業が、時間とコストをかけても成果に結びつかず、採用失敗に至った経験を持っているのではないでしょうか。ここでは、エンジニア採用で陥りがちな「失敗あるある」を3つの典型例に分け、それぞれの具体的な対策を解説します。
失敗あるある1:求人票の内容に問題あり!
エンジニアは求人票の情報から、どのような人材が求められているかを判断します。書かれている内容が、曖昧であったり、古い情報が掲載されていたりしていると、エンジニアは不信感を抱いてしまうでしょう。
求人票には、開発しているプロダクトの具体的な名称や、それに伴う技術スタックを具体的に記述してください。また、情報が古くないか、矛盾がないかという点にも注意し、必要に応じて現場の担当者に確認することも忘れないでおきましょう。
失敗あるある2:その面接は適切ですか?
面接の目的や評価軸が明確でなければ、「何のための面接だったのか」と候補者に思われかねません。面接官によって話す内容が異なったり、カジュアル面談で採用に関わるシビアな話をしてしまったりすると、最悪の場合、候補者の選考辞退につながりかねません。
面接を実施する前に、目的を明確にして面接官と共有しましょう。面接の段階に応じて、役割分担を明確にし、フェーズごとに評価する項目を統一することも重要です。
失敗あるある3:内定後のフォローは万全ですか?
内定を通知しても入社してくれるとは限りません。連絡が遅かったり、雑なコミュニケーションをしたりすると辞退されてしまうでしょう。また、仮に入社をしたとしても、会社への不信感から早期離職につながる可能性もあります。
内定後こそ候補者との丁寧なコミュニケーションが必要です。入社前に現場を見学してもらうのも良いでしょう。フォロー体制をしっかりと構築し、内定者から信頼される環境の構築が求められます。
中途エンジニア採用の成功に向けたチェックリスト
中途エンジニア採用を成功に導くために、チェックリストを作成して社内で共有することをおすすめします。以下はチェックリストの具体例です。
□ 採用の目的が社内で共有されているか
・採用活動の方向性を統一し、ミスマッチを防ぐため
・採用チーム全体の認識が一致し、効率的な採用が可能となる
□ 求める人物像(スキル・志向性)が明確になっているか
・適切な候補者を見極め、選考基準を明確にするため
・求人票の精度が上がり、質の高い応募者増加につながる
□ 求人票に業務内容や技術環境を具体的に書いているか
・候補者が自身の適性を判断し、入社後ギャップを減らすため
・エンジニアの興味を引き、応募意欲の高い候補者と出会える
□ 面接の流れ・評価軸が統一されているか
・公平な評価を実現し、優秀な人材を取りこぼさないため
・面接の質が向上し、候補者への信頼感を与える
□ 連絡やフィードバックのスピード感が保たれているか
・優秀な候補者を他社に取られないよう、機会損失を防ぐため
・候補者の入社意欲を維持し、内定承諾率の向上に貢献する
□ 候補者目線で「働くイメージ」が伝わる設計になっているか
・候補者が自身のキャリアを具体的に想像できるようにするため
・企業への理解が深まり、入社後の定着率向上につながる
チェックリストを作成し、共有してもそれだけでは不十分です。「なぜこのチェックが必要なのか」「チェックによって得られるものが何なのか」も、担当者間で徹底しましょう。また、採用活動のサイクルごとに見直しを行い、過不足がないかを確認することも重要です。
よくある質問(FAQ)
ここからはエンジニアの中途採用に関して、よくある質問について回答します。
エンジニアの技術力を正確に測るにはどうしたらいいでしょうか?
技術力を正確に測るには、現場のエンジニアに面接官を担当してもらうと良いでしょう。また、実務に近い課題を課すコーディングテストや、GitHubなどの公開リポジトリの確認も効果的です。単なる知識だけでなく、実際の開発スキルや問題解決能力も評価できます。
現場のエンジニアをどのように巻き込めばいいでしょうか?
現場のエンジニアの協力を得るには、採用活動が自身のチーム強化や業務効率化につながることを具体的に伝えるのが鍵です。新しいメンバーが加わることで、技術的な挑戦が可能になったり、既存業務の負担が軽減されたりといったメリットを明確に提示しましょう。
スカウトメールの返信率を向上させるにはどうしたらいいですか?
スカウトメールの返信率向上には、徹底したパーソナライズが不可欠です。候補者の職務経歴や公開されているSNS、ブログなどを丁寧に読み込むことが重要です。一般的なスカウト例文ではなく、候補者のスキルや志向性が自社のどの点に合致するかを具体的に記述しましょう。
早期離職を防ぐために、どんな準備が必要でしょうか?
早期離職を防ぐには、採用選考の段階からミスマッチを極力なくす準備が必要です。企業文化や実際の働き方、チームの雰囲気などを候補者に包み隠さず伝えるカジュアル面談やオフィス見学の機会を設けましょう。
自社で対応できない条件を希望する候補者が多いのですが、どこまで対応したらいいでしょうか?
自社で対応が難しい条件(例:フルリモート、高額な給与)を希望する候補者には、まず自社の現状と譲れない点を明確に伝えましょう。そのうえで、候補者の希望の背景にあるニーズを理解し、お互いに納得できる着地点を探る姿勢が求められます。
即戦力のエンジニア採用は社内SE転職ナビ

エンジニア採用において、スキルマッチとスピード感は欠かせません。「社内SE転職ナビ」では、取引企業3,300社以上・公開求人数7,000件以上(2025年6月時点)という実績を背景に、社内SE経験者を中心とした即戦力人材にリーチできます。
さらに、ダイレクトリクルーティングにも対応しており、自社で直接スカウトを送る運用もスタートしています。「今すぐ採用したい」も「将来に向けて関係構築をしたい」も、どちらの採用フェーズにも対応。まずはお気軽にご相談ください。

まとめ
本記事では、企業がエンジニアを中途採用する難しさについてまとめました。正しく背景を理解すれば、今後とるべき施策が明確になるでしょう。本記事で紹介した採用活動を始める前に行うべき準備や、採用施策を参考にして自社のエンジニア採用戦略を構築してください。
また、利用すべき採用チャネルにも種類があり、それぞれ強みや弱みがあることも説明しました。ひとつのチャネルにこだわらず、自社に合った手法を組み合わせて、効率的な採用活動を実現しましょう。
エンジニア採用の成功は、一朝一夕で達成できるものではありません。仮に採用失敗となった場合でも、対策を実践し改善していけば、着実に成果へとつながります。求めるエンジニアを採用できるよう本記事の内容をご活用ください。