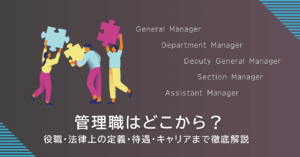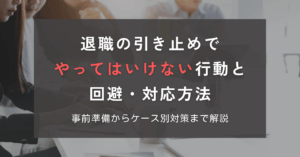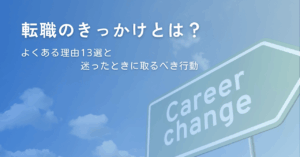「金融系SEって何をする仕事なの?一般のSEとどう違うの?」と疑問を抱いている方は多いのではないでしょうか。
本記事では、金融系SEの業務内容や年収、求められるスキル、使用言語、働き方の特徴まで詳しく解説します。本記事を読むことで、金融系SEのキャリアがより明確になり、自分に適しているかどうか判断できるようになります。
金融業界でのIT職を検討している方や、転職やスキルアップを目指しているエンジニアの方は、ぜひ最後までご覧ください。

金融系SEとは
金融系SEとは、銀行・保険・証券といった金融業界のシステム開発に携わるエンジニアのことを指します。
一般的なSEと同様に、要件定義や設計、開発、テスト、運用保守といった工程を担当しますが、金融系SEには金融取引の仕組みや業界特有のルールに関する深い理解も求められます。こうした背景から、他の業種と区別して「金融系SE」と呼ばれるのです。
また、昨今ではフィンテックの進展やブロックチェーン技術の普及により、金融業界のデジタル化が一層加速しています。業務の効率化や新しいサービス展開が急務となるなかで、金融系SEの需要は高まり続けています。
そのため、ITスキルに加え、金融知識を武器にキャリアを築きたいエンジニアにとって、金融系SEは非常にやりがいのあるポジションだといえるでしょう。業界動向に敏感なエンジニアであれば、今後の成長性を見込んで目指す価値は十分にあります。
一般的なSEとの違い
金融系SEと一般的なSEの最大の違いは、担当するシステムの業界特性にあります。SE全般がソフトウェアやシステムの開発・運用を行う点は共通していますが、金融系SEは銀行や証券会社、保険会社といった金融機関で使用されるシステムを対象に業務を行います。
金融システムは、1円の誤差も許されない厳密な処理や、取引の正確性・セキュリティを重視する設計が求められるため、エンジニアとしての正確性と責任感が非常に重要です。また、金融商品や決済の仕組み、法的な規制に関する理解も欠かせません。
このように、金融系SEは高度なITスキルに加えて、専門的な金融知識や業界理解が求められる職種であり、単なる技術者にとどまらず、業務そのものへの深い理解が必要です。
金融系SEの役割と仕事内容~7つの業種別に解説
金融系SEの業務内容は、所属する金融機関の業種によって大きく異なります。たとえば銀行では預金や送金に関するシステムが中心となり、保険会社では保険契約の管理や営業支援が求められます。
一方、証券会社では証券取引や顧客の資産情報を扱う複雑なシステムが必要です。このように、金融機関ごとに取り扱うサービスや業務の性質が異なるため、SEが担う役割も大きく変わるのです。
ここでは所属ごとの金融系SEの業務内容を詳しく解説していきます。
1. 金融機関(銀行、信用金庫等)
銀行の金融系SEは、顧客の口座管理や窓口対応、インターネットバンキングといった日常的な業務を支えるシステムの開発が担当です。具体的には、預金や出入金の処理を行う勘定系システム、営業支援ツール、窓口業務のシステムなどが含まれます。
これらは銀行業務の中核を担う重要なシステムであり、ミスやトラブルが許されません。そのため、業務では高い安定性と正確性が求められます。また、顧客情報を整理・保管するデータベースの設計や、取引履歴を活用した分析システムの開発も担当範囲です。利用者の行動をもとにしたサービス改善や、不正検知・リスク管理などの高度な対応を手がけます。
このように銀行のSEは、業務の円滑化から顧客対応の質の向上までを幅広く支える存在です。業務知識とIT技術の両面が求められるため、専門性の高い役割といえるでしょう。
2. 保険会社
保険会社の金融系SEは、主に保険商品の管理や契約業務を支援するシステムの開発を担当します。具体的な作業は、保険商品の販売管理や契約の更新、営業支援システムなど、保険業務の効率化に直結するツールの構築が中心です。
営業現場で活用されるライフプラン作成ツールやファイナンシャルプランナー向けの支援ソフトも、SEの手によって設計・開発されます。
また、契約情報や顧客データを蓄積・分析する情報システムの整備も重要です。取引履歴から営業戦略を立案したり、帳票管理の効率化によって事務作業の負担を減らしたりと、経営や業務改善にも貢献しています。
保険会社のSEは、商品知識と業務理解を活かして、営業や管理部門と連携しながら業務を支える役割を果たしています。多方面からのニーズに応える柔軟性も求められる仕事です。
3. 証券会社
証券会社で働く金融系SEは、株式や債券といった証券の売買に関するシステムを中心に開発を行います。特に、注文の受付から約定までの流れを管理する取引システムや、法令遵守を支えるコンプライアンスシステムの構築が、顧客資産と企業の信用を守るため重要な業務です。
また、顧客対応をサポートする営業支援ツールや、取引データを管理する顧客管理システム構築も、業務の効率化に欠かせない要素です。加えて、海外取引が多い証券業界では、対外接続システムのように外部との情報連携を行う仕組みや、取引データ・顧客動向の分析を行う情報システムの開発も行います。
証券会社のSEは、高度な金融知識とシステム設計力の両方が必要とされるポジションであり、情報の正確性とスピードを両立させることが成果に直結します。
3.決済サービス会社(カード会社・フィンテック企業など)
クレジットカード会社やQRコード決済、電子マネーを扱う企業に所属するSEは、日常の消費活動を支える決済インフラを開発・運用します。
主な業務は、決済処理システム、ポイント管理、加盟店管理、不正検知やセキュリティ機能の設計など。大規模トランザクションを高速かつ正確に処理するため、高性能なアーキテクチャ設計が求められます。
スマホアプリやWeb決済システムの構築、API連携、クラウド環境の活用など、モダンな開発スキルも重視される分野です。
4. 金融システムベンダ(SIer)
金融システムベンダは、銀行や保険会社など金融機関のIT業務を外部から支援する立場で、要件定義から設計・開発・保守まで一貫して担当します。
常駐型の案件も多く、顧客企業の業務を深く理解した上で、システム要件に落とし込む力が必要です。近年は、勘定系や情報系の老朽化したシステムを、クラウドやマイクロサービスへと再設計するモダナイゼーション案件も増加。顧客折衝力・提案力・技術知識のバランスが求められます。
5. ノンバンク系(リース・信販・消費者金融など)
ノンバンク系企業に所属するSEは、ローンやリース契約の管理、与信判断、請求・回収業務を支えるシステムを担当します。
顧客属性や与信結果に基づいたスコアリング処理、不正検知、提携先とのデータ連携などが主な業務です。業界的にコンプライアンスが厳しく、法規制対応や内部統制を意識したシステム設計が重視されます。また、スピード感のある改善提案や、営業支援ツールの開発も重要です。
6. 金融スタートアップ・FinTechベンチャー
スタートアップやベンチャーに所属する金融系SEは、既存の金融サービスを革新するようなプロダクトの開発に関わります。
投資アプリ、少額保険、給与前払い、家計簿連携など、ユーザー向けサービスを設計から実装・改善まで広範囲に担当するケースが多いです。
俊敏な開発(アジャイル)、スモールチーム、ユーザー視点が重視され、フロント・バック問わずフルスタックで動ける人材が歓迎されます。技術トレンドへの感度と自走力も問われる領域です。
7. 中央省庁・関連機関(日本銀行、金融庁、国税庁、証券保管振替機構など)
中央省庁やその関連機関に所属する金融系SEは、金融業界全体の土台となる制度インフラや共通基盤システムの設計・運用に携わります。銀行や証券会社といった“民間のプレイヤー”ではなく、業界を支える「ルール作り」「監督機能」「情報インフラ整備」を担う立場から、SEとしての役割も大きく異なります。
代表的な開発対象には以下のようなものがあります:
- BOJ-NET(日銀の決済ネットワーク)
- EDINET(金融庁の電子開示システム)
- e-Tax(国税庁の電子申告)
- 金融EDI・統一API基盤(各業態共通)
- 公的な金融情報プラットフォーム
これらのシステムは、銀行や証券会社、保険会社など広範な金融機関の業務基盤となる共通インフラであり、安定性・セキュリティ・制度対応力が強く求められます。
また、業務の特性上、制度改正や法令変更にあわせたシステム対応が頻繁に発生します。新しい金融制度が導入される際に、業界全体がスムーズに移行できるよう設計・調整するのも重要な業務です。
現場では、SIerや大手ITベンダーと協働しながら要件定義・設計・テスト・移行などを担当します。ユーザーは金融機関全体という広い視点であり、技術力に加えて業界知識や制度理解力、関係各所との調整力が求められる領域です。
中央省庁・関連機関で働くSEは、公共性の高い仕事に携わりたい人や、金融業界全体にインパクトを与える立場で活躍したい人にとってやりがいの大きいポジションといえるでしょう。
金融系SEの平均年収
金融系SEは、他の業種と比べて高収入を得られる可能性が高い職種です。
平均年収はおよそ750万円とされており、一般的なSEの平均年収である500万円から550万円と比較すると、200万円以上も高い水準にあります。この高い報酬水準は、金融系SEが担う責任の重さと求められる専門性の高さを反映した結果といえるでしょう。
年代別に見ると、20代では500万円から750万円、30代では700万円から900万円、40代では800万円から1,000万円、50代では1,200万円に達することもあります。特に40代以降の年収上昇が顕著で、豊富な経験と高度な専門知識を持つベテラン金融系SEには、非常に高い報酬が提供される傾向があります。
このように、金融系SEは長期的にスキルと実績を積み上げることで高収入を狙える職種です。将来的なキャリアアップや収入面を重視する方にとって、魅力的な選択肢といえるでしょう。
金融系SEに必要なスキル
金融系SEとして活躍するには、IT分野の知識や技術だけでなく、金融業界ならではの知識や実務経験も求められます。特に、システムの正確性やセキュリティが重視される金融の現場では、汎用的なITスキルに加えて、金融業界に関する理解やセキュリティ実務の経験が強みになるでしょう。
ここでは、金融系SEとして身につけておきたい代表的なスキルや知識について詳しく解説します。
ITスキル
金融業界のシステムは、高い正確性と可用性が要求されます。そのため、SEには基盤となるITスキルの幅広さと堅実な実装力が求められます。
【金融系SEに求められることの多い技術】
- 開発言語: Java、C#、Python(分析系)、一部レガシーではCOBOL
- データベース: Oracle、SQL Server、PostgreSQL
- インフラ: Linux/Windowsサーバ、VMware、AWSやAzureなどのクラウド構築スキル
- 開発手法: ウォーターフォール中心だが、FinTech系ではアジャイルの導入も進行中
COBOLは今も大手銀行の勘定系システムなど一部で使われているものの、新規開発ではJavaやC#が主流です。クラウドシフトが進む中で、クラウドネイティブな設計やAPI連携、セキュアな通信構成の設計スキルも評価されやすくなっています。
金融業界に関する知識
金融系SEは「業務の背景を理解していること」が大前提とされる職種です。単に仕様通りに作るだけではなく、ユーザー部門と同じ目線で業務課題を読み取れるかが問われます。
【知っておくと有利な知識の例】
- 融資、預金、保険契約などの業務フロー
- リスク管理やAML(マネーロンダリング対策)といった金融規制
- 金融庁ガイドラインやBIS規制、FISC安全対策基準への対応
- 証券取引、信用リスク、約款処理など、細かな業界ルール
こうした業務知識を補強するために「銀行業務検定」や「証券外務員資格」「保険募集人資格」を取得するSEも増えています。システムの精度だけでなく、業務部門との円滑な連携ができるかどうかも評価されるポイントです。
ITセキュリティの実務経験
金融系の現場では、個人情報や資産データなどを扱うため、セキュリティは“機能”ではなく“前提”として求められます。システムの利便性やスピード以上に、不正アクセスを防ぎ、トラブル時に被害を最小限に抑える仕組みづくりが不可欠です。
【金融系SEの業務で重視されるセキュリティ対応】
アクセス権限の設計(RBACなど): 利用者ごとに適切な権限を割り当て、不正アクセスを未然に防止
通信の暗号化・証明書管理: インターネットバンキングなどの安全な通信を確保
ログ監視・SIEM連携: 異常な操作やアクセスを検知し、インシデント対応の初動を迅速化
脆弱性対応(OWASP対応など): システムの弱点を事前に洗い出し、改修によって攻撃リスクを排除
さらに近年では、クラウド環境でのゼロトラスト設計や、SOC(セキュリティ運用監視センター)・CSIRT(インシデント対応チーム)との連携経験も重視されており、これらに関与した実績はセキュリティ専任ポジションやマネジメント層へのキャリアアップに直結します。
また、知識の裏付けとして、以下のような資格も評価の対象となります。
情報処理安全確保支援士(登録セキスペ): 国家資格で、セキュリティ全般の知識証明に有効
CISSP: グローバルで通用するハイレベルな資格。管理職・マネージャー層にも適した内容
CISA: システム監査寄りの資格で、内部統制やガバナンス重視の企業で重宝
CompTIA Security+: 実務に即した内容で、実践的な知識・スキルの証明に向いている
こうしたセキュリティ分野の知識や経験は、単に一領域の専門性にとどまらず、今後のキャリア選択を広げる基盤となります。エンジニアとしての信頼性を高める意味でも、意識的に強化しておきたいスキル領域です。
金融系SEでよく使われるプログラミング言語
金融系SEとして働くうえで、使用するプログラミング言語の種類は非常に重要です。代表的なものとしては、Java、COBOL、C#が挙げられ、いずれも金融業界で長く使用されてきた実績があります。
それぞれの言語には得意分野や開発環境の特徴があり、開発対象となるシステムや企業文化に応じて選定されています。これらの言語を理解することで、より実践的なスキルを身につけられるでしょう。
Java
金融系SEが扱うプログラミング言語の中でも、Javaは特に汎用性が高く、幅広い開発現場で採用されています。JavaはOSに依存せずに動作する仕組みを持っており、Java Virtual Machine(JVM)上で動作するため、どの環境でも同じようにプログラムを実行できることが特徴です。
この柔軟性により、銀行や保険会社といった多様な金融機関のシステムでも導入が進んでいます。さらに、Javaは堅牢でセキュリティ面にも優れており、取引情報や顧客データなどを扱う金融業界において安心して使用できる言語といえるでしょう。
また、Webアプリケーションから業務システムまで開発可能なため、Javaのスキルを持っていれば多様なプロジェクトに携わるチャンスが広がります。実績の多さと信頼性の高さから、今後も金融系SEにとって重要な言語であることに変わりありません。
COBOL
COBOLは、特にレガシーシステムを多く抱える金融業界で根強く使用されているプログラミング言語です。1950年代に登場した歴史ある言語ですが、その設計思想は業務処理向けに特化しており、帳票出力や大量データの処理において今なお高いパフォーマンスを発揮します。
特に、銀行や保険会社の勘定系システムでは、COBOLが多くの基幹処理を担っており、その安定性は長年にわたり証明されてきました。また、COBOLは保守性にも優れており、一度構築されたシステムが長期間にわたって運用されるケースが多いため、今後も一定の需要が見込まれています。
加えて、COBOLに対応できるエンジニアの数が減少傾向にあることから、スキルを持っていると市場価値の高い人材として重宝されるでしょう。金融系SEを目指すうえで、COBOLの知識は今後も有効な武器となります。
C#
C#はMicrosoftが開発したオブジェクト指向のプログラミング言語で、金融業界においても特定の業務アプリケーションや社内ツール開発などに広く活用されています。
主に.NET環境での開発に用いられるため、Windowsベースのシステムとの相性が非常に良く、銀行や証券会社の社内システムでも重宝されています。また、C#は文法がJavaに似ているため、Java経験者にとっても習得しやすく、複数言語を扱うプロジェクトにおいても効率よく対応できるのが利点です。
加えて、GUIアプリケーションやWebアプリケーションの開発にも強く、ユーザーインターフェースが求められる場面でも活躍できます。近年ではクラウドサービスとの連携やセキュリティ機能の実装においてもC#の採用が進んでおり、柔軟性と拡張性を兼ね備えた言語としての地位を確立しています。
金融系SEとしてのスキルの幅を広げるうえで、C#の習得は非常に有益といえるでしょう。
金融系SEの働き方の特徴
金融系SEは、他の業界のSEと比べて独自の働き方の特徴を持っています。最大の要因は、金融システムが社会インフラとして極めて高い信頼性を求められる点にあります。そのため、セキュリティ上の制約から常駐勤務が基本となるケースが多く、在宅勤務は限定的です。
また、取り扱う情報の重要性から、ミスが許されない環境であることも特徴の一つです。そのぶん、業務に対する責任も重くなりますが、収入面では高水準が期待できる職種でもあります。
常駐が多い
金融系SEの働き方において、常駐勤務が基本であることは大きな特徴です。理由は、扱う情報の機密性が極めて高く、データを外部に持ち出すことが許されないためです。
金融システムは個人情報や取引データなど、漏洩すれば企業の信用を大きく損なうような情報を多数扱っています。そのため、セキュリティ対策が徹底された社内環境で業務を行う必要があり、結果として常駐勤務が主流になっているのです。
また、開発中のシステムにトラブルが発生した際、即座に対応できる体制を整えておく必要もあります。こうした理由から、金融系SEの多くはクライアント先に常駐して業務を行っており、在宅勤務やリモート対応は一部の保守業務に限られるケースがほとんどです。
柔軟な働き方を求める方にとっては制約となるかもしれませんが、それだけ重要なシステムに関われる責任あるポジションだと言えるでしょう。
社会的・金銭的インパクトの大きい業務
金融系SEの業務では、一つのミスが金銭的損失や社会的信用の失墜につながりやすいという、非常にシビアな側面があります。これは、他業種にも共通する「正確性が求められる」というレベルを超えて、実害の大きさと即応性の要求水準が段違いである点に特徴があります。
たとえば、勘定系システムで入出金の金額が誤って処理されると、個人の生活に直結する問題となり、銀行へのクレーム対応や行政への報告対応が必要になります。株式や為替取引の分野では、システム障害によってわずか数秒の遅延が億単位の損害につながることもあります。
さらに、ログの取り扱いや監査証跡の保存義務なども厳格で、人的ミスの発生を前提としない設計・運用体制が求められるのも特徴です。したがって、金融系SEは単に「正しく作る」だけでなく、想定外のトラブルをどう抑止し、万が一の際にどう最小化するかまで含めて考える必要があり、技術力と冷静な対応力が問われます。
こうした厳しい環境に身を置くことはプレッシャーにもなりますが、同時に技術者としての信頼や評価を高める絶好の機会とも言えるでしょう。
高収入
金融系SEは、ITエンジニアの中でも比較的年収水準が高いポジションであることが多いです。その背景には、業務の専門性の高さと、業界全体としての収益性・規模の大きさがあります。
金融システムは、1件あたりの取引金額が大きく、トラブルが直接的に顧客資産や信用リスクに直結するため、技術的な信頼性が非常に重要視されます。その結果、エンジニアにも高い設計力、正確性、業務理解が求められ、必然的に報酬水準も引き上げられているのです。
特に以下のようなスキル・経験を持つ人材は、市場価値が高くなります。
- JavaやC#、COBOLなど金融系でよく使われる言語に精通している
- 金融業界の業務知識(融資、証券取引、保険契約など)を持っている
- セキュリティ設計、インフラ構築、法規制対応などの実務経験がある
また、SIerやシステムベンダ経由での金融常駐案件では、手当や時間外労働の割増、技術者単価の高さが給与に反映されるケースも多く、結果として30代で年収700万円台、40代で1,000万円を超えることも珍しくありません。
ただし、報酬に見合うだけの責任とプレッシャーが伴う仕事でもあるため、「単に収入が高いから選ぶ」のではなく、専門性を高め、長く価値を発揮できるキャリアとして選ぶ意識が重要です。
社内SEの求人なら社内SE転職ナビ

金融系SEとして求人をお探しなら7,000件以上の求人を公開する社内SE転職ナビがおすすめです。IT業界に特化した転職支援サービスであり、金融業界に強い求人や社内SE職に関する豊富な情報が集まる点が特徴です。
開発エンジニアやインフラ系職種はもちろん、IT企画・マネジメント、情シス、テクニカルサポート、テスターなど、幅広い職種の求人を扱っています。そのため金融系SEの中でも自分に最適なポジションを見つけられるでしょう。提案求人数は一人あたり平均25.6社と非常に充実しており、定着率も96.5%という高い実績を誇ります。
また、状況に応じてカジュアル面談とキャリア面談を選べる柔軟さも魅力で、どちらもオンラインで実施可能です。在職中でも転職活動を無理なく進められるため、金融系SEとして自分に合った職場を見つけたい方に最適な選択肢といえるでしょう。
まとめ
本記事では、金融系SEの業務内容や年収、必要なスキル、働き方の特徴について詳しく解説しました。金融系SEは、銀行・証券・保険といった各業界に応じた専門性が求められる職種であり、一般的なSEと比べて高い安定性と収入が期待できる点が魅力です。
一方で、常駐勤務や高い正確性が求められるなど、業務の厳しさも伴います。ですが、ITと金融の両方のスキルを活かして働きたい方には、非常にやりがいのあるフィールドです。
今後のキャリアを見据えて、自分の適性や志向に合うかどうかを見極める材料として、本記事の情報が少しでもお役に立てば幸いです。