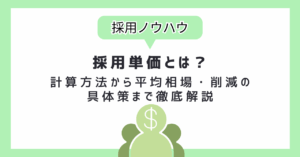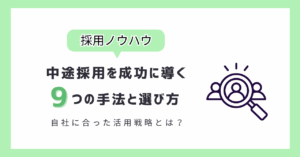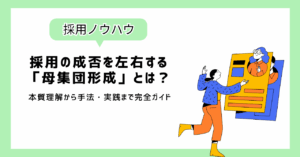エンジニア採用の難易度が高まるなか、人材確保の手段として「副業エンジニア」の活用に目を向ける企業が増えています。高い専門性を持つ人材を、必要な時に必要な分だけ業務を委託できるため、企業にも大きなメリットがあります。しかし、安易に副業エンジニアを採用すると、期待した成果は得られません。
本記事では、副業エンジニアの採用方法と活かし方について解説します。採用の前に整理すべきこともまとめるので、副業エンジニアの活用を検討している方は最後までご覧ください。

エンジニア採用、こんな課題ありませんか?
- 技術力だけでなく、事業理解も必要だけど、見極めが難しい
- 社内システムを支える柔軟な対応力を持つ人材がなかなかいない
- 企業文化にフィットするエンジニアを採用したい
「社内SE転職ナビ」なら、技術×カルチャーの両面からマッチするエンジニアをご紹介できます。エージェントによる丁寧なヒアリングに加え、企業から直接アプローチできるダイレクトリクルーティング機能もご利用可能。貴社の採用スタイルに合わせて、最適な候補者との出会いをサポートします。
副業エンジニアを“採用の選択肢”に入れるときに考えること
エンジニアの採用が難しくなっているなか、副業エンジニアは企業にとって重要な存在です。しかし、正社員と業務委託とは性質が異なるため、企業側が副業エンジニアを正しく理解し、受け入れ体制を整えなければなりません。本稿では以下の2つの視点で、副業エンジニアを採用する前に考えておくべきポイントを解説します。
- 正社員採用との違いを前提に持つ
- 「業務委託」とも異なる副業の立ち位置
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
正社員採用との違いを前提に持つ
副業エンジニアの活用を検討する際、正社員とは根本的に異なる働き方をするという点を理解しておかなければなりません。最も大きな違いは、稼働時間とコミットメントの度合いです。
本業を優先する副業エンジニアに対して企業が期待できる稼働時間は、週数時間から十数時間程度と限定的です。正社員のようにフルタイムでの業務遂行や、突発的な残業対応などは期待できません。責任範囲も、事前に契約で定められた特定の業務やタスクに限定されます。
稼働時間や業務への関与が限られるため、チームビルディングに深く関わったり、企業文化を自然に吸収・浸透させたりといった効果は期待できません。副業エンジニアに対して、正社員と同じような帰属意識や貢献意欲を求めるのは避けましょう。
このような違いを正しく認識せず、正社員の代替として安易に考えると、双方にとって不幸なミスマッチが生じる可能性があります。
「業務委託」とも異なる副業の立ち位置
一般的に企業は副業エンジニアと業務委託契約を結ぶ場合が多いものの、フリーランスのエンジニアや開発会社といった「業務委託」のプロフェッショナルと同じ扱いは避けましょう。最大の違いは、副業エンジニアの多くが「他に本業を持っている」という点です。本業の合間や余暇を活用して働いているのであって、生活の主軸ではないのです。
万が一、本業が繁忙期に入ったり、突発的なトラブルが発生したりすると、副業の業務は一時的に滞りかねません。フリーランスのプロであれば、契約期間中はプロジェクトへのコミットメントを最優先に考え、納期遅延や品質低下を避ける傾向にありますが、副業エンジニアに対して同等のコミットメントを求めるのは困難です。
稼働時間やコミュニケーションのタイミング、緊急時の連絡手段などについて、過度な期待をせずに合意形成を行うことが求められます。
副業エンジニアを活かせる企業・活かしづらい企業の違い
副業エンジニアは、高いスキルを持つ人材の力を柔軟に活用できる魅力的な選択肢ですが、すべての企業に有効というわけではありません。受け入れる企業側の体制や文化によっては、副業エンジニアを活用しづらい場合もあります。
本稿では、副業エンジニアを活かせる企業と活かしづらい企業の具体的な特徴をそれぞれ解説します。貴社がどちらに近いのかを判断するための参考にしてください。
- 活かせる企業の特徴
- 活かしづらい企業の特徴
順番に詳しく解説します。
活かせる企業の特徴
副業エンジニアを活かせる企業には、以下のような特徴があります。
- 業務の切り出しが明確である
- 情報共有の仕組みが整っている
- 非同期コミュニケーションに慣れている
業務の切り出しが明確であれば、副業エンジニアは限られた時間のなかで安心して業務を遂行可能です。依頼するタスクやプロジェクトの範囲、期待する成果物が具体的かつ明確に定義されていなければなりません。
また、開発に必要な仕様書や設計書、環境構築手順、コーディング規約などのドキュメント化も重要です。NotionやConfluence、GitHubといったツールを通じて容易にアクセスできれば、副業エンジニアはスムーズに業務を開始できます。
さらに、担当者がSlackやTeamsなどのチャットツールを活用した非同期コミュニケーションに慣れていれば、副業エンジニアとの連携も円滑に進むでしょう。
活かしづらい企業の特徴
一方で、副業エンジニアを活かしづらい企業には、以下の特徴がみられます。
- 業務の属人性が高い
- リアルタイムでの意思決定が多い
- 曖昧な指示や状況依存の判断が多い
業務の属人性の高い企業であれば、特定の人物がいなければ業務が進まないため、外部の副業エンジニアが稼働しても成果を出すのは困難でしょう。
また、リアルタイムの意思決定や対面での会議が常態化している企業でも、副業エンジニアの活用は困難です。労働時間が限られており、常にオンラインで即応できるわけではない副業エンジニアは、同期的なコミュニケーションが前提となる業務プロセスは不向きです。
指示が曖昧であったり、状況に沿った柔軟な判断が求められたりする点も、活かしづらい企業の特徴です。契約で定められた範囲の業務遂行が基本であるため、明確な指示や定義なしに高いパフォーマンスを期待するのは難しいでしょう。
採用時にすれ違いやすいポイントと防ぎ方
企業が副業エンジニアを採用する際には、思わぬトラブルが生じないように、認識にすれ違いが生じないように注意が必要です。ミスマッチが生じると、プロジェクトの遅延や品質低下だけでなく、双方の不信感にもつながりかねません。本稿では以下の3つのポイントに沿って解説します。
- “週2〜3日稼働”が実質5〜8時間しかない
- Slackを見られるのは夜や休日だけ
- 求めていた役割と実際の出力がズレる
各ポイントについて詳しく見ていきましょう。
“週2〜3日稼働”が実質5〜8時間しかない
「週2〜3日程度の稼働」という条件は、副業エンジニアの募集要項でよく見かける表現です。しかし、企業と候補者の間で認識のズレが生じやすい代表的なポイントでもあります。
企業側は、1日あたり数時間、週に十数時間程度のまとまった稼働を期待するでしょう。しかし、副業エンジニアにとっては、本業の合間や週末に細切れで作業時間を確保し、週に5〜8時間程度になるというケースも少なくありません。
労働時間に関する認識のズレを防ぐには、契約前に「週に合計何時間程度の稼働を想定しているのか」「主にどの曜日・時間帯での作業を想定しているか」といった点を具体的に確認しましょう。
時間だけで縛るのではなく、「依頼するタスクはこの3つで、それぞれこの程度のボリュームです」といったように、完了してほしいタスクの粒度や量で期待値を伝える方法も効果的です。
Slackを見られるのは夜や休日だけ
副業エンジニアとのコミュニケーションは、SlackやMicrosoft Teamsといったチャットツールを主に利用します。副業エンジニアは、本業に就いている日中は返信が困難であるため、利用頻度や返信タイミングについて事前に合意しておくといいでしょう。
合意がなされないままでいると、「質問への返信が遅い」「緊急の連絡が取れない」といった不満につながり、業務の進行に支障をきたしかねません。
コミュニケーションのタイミングに関してすり合わせたうえで、業務内容自体を、できる限り非同期コミュニケーションで完結できるよう設計してください。リアルタイムでのやり取りを前提としないタスクを中心に依頼します。
本当に緊急を要する連絡が発生した場合の連絡手段やタイミングについても、事前にルールで定めておけば、いざというときの混乱を防止できます。
求めていた役割と実際の出力がズレる
企業が副業エンジニアに期待していた役割や業務範囲が、実際のアウトプットとズレてしまうケースもあります。例えば、企業側が「既存コードのレビュー」を期待していたにもかかわらず、「新規機能の実装」が得意な副業エンジニアを採用すると、低品質なレビューしか実行されないかもしれません。
募集段階で、依頼したい業務内容や期待する役割、必要なスキルセット、そして具体的なアウトプットイメージを可能な限り詳細に明記しましょう。選考過程で候補者の経験や得意分野、副業を通じて実現したいことなどを丁寧にヒアリングし、企業が求める役割と本人の志向が合致しているかを慎重に見極めます。
業務開始後は、毎週の定例ミーティングなどを通じて、業務の進め方やコミュニケーションの取り方、期待値などについても確認しましょう。細かくフィードバックし合って、長期的に良好な協力関係を築くことが重要です。
副業人材を“チームの一員”として機能させる運用設計
副業人材を企業の成果に貢献できる“チームの一員”として機能させるには、副業エンジニアがパフォーマンスを発揮できる運用設計が必要です。本稿では、非同期でのコミュニケーションが中心となる副業エンジニアが、主体的に業務に取り組みやすくなる環境を構築するためのポイントを、以下の2点に沿って説明します。
- 期待値のすり合わせとレビュー機会の設計
- 非同期環境での情報共有とオンボーディング
各ポイントについて詳しく解説します。
期待値のすり合わせとレビュー機会の設計
副業エンジニアをチームの一員として機能させるためには、業務の開始前および期間中に「期待値のすり合わせ」と、定期的な「レビュー機会の設計」が必要です。
業務を依頼する際には、曖昧な指示ではなく以下のような期待値を明確に伝えましょう。
- 何を、いつまでに、どの程度の品質でアウトプットしてほしいのか
- どのような役割を担ってほしいのか
- どこまでの裁量権を持つのか
上記の内容を可能な限り具体的に言語化し、書面などで双方合意することが不可欠です。依頼するタスクのゴールだけでなく、使用する技術スタックやコーディング規約、コミュニケーションルールなども含めるべきです。
業務開始後は、丸投げ状態にせず、定期的な進捗確認とフィードバックの機会を最低でも週に一度は設けましょう。困っていることや疑問点、改善提案などを気軽に話し合い、お互いの期待値がズレていないかを確認し、必要に応じて軌道修正を行います。
非同期環境での情報共有とオンボーディング
稼働時間が限られている副業エンジニアは、リモートでの作業が中心となるため、非同期コミュニケーションを前提とした情報共有の仕組みが必要です。
開発に必要なドキュメント(仕様書、設計書、環境構築手順、APIドキュメント、議事録など)は、常に最新の状態に保ち、NotionやGoogle Driveといったアクセスしやすい場所に一元管理しましょう。副業エンジニアが必要な情報を自分のタイミングで確認できるため、質問の回数を削減できます。
タスク管理にはGitHub ProjectsやAsanaといったツールを活用し、各タスクの担当者、進捗状況、期限などを可視化しましょう。非同期でもプロジェクト全体の状況を把握しやすくなります。
SlackやMicrosoft Teamsなどを活用したコミュニケーションチャネルでは、以下の基本的な運用ルールを明確にしましょう。
- チャンネルの命名規則
- スレッドの活用ルール
- メンションの付け方
ルールが徹底されれば情報が整理され、必要な情報を見つけやすい状態を維持できます。
オンボーディング時には、ツールやルール、ドキュメントなどを丁寧に説明します。最初の数週間は意識してコミュニケーションを取り、疑問点を早期に解消できるようサポートしましょう。
副業エンジニアの求人なら社内SE転職ナビ

副業エンジニアの採用は、企業の多様なニーズに柔軟に対応できる一方で、適切な運用設計が重要です。社内SE転職ナビでは、幅広い企業様の採用ニーズに応えるため、公開求人数6,000件以上(2025年4月時点)を取り扱い、そのうち非公開求人率は64%に上ります。これにより、他では見つけにくい優秀な副業エンジニアとのマッチングも可能です。また、紹介平均25.6社の実績を活かし、多様な候補者から最適な人材を見つけるサポートをいたします。
副業エンジニア採用をご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。企業様の採用成功に向けて、一歩踏み出すお手伝いをいたします。
まとめ|副業人材は“人手不足の代替”ではなく“役割特化型の戦力”
副業エンジニアの活用は、深刻化するエンジニア不足に対する有効な一手となります。しかし、副業エンジニアの活用を成功させるには、適切な理解と運用設計が重要です。単なる「人手不足を補うための代替労働力」とは考えず、特定のスキルや経験を活かして、限定された役割において高い専門性を発揮する「役割特化型の戦力」として捉えましょう。
本記事では、副業エンジニアを採用する前に気を付けるべきポイントや、活用できる企業の特徴を紹介しました。採用時に生じやすいすれ違いや、適切に機能させるための運用設計についても解説しているので、副業エンジニアの採用を検討している方は参考にしてください。
副業エンジニアは企業にとって、コスト効率よく高い専門性を獲得できる、信頼できる貴重な戦力となり得ます。本記事の内容を参考にして貴社の環境を見直し、副業エンジニアと共に事業を成長させていきましょう。