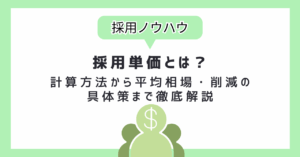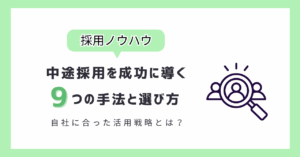エンジニア採用における競争が激化する中、従来の求人広告だけでは企業の魅力を伝えきれず、候補者との接点構築に課題を感じている採用担当者もいるでしょう。採用イベントは、母集団形成から動機づけ、選考化までを一貫して設計できるおすすめの手法です。
本記事では、エンジニア採用に特化したイベントの種類ごとの特徴と使い分け、一貫設計によって成果を最大化するための具体的な実践法を解説します。イベントを活用した採用を検討されている方は最後までご覧ください。

エンジニア採用、こんな課題ありませんか?
- 技術力だけでなく、事業理解も必要だけど、見極めが難しい
- 社内システムを支える柔軟な対応力を持つ人材がなかなかいない
- 企業文化にフィットするエンジニアを採用したい
「社内SE転職ナビ」なら、技術×カルチャーの両面からマッチするエンジニアをご紹介できます。エージェントによる丁寧なヒアリングに加え、企業から直接アプローチできるダイレクトリクルーティング機能もご利用可能。貴社の採用スタイルに合わせて、最適な候補者との出会いをサポートします。
エンジニア採用でなぜイベント活用が注目されているのか
近年、エンジニア採用市場は売り手市場が続いており、企業間の競争はますます激化しています。多くの企業が同様の求人情報を発信するなかで、候補者は待遇や業務内容だけでなく、その企業で働くことの「リアルな魅力」を求めています。
特にエンジニアが求める要素の例は以下のとおりです。
- 自身の技術的な成長機会
- チームの文化や開発スタイル
- 企業のビジョンへの共感
求人票の文面だけでは伝えきれない上記の情報を届けるため、採用イベントへの注目が高まっているのです。候補者との直接的な接点が築けるため、双方向のコミュニケーションを通じて企業の魅力を深く伝えられます。
採用イベントは、単なる情報提供の場に留まりません。候補者の疑問を解消し、企業への興味関心を高め、最終的には応募へとつなげるための重要な役割を担います。企業と候補者の相互理解を深める貴重な機会になっています。
採用イベントの種類とそれぞれの特徴
エンジニア採用で活用されるイベントは、目的やターゲット、企業のリソース状況によってさまざまです。自社で企画・運営するクローズドなイベントから、大規模なフェアやオンラインイベントまで、選択肢は多岐にわたります。
本章では、イベントを以下の3つのカテゴリーに分け、特徴やメリット・デメリットなどについて、具体的なイベント施策例と共に比較・解説します。
- 自社開催イベント(LT会・Meetup・技術説明会など)
- 外部連携イベント(逆求人フェア・合同説明会など)
- オンラインイベント(ウェビナー・バーチャル説明会など)
順番に詳しく見ていきましょう。
自社開催イベント(LT会・Meetup・技術説明会など)
自社開催イベントは、企業が主体となって企画・運営する採用イベントです。自社の技術力や開発文化、働く環境、社員の雰囲気を直接的に深く伝えられる点がメリットです。企業のブランディング強化や、カルチャーフィットを重視する候補者への強力な訴求が期待できます。
具体的な自社開催イベントは以下のとおりです。
| イベント施策 | 母集団形成 | 動機づけ | 選考化 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 技術LT会・Meetup | ◎ | ◎ | ◯ | ・技術志向の高いエンジニア層を広く集めやすい・社員の登壇により技術レベルや社風のアピールが可能・潜在的な候補者との初期接点を築きやすい・特定の技術領域に強みを持つ企業向け |
| オフィスツアー付き会社説明会 | △ | ◎ | ◎ | ・候補者が入社後の働くイメージを具体的に持ちやすい・働く環境の良さを直接アピール可能・一度に対応できる人数に限りがある・企業文化やチームの雰囲気を重視する企業向け |
| カジュアル面談型イベント | △ | ◯ | ◎ | ・リラックスした雰囲気での面談を複数実施・候補者の本音や疑問を引き出しやすく、深いレベルでの相互理解が可能・一度に多くの候補者と深く関わるのは難しい・選考前に相互理解を深め、ミスマッチを減らしたい企業向け |
| 社員との座談会 | ◯ | ◎ | △ | ・複数の社員と複数の候補者が気軽に話し合うイベント・企業への親近感や共感を醸成しやすい・コミュニケーション能力やファシリテーションスキルが成功の鍵・社員の魅力やチームワークの良さを強みとしている企業向け |
| インターン発表会・開発イベント | ◯ | ◎ | ◯ | ・技術的な課題解決やプロダクト開発プロセスを体験・発表・優秀な学生や若手エンジニアの早期発見・獲得につながりやすい・企画・運営に大きな工数とリソースが必要・新卒採用や若手エンジニアのポテンシャル採用に力を入れている企業向け |
| ハッカソン/ワークショップ | ◎ | ◯ | △ | ・短期間でプロトタイプの開発などを行う競技形式のイベント・技術志向が非常に高いエンジニアにリーチ可能・イベント後の丁寧なフォローや魅力的なキャリアパスの提示が重要・チャレンジ精神旺盛なエンジニアを集めたい企業向け |
| オンライン技術ウェビナー | ◎ | △ | △ | ・インターネットを通じて、セミナーや講演をライブ配信する形式・国内外問わず広範囲のエンジニアにリーチ可能・深い動機づけや企業文化の伝達には工夫が必要・全国・海外など、広範囲のエンジニアにリーチしたい企業向け |
自社開催イベントは、伝えたいメッセージやターゲット層が明確で、かつ運営リソースを確保できる企業にとっては非常に有効な手段です。イベントの形式だけでなく、「何を目的に、誰に、何を伝えたいのか」を明確にし、それに応じた内容と運営体制を設計しましょう。
イベントを一過性のものとせず、母集団形成、動機づけ、そして選考化という一連の採用プロセスの中で、どのフェーズに最も効果を発揮する施策なのかを意識して活用することが求められます。
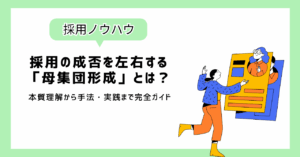
外部連携イベント(逆求人フェア・合同説明会など)
外部連携イベントは、複数の企業が合同で開催する説明会や、人材紹介会社などが主催するマッチングイベント、技術カンファレンスへの出展といった形態を指します。自社単独でイベントを企画・運営するよりも、集客にかかる工数や費用を抑えつつ、一定規模の母集団に効率的にアプローチできる点が大きなメリットです。
採用ブランドがまだ確立されていない企業や、採用リソースが限られている企業にとっては、多くの候補者と接点を持つための有効な手段となり得ます。主な外部連携イベントは以下のとおりです。
| イベント施策 | 母集団形成 | 動機づけ | 選考化 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 逆求人イベント | ◎ | △ | △ | ・企業がブースを構え、興味を持った候補者が訪問する形式・自社の知名度に頼らず、エンジニアに直接アプローチ可能・その場での深い動機づけは難しく、フォローアップの仕組みが重要・採用ブランドがまだ確立されていない企業向け |
| 技術カンファレンス出展 | ◎ | ◯ | △ | ・最新技術の情報交換やネットワーキングが主目的の場・技術感度の高い、専門的なスキルを持つエンジニア層に直接リーチ可能・個別アプローチにつなげる導線設計が重要・特定の技術領域での高い専門性や先進性をアピールしたい企業向け |
| 合同会社説明会 | ◎ | △ | △ | ・複数の企業が一堂に会し、自社の説明を行うイベント・短期間で多くの候補者と接点が持てる・自社への興味を深めるかの補完設計が重要・多くの候補者にリーチし、母集団の母数を増やしたい企業向け |
| スカウト型マッチングイベント | ◯ | ◯ | ◯ | ・企業と候補者のマッチングを行い、個別の面談機会を提供するイベント・「母集団形成」と「初期の動機づけ」をある程度両立可能・さらに深い関係構築につなげるフォローアップが重要・特定のスキルや経験を持つエンジニアを効率的に見つけたい企業向け |
| 人材エージェント主催イベント | ◯ | △ | ◎ | ・人材紹介会社主催のマッチングイベント・転職意欲の高い候補者と出会える可能性が高い・情報提供やコミュニケーション設計に工夫が必要・自社だけではアプローチしきれない層の候補者と接点を持ちたい企業向け |
| エンジニア就職フェア | ◎ | △ | △ | ・エンジニア志望者を対象とした大規模なイベント・エンジニア候補と一度に多数接触できるため、母集団形成に効果的・ブースでの短い接触時間で次のアクションにつなげる導線設計が重要・新卒採用や若手ポテンシャル採用を積極的に行っている企業向け |
外部連携イベントは集客面でのメリットが大きい反面、候補者への深い動機づけや、その後の応募へと繋げるための導線設計は、各企業の工夫と努力に大きく左右されます。「参加すれば何とかなる」という受け身の姿勢では成果につながりません。
イベントの特性を理解した上で、「このイベントでは母集団形成に注力し、その後の個別フォローで動機づけと選考化を進める」といった戦略的な活用が求められます。自社の採用課題と照らし合わせ、どのイベントが最も効果的かを見極め、最大限の成果を得るための準備と計画が求められます。
オンラインイベント(ウェビナー・バーチャル説明会など)
オンラインイベントは、インターネットを活用して開催される採用イベントの総称です。地理的な制約を受けずに広範囲の候補者にアプローチできる点と、会場費や移動費といったコストを大幅に削減できる点がメリットです。
地方在住の優秀なエンジニアや、現職が忙しくオフラインイベントへの参加が難しい層へもリーチしやすくなります。主なオンラインイベントは以下のとおりです。
| イベント施策 | 母集団形成 | 動機づけ | 選考化 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| オンライン会社説明会 | ◎ | △ | △ | ・企業の概要や募集職などをオンラインで説明する形式・全国・海外から広範囲の候補者が参加可能・熱量を伝える工夫や個別フォローが重要・広範囲の候補者に情報を届けたい企業向け |
| 技術ウェビナー(ライブ配信) | ◯ | ◯ | △ | ・専門知識を持つ社員がオンラインで講演・解説する形式・質の高いエンジニア層にピンポイントでリーチ可能・Q&Aセッションなどによる導線設計が重要・特定の技術領域に強みや先進性を持つ企業向け |
| カジュアル面談会(Zoom) | △ | ◎ | ◎ | ・企業担当者と候補者がカジュアルに情報交換を行う形式・双方向のコミュニケーションが取りやすく、深い相互理解を促進・柔軟な対応と選考プロセス案内が重要・カルチャーフィットを重視する企業向け |
| Slack/Discordイベント | △ | ◯ | △ | ・専用チャンネルやサーバーを設けたコミュニティ型のイベント・参加のハードルが低く、候補者が自分のペースで情報収集可能・参加を促す仕掛けや情報提供、自然な誘導が必要・エンジニアコミュニティを形成し、長期的な関係を築きたい企業向け |
| 録画配信型コンテンツ | ◎ | △ | △ | ・候補者が好きな時に動画を視聴できるようにする形式・候補者の都合の良い時間に情報提供でき、リーチできる範囲が広い・視聴後のアクションへの導線設計が不可欠・時間的制約なく基本的な企業情報や技術情報を届けたい企業向け |
| オンライン逆求人イベント | ◯ | △ | ◯ | ・従来の逆求人イベントをオンライン上で実施する形式・全国の候補者にリーチでき、地方の優秀な人材発掘にもつながる・個別フォローなどによる動機形成の補完が極めて重要・特定のスキルを持つエンジニアを効率的に探したい企業向け |
オンラインイベントを成功させるためには、単にオフラインイベントを置き換えるだけでなく、特性を活かした体験設計と、デメリットを補うための工夫が不可欠です。特にオンラインイベントは、オフラインに比べて参加者の温度感や反応が掴みにくいというデメリットがあります。事前の念入りな準備と、オンラインでの高いコミュニケーション能力が鍵となります。
また、オンラインイベントは、目的に応じて組み合わせたり、オフラインとオンラインを併用したりすることで、より効果を高めることも可能です。各イベント形式の特性を理解し、最終的にどのような成果につなげたいのかを明確にして設しましょう。
イベントを成果につなげる設計
採用イベントは、単に開催すること自体が目的ではありません。イベントを通じて候補者との良好な関係を築き、最終的に自社への応募、そして採用へと繋げるためには、事前の「一貫設計」が重要です。ここでは以下の3つの視点で解説します。
- 誰を呼ぶか(ターゲット設計)
- 何を伝えるか(情報設計・登壇者選定)
- どこにどうつなげるか(応募導線の設計)
順番に見ていきましょう。
1.誰を呼ぶか(ターゲット設計)
誰に情報を届けたいのか、ターゲット像の明確化が設計の第一歩です。エンジニア一般ではなく、求めるスキルや経験年数、志向性などを定義したペルソナを設定します。
ターゲットが曖昧だと、イベント内容や集客メッセージがぼやけ、期待する層の参加や動機づけが難しくなります。ターゲットが明確になれば、響くテーマやコンテンツ、効果的な集客チャネルを選定でき、結果としてミスマッチの少ない採用へとつながるのです。この初期設計が、イベント全体の質と成果を大きく左右するため、入念な準備・計画が求められます。
2.何を伝えるか(情報設計・登壇者選定)
ターゲットが明確になれば、「何を伝えるか」を設計しましょう。単なる会社概要ではなく、ターゲットが求める「働くイメージ」につながる情報提供が必要です。技術スタックや開発プロセス、チーム文化、キャリアパス、働き方の柔軟性、企業のビジョンなど、多角的な情報が求められます。
現場エンジニアによる経験や思いのプレゼンは、候補者の共感を生むうえで重要です。登壇者には、技術的知見に加え、プレゼン能力や自社の魅力を熱意をもって語れる人物を選びましょう。伝える情報と伝え手の選定が、候補者の心を動かし、イベントの成否を分ける重要な要素となるのです。
3.どこにどうつなげるか(応募導線の設計)
イベントの最終ゴールは、参加者の中から自社に合う人材を見つけ、応募や選考へつなげることです。「良い話が聞けた」で終わらせないために、参加者が自然に次のアクションへ進める応募導線を設計しましょう。
たとえば、イベント後のアンケートで個別面談希望者を募り、温度感に応じてスカウトメールを送る、サンクスメールに関連求人や限定選考ルートを案内するなどの方法があります。
重要なのは、無理強いのないスムーズな誘導です。イベント当日だけでなく、その後の継続的なコミュニケーションを通じて関心を高める視点も、応募率の向上には欠かせません。
イベント運営で成果を上げる実践ポイント
入念な設計に基づいて企画された採用イベントも、当日の運営やその後のフォローアップが適切に行われなければ、期待した成果は得られません。本章では、イベント運営で実際に成果を上げるための具体的な実践ポイントを、以下の3つのフェーズに分けて解説します。
- 集客チャネルと訴求内容の設計
- 当日の運営工夫(参加者の満足度を高める設計)
- フォロー施策(ナーチャリングと選考化)
順番にまとめるので最後までご覧ください。
集客チャネルと訴求内容の設計
イベントの成果は、「誰に、どれだけ来てもらえるか」という集客に左右されます。ターゲットエンジニア層に効果的にリーチするには、適切なチャネル選定と魅力的な訴求内容が不可欠です。connpassやWantedly、SNS、自社サイトなど、ターゲットの特性やイベント内容に合わせて使い分けましょう。
告知文では、単なる概要ではなく、「参加メリット・共感ワード・登壇者の魅力」を明確に打ち出してください。キャッチーなタイトルや画像・動画の活用、早期申し込み特典なども有効です。集客チャネルと訴求メッセージを戦略的に設計して、質の高い母集団形成を目指しましょう。
当日の運営工夫(参加者の満足度を高める設計)
当日のイベント運営は、参加者の満足度と企業イメージにつながります。スムーズな進行はもちろん、「参加して良かった」と感じる体験価値の向上が重要です。オンラインならアイスブレイクやチャット活用、オフラインなら会場の雰囲気作りや丁寧な対応を心がけましょう。Q&Aセッションでは事前に質問を準備し、議論を活性化させます。
登壇者の話し方や資料構成も満足度を左右する要素です。参加者が積極的に関わり、かつ快適に過ごせるような細やかな配慮と工夫が「その場の体験価値」の向上につながり、イベントを成功へと導くのです。
フォロー施策(ナーチャリングと選考化)
イベント後のフォローアップは、参加者を応募や採用につなげる最重要プロセスです。速やかにアンケートを実施し、参加者の温度感を把握しましょう。
「高温層」には早期の面談打診、「中温層」には関連情報提供や次回イベント案内、「低温層」には定期的な情報発信といったように、リードを分類し最適なアプローチを行います。
サンクスメールには次のアクションを促す情報を記載するなど、丁寧なナーチャリングが成果を最大化する鍵となります。
イベント活用でよくある失敗とその回避策
イベントを開催したものの、「やってみたものの効果がなかった」という声も少なくありません。本章では陥りがちな代表的な失敗例を4つ挙げ、原因と具体的な回避策、そして改善のためのポイントを解説します。
- 集客に注力しすぎて中身が薄い
- 「話して満足」で終わり、応募につながらない
- スライドが会社説明に終始し、技術や現場の魅力が伝わらない
- フォロー体制がなく、参加者を放置してしまう
次回イベントを成功させるための参考にしてください。
集客に注力しすぎて中身が薄い
参加者数を追うあまり、イベントの中身が疎かになるケースが見られます。「誰に何を伝え、どう動機づけるか」という本来の目的が不明確であるため、期待した情報が得られず企業理解が浅くなってしまいます。
改善するためには、具体的な目的とゴールの設定が重要です。必要なコンテンツは何か、ターゲット層に響く情報とは何かを考え抜き、内容から逆算して集客目標や方法を設計しましょう。
「話して満足」で終わり、応募につながらない
イベント開催自体が目的化し、その後のフォローや応募への導線設計が不十分な事例です。「良い話が聞けた」で終わってしまい、具体的なアクションにつながりません。
改善ポイントは、イベント後に参加者にどうなってほしいか、どんな行動を促したいかを明確にした導線設計です。アンケートで個別面談希望者を募ったり、登壇後にカジュアル面談へ誘導したり、サンクスメールに関連求人や問い合わせ窓口を記載したりするなどの工夫が有効です。
スライドが会社説明に終始し、技術や現場の魅力が伝わらない
失敗事例のひとつに、会社概要や福利厚生といった一般的な説明に終始し、エンジニアが求める「技術的やりがい」や「開発現場のリアルな雰囲気」が伝わらないケースがあります。具体的な働くイメージを求めている候補者にとって、事実の羅列は入社意欲を高める要素にはなりません。
スライド内容を「候補者目線」で見直しましょう。「誰がどんな想いでどんな技術に取り組んでいるのか」という情報を、現場目線・ストーリー性を意識して提供しましょう。現場エンジニアが自身の言葉で開発の面白さやチームの雰囲気を語れば、どんな綺麗なスライドよりも説得力を持ちます。
フォロー体制がなく、参加者を放置してしまう
せっかくイベントで接点を持っても、その後のフォローがなければ貴重なつながりを失ってしまいます。少なからず自社に興味を持った参加者も、放置されれば他社へ流れてしまうのです。
イベント後のフォローアップをシステムとして確立し、継続的なコミュニケーション(ナーチャリング)を行う体制を整えましょう。アンケートで温度感を把握し、それに応じてアプローチを変えます。高温層には速やかに面談案内、中温・低温層には定期的な情報提供など、関係性を維持し、適切なタイミングで次のアクションを促すことが重要です。
社内SEの求人なら社内SE転職ナビ

エンジニア採用においては、単に求人を出すだけでなく、ターゲットに響く魅力的な情報発信と戦略的なプロセス設計が不可欠です。
社内SE転職ナビでは、非公開求人が全体の64%を占めており、多様な案件から企業様のニーズに合った人材をご紹介しています。公開求人数は6,000件以上(2025年4月時点)と豊富な選択肢があり、平均して25.6社の企業様にご利用いただく信頼の実績があります。
エンジニア採用の課題解決に向けて、ぜひ一度ご相談ください。最適なイベント活用や採用戦略のご提案を通じて、御社の採用成功をお手伝いいたします。
まとめ
採用イベントは、単に多くの候補者を集めるための集客施策として捉えるだけでは、その真価を発揮できません。エンジニア採用におけるイベント活用の本質は、母集団形成から始まり、参加者の動機づけ、そして最終的な選考化へと繋がる一連のプロセスを戦略的に設計し、実行することにあります。
本記事の内容を参考にして、イベントの種類ごとの特性を理解し、自社の採用課題やターゲットに応じて最適な形式を選択してください。技術力や社風をリアルに体感してもらえる貴重な接点として、採用プロセス全体の中にイベントを効果的に組み込み、貴社の採用を成功に導いてください。