データガバナンスのルールの形骸化は多くの組織で発生する問題です。特に「データは資産である」という認識が広がり、ガバナンス施策が導入されても、その本質的な価値が理解されないまま形式的な取り組みに終わることが少なくありません。
本記事は、データガバナンスの形骸化に課題を感じているデータエンジニア・IT部門の方向けに、その実態と改善策を解説します。自社のガバナンスを見直すヒントを得たい方は、ぜひ参考にしてください。
本記事では、基本概念からデータモデル設計、テーブル設計まで、両者の実践的な違いを現役データエンジニアの視点で解説します。また、社内SEやエンジニアが効果的なデータ環境を構築・運用するためのポイントについても紹介します。
この記事は以下の方におすすめです!
- データ活用を推進したいが、現場がついてこないと感じている人
- データエンジニアやデータ基盤担当者
- これからデータガバナンスを導入・設計しようとしている担当者
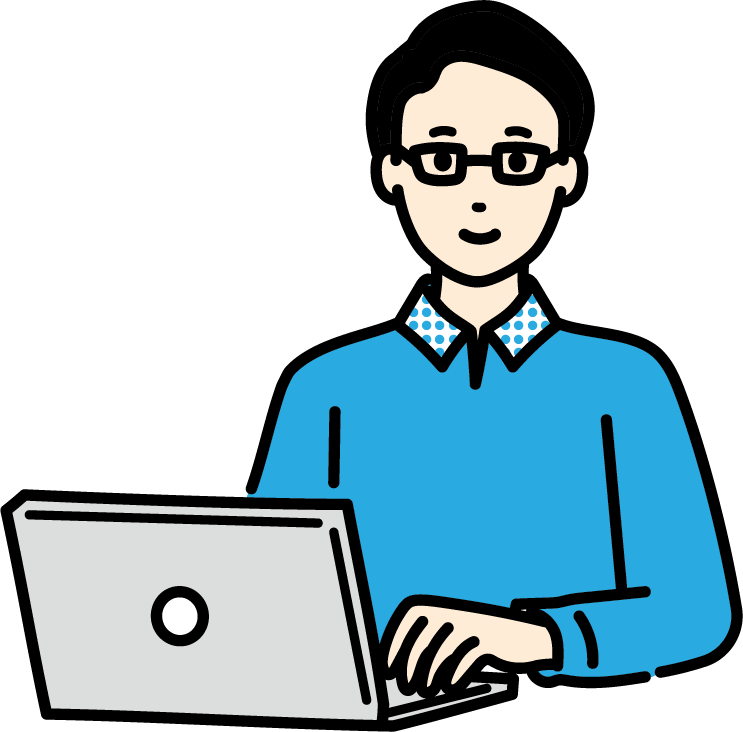
ライター:R.Kotomo
プロフィール:見習い中のデータエンジニアとして、PythonやSQL、クラウドを日々の業務で扱っています。ITエンジニアが執筆した技術記事から多くを学び、自身の経験も誰かの役に立てたいと考えライターを始めました。データ人材やデータ業界に関する情報を、初心者にもわかりやすくお伝えすることを目指しています。実務に基づいた具体的な内容や、現場で役立つノウハウを共有することで、読者のみなさまに気づきを与えられたらと思います。

ナレッジコラムシリーズ
データガバナンスが形骸化する3つの原因
データガバナンスは「データを資産として適切に管理し、活用を促進する」ために設けられる重要な仕組みです。しかし、実際には導入されたガバナンスルールが定着せず、名ばかりの存在となってしまう、いわゆる形骸化の問題が多くの現場で発生しています。
特に、データ活用の必要性が叫ばれる一方で、形式的なルールだけが先行し、現場で運用されない・されていても意味をなしていないという状況に陥るケースが目立ちます。なぜそのようなことが起きるのでしょうか?
ここでは、データガバナンスが形骸化する代表的な原因を、現場の視点から3つのカテゴリに分けて解説します。
1. 現場になじまないデータガバナンスルールが形骸化の原因に
現場に適合しないデータガバナンスルールは、形骸化の主要な原因となります。どれだけ理論的に優れたガバナンスフレームワークであっても、実際の作業環境や既存のワークフローと調和しなければ、やがて無視されるか形だけの遵守に終わるでしょう。
形骸化の原因としては多くの場合、理想と現実のギャップを考慮せずにガバナンスルールが設計されるためです。トップダウンで実施されるベストプラクティスや国際標準は、理論的には優れていても、組織の実情、既存システムの制約、チームの習熟度などを考慮していないことが少なくありません。
活用されないデータ定義書
多くの現場で、データ定義書が十分に活用されず形骸化しているのは珍しくありません。その背景には、実際のワークフローと定義書の運用方針との乖離があります。理由としては、定義書の設計と運用プロセスに現実的な考慮が欠けているからです。
- 完璧さを追求するあまり、過度に複雑な項目設計がなされ、更新手順が煩雑になり、結果として誰も積極的に活用しなくなる
- データ定義書やドキュメントの更新が運用の工数として考慮されていない
実際にシステムの運用フェーズでエンジニアの入れ替わりが頻繁に生じたため、データ定義書が更新されず、特定のエンジニアのみがデータ定義を把握しているような属人性の強いチームを経験したことがあります。
上記の例のように活用されないデータ定義書は、データ利活用推進やシステム運用の弊害となります。
「誰が管理するか」が曖昧なまま、属人化するルール
データガバナンスの責任所在が不明確なことは、ルールの属人化を引き起こす原因となります。明確な責任体制がなければ、誰もガバナンスの実効性に責任を持たず、結果的に組織全体で標準化された手順やガイドラインが徹底されにくくなります。
データガバナンスは本来、部門横断的な取り組みであり、IT部門だけでなく、ビジネス部門や経営層も含めた組織全体の課題です。しかし、ルールがなじまない多くのケースでは、「全社的な取り組み」という名目で具体的な責任者が明確にされないまま導入されることが少なくありません。
データガバナンスの責任を明確にするためには、専任のデータスチュワードを任命し、データ定義やデータ品質、メタデータ整備の実務担当を担ってもらうことがひとつの解決策になると考えられます。
2. 納期優先・属人運用でルールが形骸化
納期優先、特定の担当者に依存した属人的な運用は、データガバナンスルールを形骸化させる大きな要因です。どれほど優れたルールであっても、日々のビジネス要求に応えることが優先される状況では、後回しにされがちです。
開発スピードが優先され、定義やドキュメントは後回し
開発スピードとドキュメンテーションのバランスが崩れると、ガバナンスルールは形骸化します。特にアジャイル開発環境では、「動くソフトウェア」の価値が強調される一方で、適切なドキュメント作成の重要性が軽視されがちです。
なぜなら、動くソフトウェアやデプロイされた機能は目に見える成果として評価されますが、適切なドキュメントやデータ品質の維持などは、その重要性にもかかわらず、評価の対象となりにくいことが少なくありません。
実際に納期優先で、ドキュメントの運用や管理が煩雑になり、特定のエンジニアのみがデータ定義や背景を把握している現場を筆者は経験したことがあります。
ルールより「わかってる人に聞いたほうが早い」文化が定着する
現場では「ルールを読むより、わかっている人に聞いたほうが早い」とされる文化が定着してしまうことがあります。「わかっている人に聞く」文化は、短期的には効率的に見えるものの、長期的にはガバナンスの形骸化やナレッジの属人化を招くリスクがあります。
問題解決の場面では、公式ドキュメントを探して読み解くよりも、詳しい人に直接尋ねる方が認知的負荷が低く、すぐに解決できるためです。実際、多くの人が「詳しい人に聞いた方が早かった」という経験を持っているのではないでしょうか。
私が関わったあるチームでも、データカタログやER図が整備されておらず、ベテランメンバーの記憶に業務の多くが依存していました。その結果、ドキュメント整備や知識の共有が後回しになり、属人性の強い状況になっていました。


3. 技術的負債とのせめぎ合い
データガバナンスの欠如による技術的負債の蓄積は、時間の経過とともに組織のデータ利活用を著しく低下させます。開発サイクルの中で、「とりあえず動けばいい」という判断が積み重なり、その場しのぎの解決策が根付いてしまうのです。
また、多くの組織では技術的負債の定量化が難しく、経営層にその深刻さを伝えることができないという問題もあります。
命名規則やスキーマが統一されず、ガバナンスが機能しない
命名規則やスキーマの不統一は、データ活用の大きな障壁となります。一貫性のないデータ構造は、システム連携を複雑化し、分析の正確性を損ない、データ品質を低下させます。
こうした問題が発生する主な要因は、短期的な機能実装が優先され、長期的な一貫性の維持が軽視されがちなことにあります。また、異なるチームや時期に開発されたシステムが連携する際、標準が明確でなかったり、強制力がなかったりすると、自然と不統一が生じます。
実際に、納期を優先して構築されたシステムでは、なぜそのようなデータ構造やデータ定義になっているのかが把握されておらず、結果として一貫性のないデータ構造となり、プロジェクトが技術的負債に直面せざるを得ない状況を目にしてきました。
繰り返しになりますが、命名規則やスキーマの統一は、データの信頼性と再利用性を確保するうえで、データガバナンスの土台となる重要な要素です。
負債を直す余力がなく、「仕方ない」が放置につながる
技術的負債を認識していても解消する余力がない状況は、多くの組織が直面する課題です。「今は直せない」という判断が繰り返されると、負債はさらに蓄積し、やがては手がつけられない状態に陥ることもあります。
この課題が生じる理由は、技術的負債の返済に対する投資の難しさにあります。負債の返済は直接的な収益向上につながりにくく、その効果も目に見えにくいため、リソース配分の際に優先度が下がりがちです。
技術的負債に対処するためには、まず負債の定量化と優先順位付けが重要です。負債を明確に把握することで返済の進捗状況を管理し、返済すべき負債の優先順位を決め、効率的に返済を進めていきます。また、新機能開発と負債返済のバランスを取るため、開発時間の20%を技術的負債の返済に充てるなどのルールを設けることも効果的です。


エンジニア視点での立て直し方
形骸化したデータガバナンスを改善するためには、エンジニアリングの視点から実用的なアプローチが必要です。特に、自動化、コード化、可視化という3つの要素を組み合わせることで、持続可能なガバナンス体制を構築できます。本章では下記の3項目について説明いたします。
- データガバナンスのIaCアプローチ
- CI/CDパイプラインへのガバナンスルール組み込み
- メタデータ管理とデータカタログの活用
データガバナンスのIaCアプローチ
Infrastructure as Code(IaC)をデータガバナンスに適用することで、自動化と一貫性を実現できます。またGitなどでバージョン管理することで変更履歴が残るため、トレーサビリティが向上し、形骸化を防ぐことが可能になります。
なぜならIaCでは、ルール自体がコードとして表現され、組織で作成したガバナンスが自動的に適用されるため、乖離が生じにくくなるからです。
下記にIaCを用いたデータガバナンスの取り組み例を示しました。
| 取り組み内容 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| スキーマ定義のコード化 | データベーススキーマをコードとして管理し、バージョン管理システムで変更履歴を追跡する | GCSからBigQueryへのロード処理をTerraformでスキーマ定義し、変更履歴を確認する |
| データ検証ルールの自動適用 | データの品質ルールをコード化し、定期実行できる | dbtの検証ルールとTerraformを用いてJob実行を定義する |
| 定義ファイルの自動生成 | 実システムからデータ定義書を自動生成し、常に最新の状態を維持する | Cloud Data CatalogがBigQueryと連携し、メタデータを自動生成する |
IaCを用いたアプローチにより、ルールと実装の乖離を防ぎ、ガバナンスをエンジニアの日常ワークフローに組み込むことができます。また、組織全体のデータ品質・セキュリティ・コンプライアンス水準を継続的に高く維持できるようになります。
CI/CDパイプラインへのガバナンスルール組み込み
継続的インテグレーション/継続的デリバリー(CI/CD)パイプラインにガバナンスチェックを組み込むことで、ガバナンスの遵守を自動化しつつ、チームの開発体験を向上させることができます。
理由としては、ガバナンスの遵守を開発者に依存させるのではなく、自動化されたプロセスの一部にすることで、一貫性と効率性を両立できるからです。また、違反が早期に検出されるため、修正コストも低く抑えられます。
| スキーマ変更の自動検証 | データベーススキーマの変更が命名規則やデータ型の標準に準拠しているかをCIプロセスでチェックする |
| データ品質テストの自動化 | データロード後に品質テストを実行し、不整合があればデプロイを止める |
| メタデータ更新の強制 | コードの変更に伴うメタデータの更新が行われていない場合、ビルドを失敗させる |
| ガバナンス違反のレポート自動化 | ガバナンス違反を自動検出し、定期的なレポートを生成する |
実際にはdbtなどのDataOpsツールとGitHub Actionsなどを組み合わせてCI/CDを構築することで、データの品質と信頼性を自動的に維持しつつ、チーム全体の開発体験を向上させられます。
メタデータ管理とデータカタログの活用
メタデータ管理とデータカタログの導入は、形骸化したデータガバナンスを立て直す最も効果的な手段の一つです。この取り組みにより、「わかる人に聞く」文化から「自分で調べられる」文化への転換が可能になります。
理由は、データの民主化と透明性の確保にあります。メタデータを一元管理し、カタログ化することで、データの探索可能性と信頼性を高めることができます。以下に代表的な機能を記載しました。
| データカタログ | 誰でも簡単にデータの定義や品質情報を検索できるプラットフォームを提供 |
| 自動メタデータ収集 | データソースからメタデータを自動的に収集し、メンテナンスの負荷を軽減 |
| データリネージ | データソースからデータの出力先までの流れを可視化し、影響分析を容易にする |
| コラボレーション機能 | データに関する質問や議論をカタログ上で行い、ナレッジの共有を促進 |
メタデータ管理とデータカタログの活用を行い、「わかる人に聞く」文化から「自分で調べられる」文化への転換は、データガバナンスの持続可能性を高める重要な一歩と言えるでしょう。
社内SEの求人なら社内SE転職ナビ


データ活用が重要視される今、ガバナンスが現場で形骸化してしまう課題に直面している方も多いのではないでしょうか。
社内SE転職ナビでは、公開求人5,200件以上、非公開求人10,000件以上を保有し、ガバナンス構築や全社的なデータ整備に関わるポジションも多数掲載しています。単なる保守運用にとどまらず、現場と経営をつなぐ「仕組みづくり」に挑戦したい方に最適です。
「現場に根付くデータガバナンスを実現したい」そんな想いを形にできる職場を、私たちと一緒に見つけてみませんか。
まとめ
データガバナンスルールの形骸化は、組織のデータ利活用の障害となります。本記事で見てきたように、この問題は現場との乖離、納期優先の文化、技術的負債の蓄積など複合的な要因から生じますが、エンジニアリングの観点からの実践的なアプローチで解決できます。
データガバナンスは単なる規制やルールではなく、データの価値を最大化するための基盤です。エンジニアの視点から、実用的かつ持続可能なガバナンスの仕組みを構築することが、データ駆動型組織の確立に必要となるでしょう。


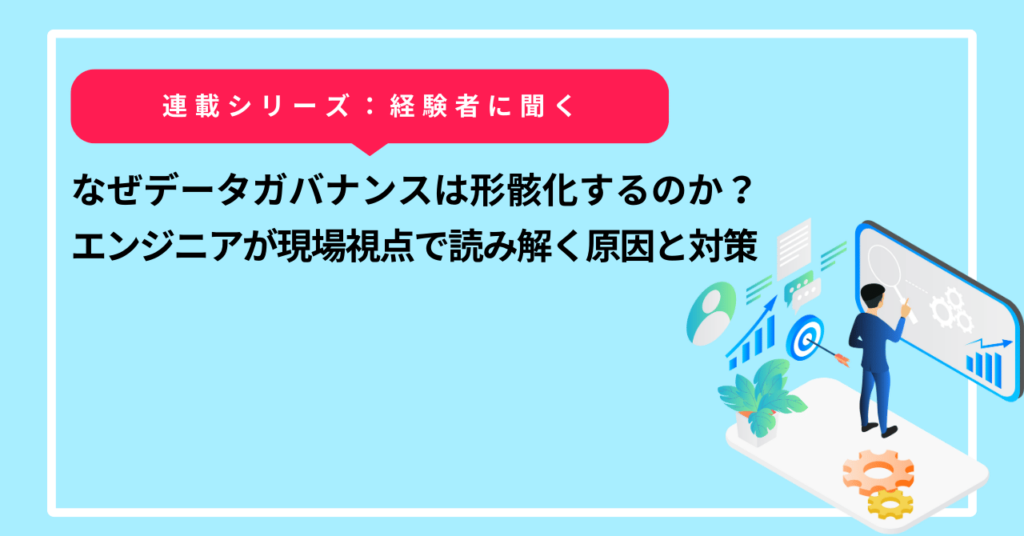

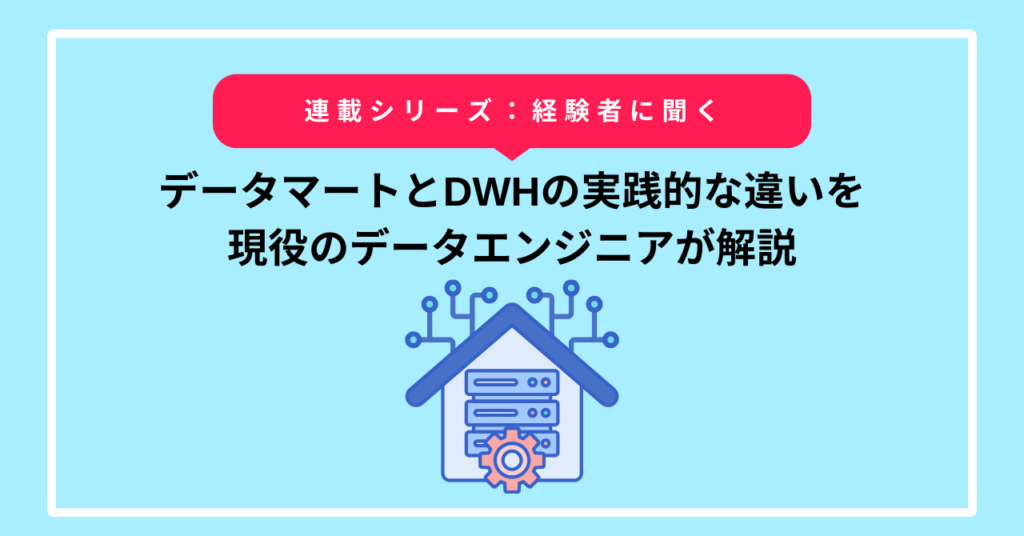



-13-1-300x157.png)







