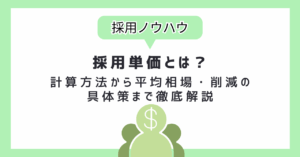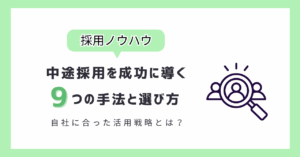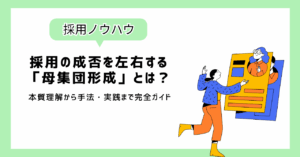近年、IT市場の拡大に伴いエンジニア人材の需要は高まる一方です。同時にエンジニアの離職率の高さも大きな課題となっています。ひとたび優秀なエンジニアが流出すると、プロジェクトの遅延やチームの生産性低下など、企業にとって大きな損失が生じかねません。
本記事では、エンジニアが離職する主な理由を分析し、人材の定着に効果的な施策について詳しく解説します。エンジニアの離職にお困りの方はぜひ最後までご覧ください。

エンジニア採用、こんな課題ありませんか?
- 技術力だけでなく、事業理解も必要だけど、見極めが難しい
- 社内システムを支える柔軟な対応力を持つ人材がなかなかいない
- 企業文化にフィットするエンジニアを採用したい
「社内SE転職ナビ」なら、技術×カルチャーの両面からマッチするエンジニアをご紹介できます。エージェントによる丁寧なヒアリングに加え、企業から直接アプローチできるダイレクトリクルーティング機能もご利用可能。貴社の採用スタイルに合わせて、最適な候補者との出会いをサポートします。
エンジニアの離職率
厚生労働省が発表した「令和5年雇用動向調査結果の概況」によると、情報通信業の離職率は12.8%程度でした。比較的離職率の高いサービス業を除くと、情報通信業の離職率は高く、製造業(9.7%)や建設業(10.1%)を上回っています。この数字はIT業界全体の平均であるため、企業によって状況は大きく異なります。
IT業界は技術の進化が非常に早いため、常に最新のスキルを追いかけなければなりません。そのため、スキルアップの機会や労働環境の良し悪しは、エンジニアが転職を決意する大きな要因となっています。人材の流動性が高いIT業界で優秀なエンジニアの離職を防ぐには、企業側がエンジニアの定着率を高める施策を積極的に検討する必要があるのです。
エンジニアが離職する理由
エンジニアが会社を離れる理由はさまざまです。企業が離職を防ぎ、エンジニアの定着を図るには、まずどんな理由で離職が起きているのかを把握することが重要です。
本章では、エンジニアが離職を決断する主な背景について取り上げていきます。ぜひ、自社の状況と照らし合わせながらご覧ください。
成長機会の不足
エンジニアは常に最新技術を学び続けなければなりません。社内で十分な学習機会が提供されなければ、エンジニアはスキルアップが難しく将来的な市場価値の低下につながると考えるでしょう。
業務がルーチン化していると、新しい知識や技術を習得する機会が限られます。経験豊富なエンジニアでも、同じ業務内容を継続するだけでは技術のキャッチアップが困難です。成長意欲の高いエンジニアであればあるほど、成長機会を業務時間外に求めるようになります。
ただし、ワークライフバランスが重視される現代では、業務外はプライベートを重視したいという方も増えています。成長の機会もプライベートも重視するエンジニアは、希望が満たされる環境を求めて転職するのです。
技術スタックが古い
最新技術を活用できない環境では、エンジニアは市場価値の低下を懸念します。IT業界では技術の進化が早いため、古い技術しか使えない環境はキャリア形成において大きなリスクとなるのです。
レガシーシステムの維持だけを求められる職場では、「この先も古い技術だけを使い続けることになるのでは」という不安から、エンジニアはキャリアの成長を阻害されていると感じるかもしれません。
昨今では、企業の技術スタックをまとめて閲覧できるサービスも登場しており、企業の技術環境を重視するエンジニアが転職先選びの際に参考にしています。最新技術にキャッチアップできる環境を求めて転職を決意するケースが増えている証拠といってもいいでしょう。
専門性を活かせない
エンジニアが自身の得意分野や経験を活かせる業務に携われない状況が続くと、モチベーションが低下しかねません。とくに高度な専門性を持つエンジニアは、専門知識を発揮できない環境は大きなストレスでしかないのです。
新しい技術を活かせる場がない場合や、逆に幅広い業務ばかりを任される状況が続くと、キャリアパスに不安を感じる場合もあります。「このままでは専門性が深まらない」という焦りから、専門性を伸ばせる環境を求めて転職を考えるケースも少なくないのです。
現場のニーズに応じて業務をこなすエンジニアの場合、「何でも屋」になってしまい専門性が育たないという悩みにつながります。専門性を高めたいというエンジニアの意欲を満たせない環境では離職リスクは高まるのです。
評価制度が不透明
成果が正当に評価されない環境では、エンジニアの不満は蓄積しやすくなります。エンジニアの業務は、数値化しにくく定量的な評価が困難です。そのため、評価基準が不透明だと「どれだけ努力しても正当に評価されない」と感じてしまい、モチベーションの低下につながります。
昇進・昇給の基準が曖昧な企業では、努力が報われないという不満から、より透明性の高い評価制度を持つ企業への転職を考える傾向にあります。「給与などの金銭面への不満」も主な退職理由のひとつです。エンジニアの評価制度は、業績評価や能力評価だけでなく、意欲や姿勢、態度などを評価する情意評価も加えた3つをバランス良く機能させなければなりません。
長時間労働
開発の納期が厳しい企業では、長時間労働が常態化している場合もあります。厚生労働省の「IT業界の長時間労働対策について」によると、IT業界は全産業平均よりも年間で総実労働時間が約200時間長く、所定外労働時間は約70時間長いと指摘されています。
顧客からの継続的な受注を確保するために、タイトな納期や急な仕様変更にも対応しなければならない状況が、長時間労働の一因です。近年のIT需要の急増も業務量の増加に拍車をかけています。
働き方改革が進む現代では、ワークライフバランスを重視するエンジニアが増えており、過度な残業が続く職場環境では転職を考えざるを得ません。家庭があるエンジニアにとって、長時間労働は家族との時間を奪うため離職リスクをさらに高めるのです。
休日出勤が多い
サービスの運用・保守を担当するエンジニアは、システムトラブルや緊急対応のため、休日出勤を求められます。24時間365日稼働するサービスを支えるには、オンコール対応や緊急時の駆けつけ対応が必要となる業務もあります。
こうした状況が頻発し、十分な休息を取れない状況が続くと心身の負担は増える一方です。「プライベートな予定が立てられない」「常に緊急対応の可能性を考えなければならない」というストレスは、エンジニアの離職を促す要因となっています。
若手エンジニアの中には、入社前に休日対応の実態を十分理解していないケースもあり、想像以上の負担に直面して早期離職を選ぶ場合もあるでしょう。定着率を向上させたい企業にとって、休日対応の体制整備は急務なのです。
リモートワーク・フレックス制度がない
リモートワークやフレックス制度の有無は、エンジニアの働き方に大きな影響を与えます。特にコロナ禍以降、リモートワークの普及により働き方の選択肢が広がり、エンジニアはより自由な働き方を選べるようになりました。
オフィスに常駐せずとも遂行できる作業もあるため、出社が必須の環境は時間的・精神的負担に見られかねません。通勤時間の削減や業務集中時間の確保など、リモートワークのメリットが得られない環境では、柔軟な勤務体制を持つ企業への転職を考えるエンジニアが増えています。
多様な働き方ができる環境は、エンジニアの定着率向上のポイントです。リモートワークやフレックス制度を導入して、エンジニアの離職を防止しましょう。
エンジニアの離職を防ぐために──定着率を高める10の具体策
エンジニアが長く働き続けられる環境をつくるためには、「なぜ離職するのか」を理解し、それに応じた対策を講じることが不可欠です。ここでは、エンジニアの定着率向上に効果的な10の施策をご紹介します。
1. 技術研修の継続的な実施
社内外の技術研修を定期的に実施すれば、エンジニアに最新技術の学習機会を提供できます。とくに実務に直結する研修内容を取り入れれば、日々の業務に活用できるスキルを習得可能です。
研修プログラムは、新入社員向けの基礎研修から、中堅エンジニア向けの専門研修まで、レベルに合わせて用意するといいでしょう。外部講師を招いたセミナーや、社内エンジニアによる勉強会の開催も知識共有の場として有効です。
成長意欲の高いエンジニアにとって、このような学習機会は大きな魅力です。「この会社にいれば常に最新技術が学べる」という安心感が定着率向上につながります。エンジニアのスキルアップだけでなく、企業の技術力向上ももたらす重要な施策です。
2. 資格取得支援制度の導入
エンジニア向けの資格取得を支援する制度は、スキルアップへのモチベーション向上につながります。受験費用の補助や、合格時の報奨金制度などが効果的です。
資格取得を通じて得られる知識や技術は、業務の質の向上をもたらします。資格という形で自身のスキルが客観的に証明されるため、エンジニアの自信にもつながるでしょう。とくに若手エンジニアには、「次はこの資格を取得しよう」という明確な目標ができるため、キャリアパスを考える指針となります。
企業側も、社員の資格取得状況を把握して適材適所の人員配置に活用しましょう。資格取得支援制度は、エンジニアの成長意欲を刺激するだけでなく、企業への帰属意識を高める効果も期待できます。
3. メンター制度の活用
経験豊富なエンジニアが若手を指導するメンター制度は、技術的なサポートだけでなく、精神的な支援も提供できる仕組みです。新入社員や中途入社のエンジニアが直面する不安や悩みを先輩エンジニアに相談できる環境を整え、早期の離職を予防します。
メンターは技術面の指導に加えて、キャリア形成や職場での人間関係、働き方に関するアドバイスも行います。「困ったときに頼れる人がいる」という安心感は、新たな職場環境に馴染む上で重要です。
また、メンター側も後輩のサポートを通じて、自身の知識を整理し指導力を高める機会となります。組織全体の知識共有や技術継承の観点からも、メンター制度は効果的な施策です。
4. 技術書購入の補助制度
最新技術を学ぶために必要な技術書の購入費用を会社が補助する制度は、エンジニアの自己学習を支援する施策です。技術書は決して安くない投資であるため、会社の費用負担により経済的な負担なく知識を深められます。
月額の上限を設定し、業務に関連する書籍であれば自由に購入できる形式や、申請制で承認後に購入する形式など、企業の状況に合わせた制度設計が可能です。購入した書籍を社内ライブラリとして共有すれば、組織全体の知識向上にも役立ちます。
技術書購入補助制度は、「会社が自分の成長を支援してくれている」という実感をエンジニアに与えるため、エンジニアの学習意欲を刺激し、会社への信頼感を高める効果があります。
5. 技術スタックの定期的な見直し
社内で活用する技術を定期的に見直し、最新技術を積極的に導入しましょう。古い技術スタックだけを使い続ける環境では、エンジニアのスキルが市場から取り残される恐れもあり、それが離職の原因となりうるからです。
新しい技術を導入する際には、一度に全てを変更するのではなく、段階的な移行がおすすめです。新技術の選定プロセスにエンジニア自身が参加できる仕組みにすれば、技術選定の透明性と納得感の向上につながります。
技術スタックの公開も効果的な施策です。自社の技術環境を積極的に公開して、技術への投資に前向きな企業姿勢をアピールし、エンジニアの定着と新たな人材の獲得につなげましょう。
6. 専門性を活かしたアサインの徹底
エンジニアの得意分野や興味のある分野を考慮した業務アサインは、モチベーション維持につながります。「自分のスキルや経験が活かせる」と感じられる業務に取り組めば、エンジニアの満足度は高まるでしょう。
適材適所の配置を実現するには、各エンジニアのスキルや興味の把握が重要です。定期的な面談や自己申告制度を通じて、「今後挑戦したい技術」「深めたい専門分野」を確認し、可能な限り希望に沿った業務を割り当てましょう。
全てのエンジニアが常に希望する業務だけを担当できるわけではないので、、中長期的な視点で個々の専門性を伸ばせるようなキャリアパスを意識しなければなりません。エンジニアが自身の専門性を発揮できる環境は、長期的な定着につながる重要な要素と考えましょう。
7. 評価基準の明確化とフィードバック
エンジニアの成果を適正に評価するために、具体的な評価基準を設定しましょう。エンジニアの業務は成果が目に見えにくいため、評価基準が曖昧だと「頑張っても評価されない」という不満につながるからです。
評価項目としては、業績評価(プロジェクトの完了状況や納期遵守など)、能力評価(技術力や問題解決力など)、情意評価(チームワークやコミュニケーション能力など)の3つの観点からバランスのよい設定が重要です。
評価基準を社内に明示し、定期的なフィードバックを通じて現状の評価と改善点を伝えましょう。エンジニアは自身の立ち位置を理解した上で、次の目標に向けて取り組みを実施します。透明性の高い評価制度は、エンジニアの納得感を高め、職場への信頼感を向上させるものです。
8. 残業の事前承認制の導入
長時間労働を防ぐために、残業の事前承認制を導入しましょう。業務の優先順位を明確にして無計画な残業を減らし、効率的な業務遂行につながるからです。
残業が必要な場合は事前に上長に申請し、承認を得るプロセスを設けます。「なぜ残業が必要か」「いつまでに終わらせるか」を明確にして、不要不急な残業を防ぎます。上長は申請内容を精査し、業務の分散や優先順位の見直しなど、残業を減らすための代替案も提示しましょう。
残業の事前承認制は、単に労働時間の管理だけでなく、業務の可視化とプロジェクト管理の改善にもつながります。働きやすい環境づくりは、優秀なエンジニアを引き留める重要な要素となるのです。
9. 休日対応のローテーション制
休日出勤が特定のエンジニアに集中しないように、対応業務のローテーション制を導入しましょう。特定のメンバーだけが常に休日対応を担当すると、心身の疲労が蓄積し、離職リスクが高まるからです。
チームメンバー全員が休日対応の当番を順番に担当する仕組みを設けます。月単位や週単位でスケジュールを作成し、事前に共有しておけばプライベートな予定も立てやすくなります。緊急時以外の対応は平日に先送りするルールを設けるなど、休日の負担を最小限に抑える工夫も必要です。
休日対応のローテーション化により、特定のエンジニアに負担が偏ることを防ぎ、チーム全体で分担する体制が構築できます。「休むときはしっかり休める」という安心感は、エンジニアの長期的な定着につながります。
10. 転職エージェントとの連携
人材定着に関する課題を把握し、適切な採用・育成施策を実施するには、転職エージェントへの相談も有効です。転職エージェントは、IT業界の市場動向や人材のニーズについて豊富な情報を持っており、エンジニアが何を求めて転職するのかを把握しているからです。
転職エージェントからは、同業他社の待遇や福利厚生、働き方に関する市場動向も入手できます。これらの情報を参考に、自社の環境や制度を見直して、競争力のある職場環境を整えましょう。
転職を考えるエンジニアの本音を理解すれば、離職防止のための効果的な施策を検討できます。転職エージェントと連携して、採用活動だけでなく既存社員の定着率向上にも役立つパートナーシップを構築しましょう。
エンジニアが「ここで働き続けたい」と思える職場づくりは、日々の取り組みの積み重ねです。今回ご紹介した施策を参考に、自社に合った改善策を検討してみてください。必要があれば、外部の専門家の力を借りることも選択肢に入れておきましょう。
ITエンジニアの採用なら社内SE転職ナビ!

環境変化の激しいIT業界で、ITエンジニアの採用にお悩みであれば、専門的なノウハウを持つ社内SE転職ナビにご相談ください。社内SEに特化した求人情報を多数掲載しており、貴社の求めるスキルや経験を持つエンジニアに効率的なアプローチが可能です。
IT業界に精通した担当者が、貴社の企業文化や技術環境を深く理解した上で、最適な人材をマッチングします。単なる採用支援にとどまらず、エンジニアの定着率向上のためのアドバイスも提供可能です。
企業側のニーズとエンジニア側の希望をしっかりとすり合わせて、入社後のミスマッチを防ぎます。エンジニアの離職でお悩みの企業様、優秀なIT人材の採用をお考えの企業様は、ぜひ社内SE転職ナビにご相談ください。
まとめ
エンジニアの離職を防ぐためには、離職の原因となる様々な要因を理解し、適切な対策を講じる必要があります。離職率を下げるための施策には、成長機会の提供や適切な評価制度の確立、働きやすい環境の整備などが挙げられます。
本記事で紹介した施策を組み合わせて実施すれば、エンジニアが「この会社で長く働きたい」と思える環境の構築が可能です。単に離職率を下げるだけでなく、技術力の蓄積や組織文化の醸成を行い、企業の長期的な成長を実現しましょう。
効率よくエンジニアの離職を防ぎたい場合は、社内SE転職ナビの利用もご検討ください。貴社の成長につながる環境構築をサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。