SESエンジニアに興味があるけど、自分に向いているかどうか不安…。そんなふうに感じている方も多いのではないでしょうか?SESエンジニアは幅広いプロジェクトに参加できる一方で、環境の変化や自己管理能力が求められるため、向き不向きがはっきり分かれる働き方でもあります。
本記事では、現役のSESエンジニアであるR.Kotomoが、「SESに向いている人・向いていない人」の特徴や、SESとして働くメリット・注意点について詳しく解説いたします。SESへの転職や案件探しを検討しているエンジニアの方は、ぜひ参考にしてみてください。
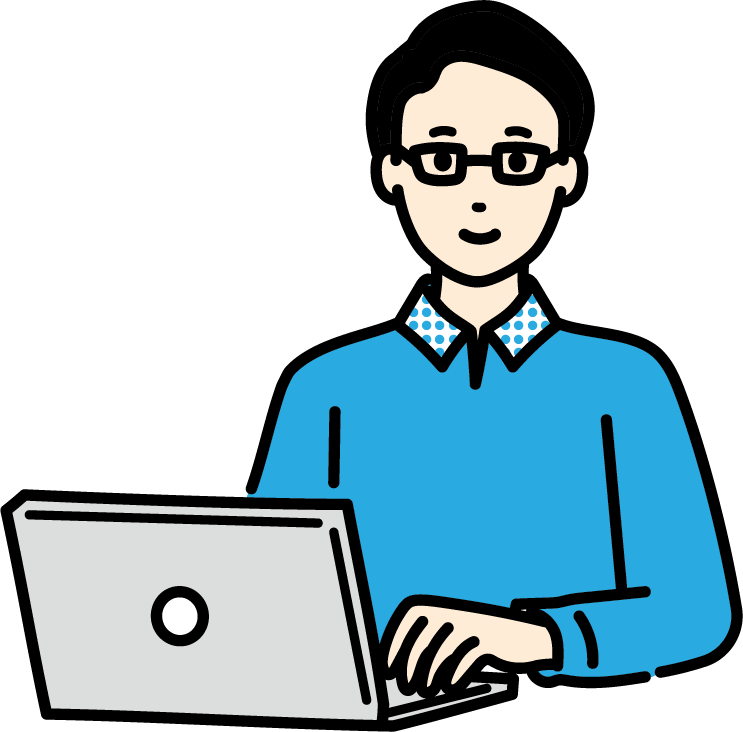
ライター:R.Kotomo
プロフィール:見習い中のデータエンジニアとして、PythonやSQL、クラウドを日々の業務で扱っています。ITエンジニアが執筆した技術記事から多くを学び、自身の経験も誰かの役に立てたいと考えライターを始めました。データ人材やデータ業界に関する情報を、初心者にもわかりやすくお伝えすることを目指しています。実務に基づいた具体的な内容や、現場で役立つノウハウを共有することで、読者のみなさまに気づきを与えられたらと思います。

ナレッジコラムシリーズ
SESエンジニアの働き方とは
SESの特徴
SES(System Engineering Service)とは、エンジニアを顧客企業に派遣し、そこでシステム開発やIT関連業務など、顧客企業に対してエンジニアの技術力や専門スキルを提供するサービスを指します。
自社のオフィスではなく、クライアント先で働くことが特徴で、プロジェクトごとに異なる環境で業務に携わることになり、様々な技術や業界知識を習得できる機会が多いです。
企業がIT人材を柔軟に調達するニーズと、エンジニアが多様な環境で経験を積めるという双方のメリットから、この働き方が広まっています。
SES・社内SE・自社開発の働き方の違い
SESエンジニアは客先常駐型で多様な環境を経験できる一方、社内SEや自社開発は安定性や専門性に優れています。理由としてはSESと社内SE・自社開発では働く場所や指揮命令系統、プロジェクトの継続性、技術スタックの一貫性という点で大きく異なるからです。
SESエンジニアはプログラミング言語は変わらないとしてもA社でAzureを使った開発、次はB社でAWSを使った開発というように技術環境がプロジェクトごとに変化することがあります。一方で社内SEは自社システムの保守運用に一貫して携わり、自社開発なら例えばPythonによるAI開発に特化するといったように専門性を高められます。どの働き方も一長一短があり、自分の志向や目指すキャリアパスに合わせて選択することが重要です。
SESエンジニアに向いている人の特徴
SESエンジニアに向いている人の特徴を以下にあげました。
- 多様な技術を経験したい人
- 環境やプロジェクトの変化を楽しめる人
- 自己学習やスキルアップに積極的な人
- 自己管理能力が高い人
順に説明します。
多様な技術を経験したい人
様々な技術や開発手法を幅広く経験したい方はSESエンジニアに向いています。なぜならSESエンジニアは短期間で複数のプロジェクトや業界に関わることができ、多様な技術スタックに触れる機会が豊富だからです。
実際に私の場合は、データ基盤構築、機械学習システムの運用保守など幅広い業務に携わることができ、複数の技術分野を経験できました。このように数年で複数の技術分野を経験できた事例もSESエンジニアとして珍しくありません。
繰り返しになりますが、SESエンジニアは多様な技術を実務で経験できる可能性があるため、様々な技術に触れたい方はSESエンジニアに向いていると考えています。
環境やプロジェクトの変化を楽しめる人
新しい環境に適応することに抵抗のない方はSESエンジニアに向いています。理由としてはSESでは1年程度でプロジェクトが変わることが珍しくなく、新しいチームや企業文化に適応する必要があるためです。
保守的な金融機関から、自由な社風のIT企業、厳格なプロセスを持つ製造業まで、様々な企業文化や働き方を経験できます。実際に企業ごとに開発体制やプロジェクトの管理方法等が異なり、順応していく必要があると私自身感じています。「変化」を成長の機会と捉え、新しい環境に適応できる方にSESエンジニアは向いていると考えています。
自己学習やスキルアップに積極的な人
自身で必要なスキルを整理し、計画的・自発的に学び続ける意欲のある方はSESエンジニアに向いています。自社開発などのエンジニアとは異なり、SESエンジニアは常駐先の企業に対してスキルアップのためのフォローやキャリアを考えたアサインなどは期待できないからです。
実際に私含め、周りのSESエンジニアは自身で必要なスキルを整理し、学習計画を立て継続的に学び続けている人が多いです。また、現場で必要とされる技術を前もって学んだり、業務時間外に資格取得やオンライン講座で自己研鑽したりといったことがより求められると思います。
自身で学習計画をたて継続的に学び続けることが、苦ではない方にとって、SESエンジニアは自己成長の機会が豊富な働き方といえます。
自己管理能力が高い人
タスク管理やモチベーション維持をご自身でできる方はSESエンジニアに向いています。常駐先には一人でチームに入ることも多く、自律的に働く力が求められるためです。
実際に上司から指示がなくても主体的にタスクをこなし、質の高い成果を出せる方や、困ったときに適切に質問や相談ができる方は、どの現場でも活躍している印象があります。また、自分の市場価値を意識してキャリアプランを立て、次に必要なスキルを見極められる方も成功しやすいです。
繰り返しになりますが、タスク管理やモチベーションの維持などの「自己管理能力」の高い方は、SESエンジニアに向いているでしょう。
SESエンジニアに不向きな人の特徴
SESエンジニアに不向きな人の特徴を以下にあげました。
- 安定した環境で落ち着いて働きたい人
- 一定の技術や業務に集中したい人
- コミュニケーションが苦手な人
それぞれ順に説明します。
安定した環境で落ち着いて働きたい人
環境の安定性や継続性を重視する方にはSESエンジニアは向いていない可能性があります。前述したようにSESは定期的に職場や人間関係が変わるため、安定志向の方にとってストレス要因になりやすいからです。
「同じチームで長く働きたい」「オフィスの場所や通勤経路を頻繁に変えたくない」「同じツールを使用して仕事したい」という方は、環境が変わるたびに大きな負担を感じることがあります。特に、人間関係構築に時間がかかるタイプの方は、ようやく馴染んだ頃にプロジェクトが終わり、新たなプロジェクトに移行するのでストレスを感じやすいでしょう。
安定志向の強い方は、社内SEや自社開発など、より環境が固定された働き方を選ぶ方がパフォーマンス高く仕事を進めていけると思います。
一定の技術や業務に集中したい人
特定分野の専門性を極めたい方にはSESエンジニアが不向きな場合があります。理由としてはSESではプロジェクトごとに必要とされる技術が変わることが多く、一つの技術を極める機会が限られるためです。
プロジェクトによって全く異なる技術スタックを使うことになるSESでは、専門性の構築に時間がかかってしまいます。例えばデータ基盤を例にあげても、AWS上に構築するかGoogle Cloud上に構築するかで求められるスキルが大きく異なります。特定技術に深く携わりたい方は、自社開発企業や専門性の高いチームに所属することを選択するのが良いでしょう。
コミュニケーションが苦手な人
主体的にコミュニケーションをとっていくのが苦手な方は、SESエンジニアとして働くのに向いていないと考えています。
SESエンジニアはプロジェクトや環境が変化するたびに、人間関係を再構築し、コミュニケーションの頻度や方法なども柔軟に変化させる必要があるからです。
実際にリモートワーク中心の企業であれば、チャットでの非同期のコミュニケーションが多くなり、出社中心の企業であればMTGなどの対面でのコミュニケーションが増えるなど、企業によって様々です。その中で従来のコミュニケーション手法や頻度、粒度に固執すると業務が回らなくなる可能性があります。
繰り返しになりますが、プロジェクトの変化に伴いコミュニケーションの方法も柔軟に変える必要があることも念頭に置いておきましょう。
SESエンジニアとして働くメリットと注意点
SESエンジニアとして働くメリットと注意点についてそれぞれ説明します。
SESのメリット
- 多様な経験を詰める
- 人脈を広げられる
- 市場価値を把握できる
SESエンジニアには多様な経験、広い人脈、市場価値の把握などの大きなメリットがあります。
多様な経験
SESエンジニアは、異なる業界や企業のプロジェクトに参加することで、短期間で多様な技術経験を積むことができます。
実際にエンタメ業界のGoogle Cloud上へのデータ基盤構築、通信業界におけるAWSのETL基盤構築など数年で様々な業界にわたり、多様な技術スタックを私自身経験してきました。特に若手エンジニアにとって、技術的な視野を広げる絶好の機会になると考えています。
SESエンジニアは幅広い業界向けの開発体験や多岐にわたる技術スタックを短期間で経験できる可能性のある働き方です。
人脈
SESエンジニアは、多様な業界や企業の人々とネットワークを構築できます。理由としては異なるプロジェクトで多くのエンジニアと協働することで、自然と広範囲な人脈が形成されるためです。
アサイン先の企業での出会いは、単なる一時的な接点ではなく、自身のキャリアのロールモデルとなる人に出会うなど、将来のキャリアに大きな影響を与える可能性があります。SESエンジニアではキャリア形成にプラスに働くような人脈を構築できる可能性があります。
市場価値の把握
SESエンジニアは、自分の市場価値を客観的に把握しやすい働き方です。なぜなら多様なプロジェクトを経験することで、業界の給与相場や求められるスキルセットを把握できるからです。
特に私が日々実感するのはデータエンジニアに求められるスキルが企業のデータ利活用のフェーズによって異なることです。これからデータ利活用を推進していくような企業においては、ジュニアレベルのエンジニアでも重宝される場合があります。一方でデータ利活用が進んでいる企業においてはシニアレベルのエンジニアを求めていることが多いように感じます。
このような視点を持つことができたのもSESエンジニアとして多様なプロジェクトや企業を経験してきたからだと考えています。
繰り返しになりますが、SESエンジニアは自分の市場価値を知るために多様な業界やプロジェクトを経験することで、常に客観的な評価軸を持つことができます。
SESの注意点
SESエンジニアとして働くうえでの注意点を解説していきます。
- 労働環境の不安定さ
- 専門性の構築の難しさ
SESエンジニアは多様な経験ができる一方で、上記のように働いていくうえで難しさもあります。
労働環境の不安定さ
SESエンジニアとして働くうえで念頭に置いておきたいのが、労働環境の不安定さです。プロジェクトベースの働き方には、継続性や一貫性の面で課題が生じやすいためです。
実際に同じ企業でもプロジェクトが変わったため、フルリモートから出社ベースの働き方になったり、本人が望んでいないにも関わらず案件を変えられたりといったこともあるようです。
SESエンジニアにはプロジェクトごとに様々な技術スタックを身につけられる機会がある一方で、働き方もプロジェクトに依存するというリスクも考慮する必要があります。
専門性の構築の難しさ
SESエンジニアは専門性の構築が難しい場合があります。前述したようにプロジェクトによって求められる技術スタックが異なり、長く特定の領域に特化したプロジェクトにアサインされる可能性が低いためです。
実際に私自身が特定の領域にこだわった案件を探した際は、プロジェクト終了後に次の配属先がすぐに決まらず、「待機」状態になることもありました。また、チームの状況によってはテストがメインタスクになり、開発経験を積むことができないことも考えられます。
専門性の構築が難しい可能性もあることを理解した上で、自分なりの対策(専門分野の自己学習、強みの明確化など)を講じることが、SESエンジニアとして長く活躍するコツです。
SESエンジニアとして成功するためのポイント
SESエンジニアとして成功するためのポイントを2点説明します。私の周りで活躍するSESエンジニアはこれらを実践しながら長く現場で活躍しています。
- スキルアップのための自己研鑽
- 柔軟なコミュニケーション能力の養成
順に説明します。
スキルアップのための自己研鑽
SESエンジニアとして成功するには、計画的な自己研鑽を継続的に行うことが不可欠です。理由としては市場価値を維持・向上させるためには、業務で得られる経験だけでなく、自発的な学習が必要だからです。
毎週決まった時間を学習に充てる習慣をつける、年間の資格取得計画を立てる、技術書を月1冊読む目標を設定するなど、具体的な学習計画を立てることが効果的です。また、勉強会やハンズオンセミナーに参加したり、個人開発やOSS活動に取り組むことで、実践的なスキルを磨けます。
学び続ける姿勢と具体的な行動計画を自社開発やSIerのエンジニアよりも強く持つことで、SESエンジニアとしての市場価値を高め続けていけます。
柔軟なコミュニケーション能力の養成
様々な職場環境に適応するためには、柔軟なコミュニケーション能力が技術力と同じく重要です。なぜならSESエンジニアは短期間で新しいチームに溶け込み、信頼関係を構築しながら業務でパフォーマンスを発揮する必要があるからです。
- チームのコミュニケーションスタイルを素早く把握する
- わからないことは適切なタイミングで質問する
- 定期的に進捗や課題を報告する
上記のような基本的なコミュニケーションを徹底することが大切です。また、クライアント企業の文化や価値観を尊重し、場にふさわしい振る舞いができることも重要と考えています。例えば、保守的な金融機関では堅実さを、ベンチャー企業では機動力を重視するなど、環境に合わせたコミュニケーションスタイルに切り替えられるとよいでしょう。技術力と同じく環境適応力と円滑なコミュニケーション能力は、SESエンジニアには求められます。
社内SEの求人なら社内SE転職ナビ


SESエンジニアとしての経験を活かしつつ、あなたのキャリアをより充実させる選択肢が見つかるかもしれません。社内SE転職ナビでは、業界トップクラスの非公開求人率64%(2024年2月時点)を誇り、他では見つからない魅力的な求人にアクセス可能です。
さらに、公開求人数は6,000件以上(2025年4月時点)と豊富な選択肢をご用意。平均で25.6社もの企業をご紹介する実績があり、あなたのニーズに合った企業探しを全力でサポートします。
この記事を読んで「次のステージへ挑戦したい」と感じた方は、まずは登録から始めてみてください。新たな可能性がきっと広がります。
まとめ
SESエンジニアという働き方が、自分の特性や志向に合っているかを見極めることが重要です。本記事で説明したように「変化を楽しめる」「多様な経験を積みたい」「自己研鑽を続けられる」といった方は、SESの環境で力を発揮できる可能性が高いです。
一方で、「安定した環境が好き」「一つの分野を極めたい」という方は、SESエンジニアに不向きの可能性が高く、別の働き方を検討するのも良いと思います。
自分の性格や志向、キャリア目標に合わせて働き方を選択し、その特性を最大限に活かすことが、エンジニアとしての満足度と成長につながります。SESという働き方を検討するうえで、この記事が少しでもお役に立てたら嬉しいです。

-13-1.png)
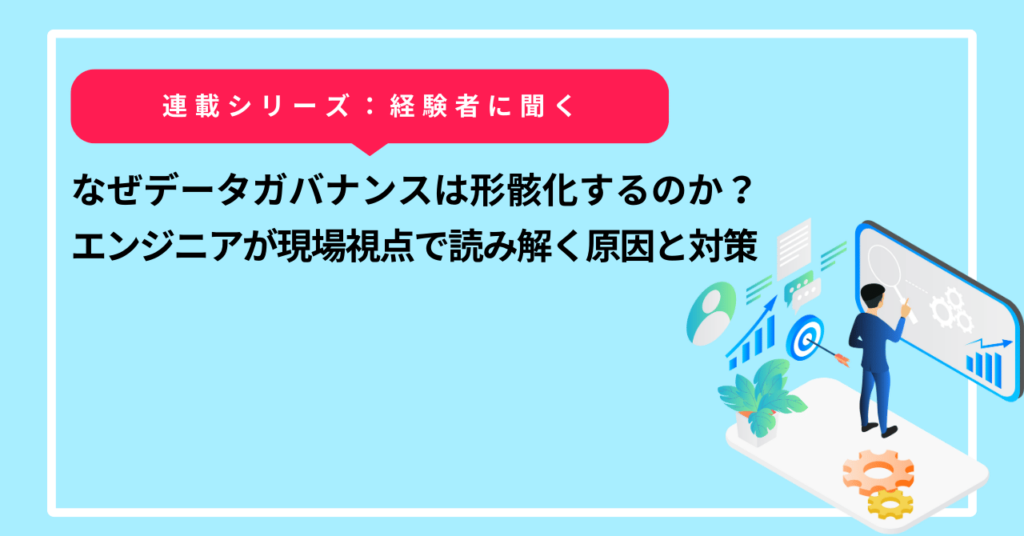

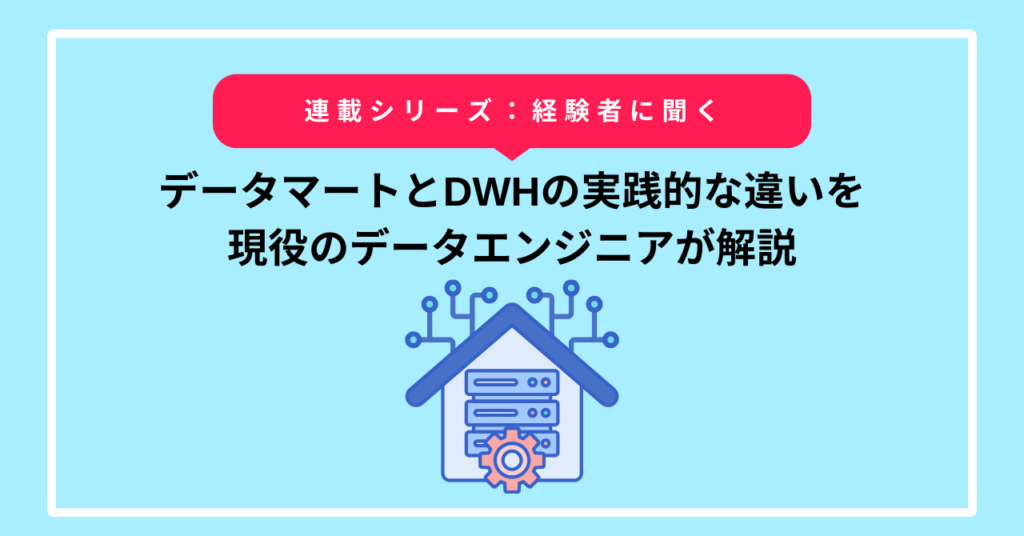
-13-1-300x157.png)










