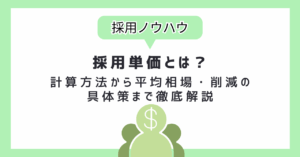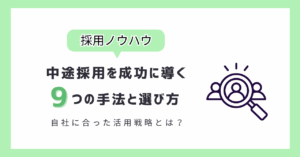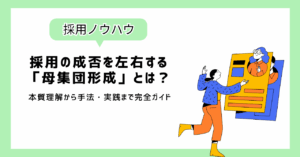フリーランスITエンジニアと契約する際に、「どの契約を選べばいいか」「どのような内容を盛り込めばいいか」といった悩みを抱えている方もいるでしょう。トラブルを未然に防ぎ、円滑な協業関係を構築するためには適切な契約形態を選択しなければなりません。
本記事では、フリーランスITエンジニアとの主な契約形態である請負契約と準委任契約の特徴を解説します。契約時に注意すべきポイントや安全に契約するための方法についても詳しく紹介するので最後までご覧ください。

エンジニア採用、こんな課題ありませんか?
- 技術力だけでなく、事業理解も必要だけど、見極めが難しい
- 社内システムを支える柔軟な対応力を持つ人材がなかなかいない
- 企業文化にフィットするエンジニアを採用したい
「社内SE転職ナビ」なら、技術×カルチャーの両面からマッチするエンジニアをご紹介できます。エージェントによる丁寧なヒアリングに加え、企業から直接アプローチできるダイレクトリクルーティング機能もご利用可能。貴社の採用スタイルに合わせて、最適な候補者との出会いをサポートします。
フリーランスITエンジニアとの契約の種類
フリーランスITエンジニアと契約を結ぶ際には、以下の2つの契約形態があります。
- 請負契約
- 準委任契約
各契約には特徴やメリット・デメリットが存在するため、プロジェクトの内容や目的に応じて適切な契約形態を選択しなければなりません。契約形態によって責任の所在や報酬の支払い方法、業務の進め方も大きく異なるため十分な理解が必要です。ここでは、それぞれの契約形態について詳しく解説するので参考になさってください。
請負契約
請負契約は、フリーランスITエンジニアが成果物の納品を約束する契約形態です。Webサイトの構築やシステム開発など、明確な成果物がある場合に適しています。この契約では、エンジニアは自らの裁量で作業を進める自由がある一方で、納品物の品質に対して責任を負います。
請負契約の最大の特徴は、仕事の完成を約束する点にあり、発注者は完成した成果物に対してのみ報酬を支払う義務が生じます。そのため、作業が長引いても追加の報酬は発生しません。
もし、納品後に不具合が見つかった場合には、契約不適合責任としてエンジニア側が無償で修正対応を行う義務が生じる場合もあります。後のトラブルを避けるために修正範囲や期間を契約書に明記しておくといいでしょう。
準委任契約
準委任契約は、特定の業務の遂行自体を目的とする契約形態です。この契約では、フリーランスITエンジニアは成果物の完成ではなく、依頼された作業の実施が求められます。報酬は工数(時間)に応じて支払われるため、エンジニアにとっては安定した収入が期待できます。
発注者側は作業の進め方について一定の指示を出せる一方で、成果物の完成責任は負いません。準委任契約では「固定制」と「変動制」の報酬体系があり、固定制では月額が一定、変動制では稼働時間に応じて報酬が変動します。
ただし、業務範囲が曖昧になりがちなため、「これも含まれるはず」といった認識の相違が生じないよう契約前に業務範囲を明確にしておきましょう。

フリーランスITエンジニアとの契約の注意点
フリーランスITエンジニアとの契約では、さまざまなトラブルが発生する可能性もあります。契約書の内容不備や認識の相違から生じるトラブルを防ぐためには、契約前に注意点を理解し適切な対策を講じなければなりません。主な契約時の注意点は以下の8種類です。
- 偽装請負
- 契約不履行
- 機密情報の漏洩
- 知的財産権の侵害
- 技術レベルのミスマッチ
- 納期の遅延
- 突然の契約解除
- 請求トラブル
各注意点について順番に見ていきましょう。
偽装請負
偽装請負とは、契約形式は請負契約であるにもかかわらず、実態としては発注者がフリーランスITエンジニアに対して指揮命令を行っている状態を指します。出退勤や勤務時間を管理したり、細かい作業指示を行ったりすると該当します。
本来、請負契約では、エンジニアは独立した事業者として自らの裁量で業務を遂行する権利があります。そのため、偽装請負状態になると労働者派遣法違反となるリスクがあります。発注者側だけでなく、エンジニア側にも影響を及ぼす重大な問題なので注意が必要です。
偽装請負を避けるためには、契約形態と業務の実態を一致させましょう。もし発注者から細かい指示が必要であれば、請負契約ではなく準委任契約や派遣契約を選択するべきです。
契約不履行
契約不履行とは、契約で合意した内容が守られない状態を指します。フリーランスITエンジニアとの契約では、納期遅延や成果物の品質不足、仕様との不一致などが契約不履行に該当します。
特に請負契約では、成果物の完成義務があるため契約不履行となるリスクが高まります。契約不履行が発生した場合、プロジェクトの遅延や追加コストの発生だけでなく損害賠償請求など法的な問題に発展するケースもあります。
このようなトラブルを防ぐには、契約書に業務内容や納期、品質基準を具体的かつ詳細に記載しましょう。成果物の受け入れ基準や検収方法、修正対応の範囲なども明確にしておく必要があります。定期的な進捗確認も有効な対策のひとつです。
機密情報の漏洩
フリーランスITエンジニアは、プロジェクト遂行中に発注者の機密情報や顧客データにアクセスする機会があります。機密情報が意図せず外部に漏洩してしまうと、発注者に深刻な損害が生じてしまいます。
機密情報漏洩のリスクは、エンジニアの故意によるものだけではありません。公共のWi-Fiでの作業や、パスワードで保護されていないデバイスの使用、クラウドストレージの誤った共有設定などが原因となるケースもあります。
リスクを軽減するためには、契約時に秘密保持契約(NDA)を締結し、取り扱う情報の範囲や保管方法、契約終了後の情報廃棄の方法、違反時のペナルティなどを明確に定めましょう。機密レベルに応じたアクセス権限の設定も効果的です。
知的財産権の侵害
フリーランスITエンジニアが納品する成果物には、第三者の知的財産権が含まれる可能性もあります。オープンソースのライブラリやフレームワーク、市販のソフトウェアコンポーネントなどを使用する場合はライセンス条件を遵守しなければなりません。
権利関係が不明確なまま成果物を利用すると、著作権侵害などの法的問題に発展するリスクもあります。納品物の著作権がエンジニア側に残るのか、発注者側に移転するのか、権利の帰属が不明確であれば後々の改修や転用の際にトラブルが生じかねません。
問題を防ぐには、契約書に使用するサードパーティ製品のライセンス条件や、成果物の著作権の帰属、使用範囲などを明記しましょう。商用利用や再配布を行う場合は、より慎重な確認が必要です。
技術レベルのミスマッチ
フリーランスITエンジニアの技術力や経験が、プロジェクトが要求するレベルに達していない場合、深刻な問題につながりかねません。技術レベルのミスマッチは、プロジェクトの遅延や品質低下、最悪の場合は開発の中止となる場合もあります。
発注者側がエンジニアのスキルを過大評価したり、エンジニア側が自身の能力を誇張したりすると発生しやすくなります。またIT業界は技術トレンドの変化が激しいため、「以前は対応できた」というスキルの陳腐化にも注意しなければなりません。
ミスマッチを防ぐためには、契約前の技術面接やスキルチェックが重要です。過去の実績やポートフォリオを確認したり、小規模なテスト案件から始めたりしてスキルレベルを確認しましょう。


納期の遅延
納期の遅延は、フリーランスITエンジニアと契約した場合にしばしば発生する問題です。技術的な課題の発生や要件の変更、エンジニア側の体調不良や他案件との兼ね合いなど、さまざまな要因で納期遅延が発生します。
遅延のリスクを軽減するには、現実的なスケジュール設定が重要です。技術的な不確実性を考慮し、余裕を持ったスケジュールを組み、想定外の問題が発生しても対応できるようにしましょう。定期的な進捗確認を行う仕組みの導入も有効です。
契約書には納期遅延時のペナルティや対応方法を明記しておきましょう。エンジニア側の納期意識の向上につながります。高めることができます。重要なプロジェクトではバックアッププランも検討しておきましょう。
突然の契約解除
フリーランスITエンジニアは、企業に所属する従業員と異なり突然契約を解除する可能性があります。体調不良や家族の事情、より条件の良い案件の出現など、理由はさまざまです。
プロジェクトの途中で契約が解除されると、代替エンジニアの確保や引継ぎに時間とコストがかかり、プロジェクト全体が遅延しかねません。特殊な技術や知識を持つエンジニアの場合、代替要員の確保が困難なケースもあります。
リスクを軽減するためには、契約書に解約条件(解約予告期間や違約金など)を明確に記載しましょう。プロジェクトの知識やノウハウが特定の個人に集中しないよう、定期的な情報共有や文書化の徹底も有効です。一人が抜けてもプロジェクトを継続できる体制も整えておきましょう。
請求トラブル
報酬の支払いに関するトラブルは、フリーランスITエンジニアとの契約で発生しうる問題です。追加作業の発生や要件変更に対する報酬の扱いは、認識の相違が生じやすいポイントです。
エンジニア側は「追加作業なので追加報酬が必要」と考える一方で、発注者側は「当初の契約範囲内」と認識している場合もあります。成果物の品質に不満がある場合、発注者側が報酬の減額や支払い拒否を求めるケースもあります。
トラブルを防ぐには、契約書に報酬体系(固定報酬か時間単価か)、支払い条件(前払い・中間払い・後払いの割合)、追加作業が発生した場合の取り扱いなどを明確に記載しましょう。未払い・過払いのリスクを回避するために、作業内容や工数を記録する仕組みの導入もおすすめです。
フリーランスITエンジニアと安全に契約する方法
フリーランスITエンジニアとの契約の注意点を踏まえ、リスクを最小限に抑える契約を準備しましょう。適切な対策を講じてトラブルを未然に防ぎ、円滑なプロジェクト進行につなげます。フリーランスITエンジニアと安全に契約するための具体的な方法は、以下の7種類です。
- 契約内容の明確化
- 監査・チェック体制の導入
- 契約書の詳細化
- NDA(秘密保持契約)の締結
- アクセス権限の制限
- 著作権の帰属の明確化
- 転職エージェントの活用
順番に見ていきましょう。
契約内容の明確化
フリーランスITエンジニアとの契約トラブルの多くは、契約内容の曖昧さに起因します。トラブルを未然に防ぐには、契約内容を可能な限り明確にしなければなりません。まず、業務の範囲とそれに含まれない範囲(スコープ外)を具体的に定義しましょう。
「Webアプリケーションの開発」といった曖昧な表現ではなく、「ユーザー登録機能、商品検索機能、決済機能を含むECサイトの開発」のように詳細な記述が望ましいです。納期についても、最終納期だけでなく中間マイルストーンを設定し、進捗の遅れを早期に発見できるようにしましょう。
報酬は、金額だけでなく、支払い条件や追加作業の取り扱いも明記してください。修正対応の範囲や期間も事前合意が求められます。
監査・チェック体制の導入
プロジェクトの進行状況を定期的に監査・チェックする体制構築もフリーランスITエンジニアとの契約では重要です。問題の早期発見とスムーズな対応が可能となり、納品物の品質確保やスケジュール遅延の防止につながります。
週次や隔週などの定期的な進捗報告会を設けたり、開発中のコードレビューを実施したりするといいでしょう。進捗報告のフォーマットを事前に決めておけば、報告の質が一定となり問題点を逃しません。中間成果物のレビューも行い、方向性の誤りや品質問題の早期発見も大切です。
チェックポイントを両者の合意のもと契約書に明記し、偽装請負のリスクを回避しつつ適切な品質管理を行いましょう。
契約書の詳細化
フリーランスITエンジニアとの契約では、口頭の約束や簡易的な契約書では不十分です。詳細な契約書の作成を忘れないようにしましょう。契約書には基本的な業務内容や報酬だけでなく、予想されるトラブルへの対応策も盛り込むべきです。
業務範囲を具体的に記載し、含まれるものと含まれないものを明確にします。納期も、最終期限だけでなく中間納品のスケジュールも設定します。報酬は、金額や支払い条件、追加作業の扱いを詳細に定めましょう。
成果物の検収基準や検収方法、瑕疵担保責任の範囲と期間も明確にする必要があります。納期遅延時のペナルティや契約解除の条件、解除時の成果物や報酬の扱いなども記載します。法的な専門知識がない場合は、弁護士などの専門家に相談しましょう。
NDA(秘密保持契約)の締結
フリーランスITエンジニアは、プロジェクト期間中に機密情報にアクセスする機会があります。情報漏洩のリスクを軽減するには、業務委託契約とは別にNDA(秘密保持契約)を締結しましょう。
NDAにはどの情報が機密情報に該当するのか、その範囲を明確に定義します。顧客データや未公開の製品情報、システム構成図、アクセス認証情報などがその一例です。機密情報の取り扱い方法や、契約終了後の情報の返却・廃棄方法についても具体的に規定する必要があります。
秘密保持義務の期間や違反した場合のペナルティも明記して、抑止力を高めましょう。とくに重要な情報を扱う場合は、情報セキュリティに関する研修や誓約書の提出をおすすめします。
アクセス権限の制限
フリーランスITエンジニアに対しては、業務に必要な範囲内でのみシステムやデータへのアクセスを許可しましょう。不必要な情報へのアクセスを制限して、情報漏洩のリスクを低減します。エンジニアには担当業務に必要最小限のアクセス権限のみを付与します。
重要なシステムには多要素認証を導入し、特定のIPアドレスからのみアクセス可能にするなどの制限も有効です。VPNやリモートデスクトップなど、安全な接続手段を提供して、公共Wi-Fiなどの安全でない環境からの作業によるリスクを軽減しましょう。アクセスログを取得・監視する仕組みによる不正アクセスの早期発見や事後的な証跡確保も必要です。
著作権の帰属の明確化
フリーランスITエンジニアが開発したプログラムやシステムの著作権がどちらに帰属するかを明確にしておきましょう。著作権の帰属が不明確だと、納品後の改修やソースコードの再利用、派生製品の開発などに制約が生じかねません。
一般的には、発注者がプログラムの著作権を取得するケースが多く、その場合は契約書に「著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む)は発注者に譲渡される」と明記します。
エンジニア側が汎用的なライブラリやモジュールの著作権を保持したい場合は、契約の対象から除外する条項の記述も可能です。エンジニアの実績として納品物をポートフォリオに掲載してもよいかについて、事前に合意しておくと良いでしょう。
転職エージェントの活用
最小限のリスクでフリーランスITエンジニアと契約するには、フリーランス就業支援エージェントの活用がおすすめです。IT人材に特化したエージェントは、多数のフリーランスエンジニアの情報を保有しており、プロジェクトの要件に合ったスキルや経験を持つ人材を効率的にマッチングできます。
過去の案件実績や評価情報を持っているため、エンジニアの技術力や信頼性を一定程度担保できます。契約条件の交渉や契約書の作成サポート、トラブル発生時の仲介など、契約に関するさまざまな面でサポート可能です。
高度な専門技術が必要な案件や短期間で人材を確保したい場合には、エージェントの活用が最適です。ただし、エージェント経由の場合は、仲介手数料の発生を考慮する必要があります。
フリーランスITエンジニアと安全に契約するなら社内SE転職ナビ!

フリーランスITエンジニアとの契約におけるさまざまなリスクを回避し、安全に優秀な人材を確保したいとお考えなら、社内SE転職ナビがおすすめです。
社内SE転職ナビでは、技術力やコミュニケーション能力、過去の実績など、多角的な観点でフリーランスITエンジニアを評価しているため、貴社のプロジェクトに最適な人材とのマッチングが可能です。
契約書の作成サポートや定期的なフォローアップなど、契約後のサポート体制も充実しています。万が一トラブルが発生した場合にも、専門のコンサルタントが迅速に対応し、問題解決をサポート可能です。フリーランスITエンジニアとの安全な契約を求めているのであれば、この機会にぜひ社内SE転職ナビをご活用ください。
まとめ
本記事では、フリーランスITエンジニアとの契約に関するポイントを解説しました。主な契約形態である請負契約と準委任契約の特徴を理解し、プロジェクトの性質に適した形態を選択なさってください。
偽装請負や契約不履行、機密情報の漏洩など、契約におけるさまざまなリスクとその対策についても詳しく説明しました。紹介した対策を実施し、フリーランスITエンジニアとの協業をより安全に進めましょう。
自社主体の契約に不安がある場合は、フリーランスITエンジニアとの契約に実績豊富な社内SE転職ナビにご相談ください。契約内容だけでなく、スキルや経験面も考慮したマッチングを提供いたします。