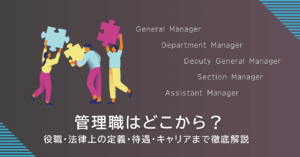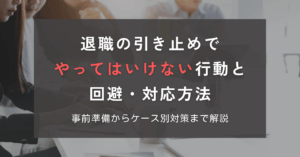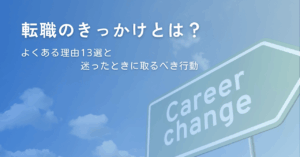出産は、体にも生活にも大きな変化をもたらすライフイベント。その中で「収入が減ってしまうのでは」と不安を感じる方も少なくありません。実際、会社員であっても産休中の給与支払いは義務ではなく、多くの企業で無給となるのが現実です。
そんなとき、頼りになるのが健康保険から支給される「出産手当金」。産休中の給与が出ない場合に、所得の約2/3が健康保険から支給される制度で、働く人の生活を支えてくれます。
この記事では、出産手当金のしくみや対象条件、支給金額の目安、申請の流れ、そして退職予定者の注意点まで、わかりやすく解説します。出産を控えている方も、今後を見据えて知っておきたい方も、制度の基本をぜひ押さえておきましょう。

産休手当(出産手当金)とは?
出産手当金は、産休中の給与が出ない場合に、健康保険から所得の約2/3が支給される制度です。
法律上、出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間前)から産前休業、出産の翌日から8週間は産後休業とされています。給与が支払われない場合、その期間に応じて出産手当金が支給され、公的医療保険によるサポートとして働く人の生活を支えます。
出産手当金の対象になるのはどんな人?
以下の3点すべてに該当する場合、出産手当金を受け取ることができます。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 健康保険の被保険者である | 勤務先の社会保険(協会けんぽや組合健保など)に加入している |
| 妊娠4か月(85日)以降の出産である | 出産だけでなく、流産・死産・中絶も対象になる場合があります |
| 出産を理由に会社を休業している | 無給で休業していることが前提(給与支給ありの場合は減額 |
※パート・アルバイトでも、社会保険加入条件を満たしていれば対象になります。
※出産前後に退職する場合でも、条件を満たしていれば申請可能です。
出産手当金はいつ振り込まれる?支給される時期と受け取り方
出産手当金の支給時期は、申請からおよそ1〜2か月後が目安です。産後に必要書類をそろえて健康保険組合に申請し、不備がなければ、指定口座に一括で振り込まれます。
ただし、以下のようなケースでは時期が前後することがあります。
- 医師の証明や勤務先の記入が遅れる
- 健康保険組合側の審査が混み合っている
- 申請を分割して行う(例:産前分・産後分に分けて申請)
「なるべく早く受け取りたい」という場合は、産前分だけでも先に申請する方法もあります。その場合でも、勤務先や医療機関への確認・依頼が必要になるため、出産前に流れを把握しておくと安心です。
一部を先に受け取りたい場合は「分割申請」を活用
出産手当金は、本来産前・産後あわせて一括で申請しますが、事情に応じて分けて申請することも可能です。
たとえば以下のようなケースでは、分割申請が役立ちます。
分割申請しても、トータルの支給額に変わりはありません。ただし、申請回数が増える分、会社や医療機関への依頼もそれぞれ必要になる点は押さえておきましょう。
支給される期間と金額の目安
出産手当金は、「どのくらいの期間、いくら支給されるのか」が事前にわかっていると安心です。以下に、支給期間や金額の計算方法、支給額の目安をまとめました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給期間 | 産前42日間(多胎妊娠は98日)+ 産後56日間(合計98日が基本) |
| 計算式 | (直近12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30) × 2/3 × 対象日数 |
| 支給例 | 標準報酬月額が20万円の場合: 4,445円/日 × 98日 ≒ 43万5,610円 |
※出産予定日より遅れた場合は、予定日から実際の出産日までの遅れた日数も対象になります。
育児一時金との違いって?
出産に関する公的なサポート制度には、出産手当金のほかに「出産育児一時金」もあります。両方とも健康保険に基づく制度ですが、対象者や支給の目的が異なるため、混同しないようにしましょう。
出産育児一時金は、出産にかかる医療費をカバーする目的で支給される制度で、加入している健康保険(全国健康保険協会=協会けんぽ、または組合健保など)から支払われます。
原則として1児につき42万円が支給され、分娩費用や入院費などに充てられます。医療機関に直接支払われる「直接支払制度」が一般的で、自己負担の軽減につながります。
一方、出産手当金は、出産のために仕事を休む間の所得補償を目的とした制度で、勤務先を通じて加入している健康保険から支給されます。
| 制度名 | 対象 | 金額 | 支給タイミング |
|---|---|---|---|
| 出産手当金 | 勤務先の健康保険に加入している人 | 賃金の約2/3(後述) | 出産後、申請後1~2か月 |
| 出産育児一時金 | 健康保険加入者全員 | 42万円(1児) | 出産直後または医療機関へ直接支払い |
両方の制度は併用が可能です。つまり、「出産費用の補助」と「休業中の収入補填」を別々にカバーできるということです。どちらも申請忘れのないよう、早めに準備を進めましょう。
出産手当金の申請方法
ここでは、実際に出産手当気を申請する際の方法についてご説明します。
申請に必要な書類
出産手当金を申請する際に必要となる主な書類は、以下の3点です。
| 必要な書類 | 概要 |
|---|---|
| 健康保険 出産手当金支給申請書 | 申請の中心となる書類で、健康保険組合や勤務先から入手できます。協会けんぽなどではWebサイトからダウンロード可能です。 |
| 勤務先による証明(事業主記入欄) | 休業期間や賃金の支払い状況を会社が記入する欄です。在職中は人事や総務に依頼すれば対応してもらえますが、退職後に申請する場合は自分で依頼する必要があります。 |
| 医師または助産師による証明(出産の事実の証明) | 出産日や妊娠週数を記載してもらう欄で、産院で記入を依頼します。分割申請する場合は、産前・産後それぞれに証明が必要です。 |
書類はすべてそろってから健康保険組合に提出する必要があります。不備があると支給までに時間がかかるため、事前に必要な項目や依頼先を確認しておくことが大切です。
申請の流れ
出産手当金は、出産後に申請することで支給されます。以下の流れに沿って、必要書類を準備・提出しましょう。
勤務先の総務や人事などから、「健康保険 出産手当金支給申請書」をもらいます。
多くの健康保険組合では、公式サイトからダウンロードすることも可能です。
申請書には、被保険者(あなた)の氏名・住所・保険証の記号番号・振込口座などを記入する欄があります。間違いがないよう、落ち着いて記入しましょう。
勤務状況や休業期間、賃金の支払い状況などを、会社の担当者に記入してもらいます。
この欄は、申請するたびに必要になるため、分割で申請する場合はその都度記入が必要です。
勤務状況や休業期間、賃金の支払い状況などを、会社の担当者に記入してもらいます。
この欄は、申請するたびに必要になるため、分割で申請する場合はその都度記入が必要です。
すべての記入が済んだら、加入している健康保険組合へ申請書を提出します。
提出後、特に問題がなければ、およそ1〜2か月後に指定口座へ一括で振り込まれます。
退職予定の場合の注意点
出産を機に会社を退職する場合でも、以下の条件を満たしていれば、出産手当金を受け取ることができます。
- 退職日の前日までに、継続して1年以上健康保険に加入していた
- 退職後も、産前産後の条件を満たしている
たとえば「妊娠9か月のタイミングで退職したが、退職日前日まで社会保険に加入していた」という方であれば、出産手当金の対象になります。
「退職日の出勤」に注意
退職日当日に出勤してしまうと、「労務に就いた」と見なされ、出産手当金の支給対象から外れてしまう可能性があります。そのため、退職日はあくまで「出勤しない日」として設定し、有給休暇の消化などで対応するのが安心です。
退職後の申請手続きはどうすればいい?
会社を退職した後は、出産手当金の申請も自分自身で行う必要があります。在職中であれば人事や総務がサポートしてくれることが多いですが、退職後はそういった相談窓口がなくなるため、不安を感じる方もいるかもしれません。
手続きの流れ自体は複雑ではありませんが、提出書類の記入先や送付先が変わる点には注意が必要です。具体的には、在職中であれば会社経由で健康保険組合に提出していた申請書を、退職後はご自身で健康保険組合に直接郵送する形になります。(例:協会けんぽ加入者であれば、該当の支部宛てに郵送)
提出先や申請書の様式は、健康保険組合のWebサイトで確認できるので、退職前に一度チェックしておくと安心です。
出産手当金についてのよくある質問・Q&A
ここでは、出産手当金についてのよくある質問に回答します。
Q. 出産前に退職した場合でももらえますか?
一定の条件を満たしていれば、退職後でも申請可能です。特に「1年以上の被保険期間があること」と「退職日に出勤していないこと」は重要な条件です。
Q. 支給額は実際の給与と違いますか?
支給額は標準報酬月額をもとに算出され、実際の手取りとは異なります。社会保険料や税金が控除されないため、手取りに近い金額になります。
Q. パートや派遣社員でも対象になりますか?
社会保険に加入していれば、雇用形態に関係なく出産手当金の対象になります。
Q. フリーランス(国民健康保険)でも受け取れますか?
出産手当金は会社の健康保険に加入している人が対象です。国民健康保険加入者は対象外ですが、出産育児一時金は受け取ることができます。
社内SEの求人なら社内SE転職ナビ

ライフイベントと両立できる働き方を考えたとき、社内SEという選択肢は現実的で、再現性のあるキャリアです。実際に「社内SE転職ナビ」では、公開求人数は6,000件を超え(2024年5月時点)、ワークライフバランスを重視する方からの登録も増えています。
さらに、提案求人数の平均は25.6社。限られた時間の中でも、経験や希望に合う職場を見つけやすい環境が整っています。制度だけでなく、働き方も見直したい方にこそ、一度触れてほしい転職支援サービスです。
まとめ
育児一時金や民間保険など、他の制度ともあわせて活用しながら、ご自身の働き方・ライフスタイルに合った準備を進めていきましょう。出産手当金は、産休中の収入減をカバーしてくれる重要な制度です。育児に専念する時期に、経済的不安を少しでも減らしてくれるこの制度は、働く人にとっての大きな支えになります。
とくに、ITエンジニアのようにプロジェクトごとに動きが変わる仕事では、「制度を正しく知っておくこと」自体が、将来の安心につながります。出産育児一時金や、民間の保険サービスなどとあわせて、自分に合った制度を組み合わせながら、無理のないライフプランを描いていきましょう。もし制度の使い方に迷ったら、加入している健康保険組合や職場の担当者に、早めに相談することをおすすめします。
※本記事は2025年4月時点の情報に基づいて作成しています。制度内容は変更される可能性があるため、最新情報は加入している健康保険組合の公式サイトでもご確認ください。



-11-300x157.png)