エンジニアがモチベーション高く仕事に取り組むことは、成果を出すうえで欠かせません。この記事では、モチベーション管理の重要性と、低下する原因、それを高めるための具体的な方法について解説します。
この記事は以下の方におすすめです!
- 仕事に対してやる気がでないことに悩むエンジニア
- 自身のパフォーマンス低下を感じている方

ライター:firstriver
30年以上の会社生活を経験。家電機器に組み込むマイクロコンピュータのソフトウェアと周辺回路の設計を皮切りに、ソフトウェア開発部門、技術開発部門の開発リーダーやマネージャーに。その後、ケーブルテレビ配信の技術規格策定に携わる。現在は、化学メーカーの情報システム部門で各種システムやツールの導入・運用を担当。

ナレッジコラムシリーズ
そもそもモチベーションとは何か?
モチベーションは、日本語では「やる気」「意欲」「動機づけ」と訳されます。
モチベーションは目標やゴールに向かって行動する原動力であり、たとえば「仕事へのモチベーションが高い」とは、仕事に対して前向きに取り組んでいる状態を指します。これは、効率よく成果を出すうえで欠かせない要素です。
エンジニアのモチベーション管理
エンジニアのモチベーションが下がると、次のような影響が出ることがあります。
- 資料作成で誤字やミスが増え、品質が低下
- 手戻りや修正対応に時間を取られ、納期遅れが発生
- コードの完成度が下がり、バグ修正に多くの工数がかかる
こうした状態が続くと、チームやプロジェクト全体にも悪影響を及ぼします。
エンジニアのモチベーションを下げる理由
エンジニアとして日々の業務に取り組む中で、やる気を失ってしまう場面は少なくありません。では、どのようなことがモチベーションの低下につながるのでしょうか。主な要因を紹介します。
- 正当に評価されない
- 今後の長期的目標を設定できていない
- 職場の人間関係
- 希望する業務に携われない
- 常に残業が多い
- 昇給がない
- 体調不良
正当に評価されない
会社で働く大きな目的の1つは給与をもらうことです。会社員は会社に労働力を提供してその対価として給与をもらうことができます。会社に提供した労働力を評価されることによって初めて、給与がアップするものです。
ところが、自分では頑張っているつもりなのに、給与がいつまで経っても上がらなければ、会社から「正当に評価されていない」と考えざるをえません。このような状態が続けば、仕事に対する意欲は失われていく可能性が高くなります。
例えば開発プロジェクトにおいて、自分の頑張りがプロジェクトを成功に導いたにもかかわらず、同僚が評価され自分が評価されない場合、「こんなにも頑張ったにもかかわらず正当に評価されない」と感じるかもしれません。
成長できている実感がない
エンジニアは、仕事を通じて専門スキルや業務遂行能力が高まっていると感じられることで、達成感ややりがいを得られる人が多いでしょう。そしてその実感が、「また頑張ろう」という前向きな気持ちにつながっていきます。しかし、日々の業務がルーチンワークばかりで、新しい知識や技術を学ぶ機会が少ないと、成長の実感が得られず、やる気を失いやすくなります。
たとえば、
- 同じ機能の保守対応ばかりで、新しい技術に触れることができない
- 難易度の高い業務がチーム内の特定のメンバーに偏っていて、チャンスが回ってこない
- 評価面談で「成長している」と言われても、具体的な根拠やフィードバックがない
こうした状況が続くと、「このままでいいのだろうか」という不安や焦りにつながります。もし成長の実感が持てないと感じたら、まずは上司にキャリアやスキルアップの方向性について相談してみることが一つの手です。
長期的目標を設定できていない
仕事は一通りこなせるようになり、エンジニアとしてある程度の業務は任されている。そんな中でも「この先、自分は何を手掛けていきたいのか」「将来どんな立場で頑張っていきたいのか」といった明確な目標を持っていないと、日々の業務がただのルーティンになってしまいがちです。
目標がないまま与えられた仕事をこなしていると、いわゆる「惰性で働く」状態に陥りやすく、モチベーションの維持が難しくなってしまいます。エンジニアとしてのモチベーションを保つためには、「自分は何を目指すのか」という長期的な目標、つまりキャリアパスを描くことが重要です。
たとえば次のような目標を設定することで、将来像を具体的に思い描きながら仕事に取り組むことができます。
- 入社3年後には、独力で開発プロジェクトメンバーとして役割を果たせるようになる
- 入社5年後には、チームリーダーとしてメンバーを牽引し、プロジェクトに貢献していく
- 入社10年後には、プロジェクトリーダーとして全体をまとめ、成功に導く立場になる
- 20年後には、CTOとして会社の技術方針を立案し、経営にも関わっていく
目標の内容は人それぞれですが、「こうなりたい」というイメージがあるだけで、今の業務に対する向き合い方は大きく変わります。長期的な目標を持ち、それを意識しながら仕事に取り組むことが、エンジニアとしてのモチベーション維持につながります。
職場の人間関係
会社で仕事を進めていくうえで、職場の人間関係を良好に保つことは非常に大切です。人間関係が良ければ、相談や確認といったコミュニケーションが自然に行われるため、仕事もスムーズに進みます。一方で、関係がぎくしゃくしていると、ちょっとしたやり取りすら億劫になり、ミスや遅れ、非効率が生じやすくなります。
たとえば、次のような場面です。
上司から「明日までに〇〇の資料を作ってほしい」と指示があり、それを聞いたチームメンバーが、良かれと思って急いで資料を作成し、会議に臨んだ。ところが、その資料はすでに別のメンバーにも指示が出されており、会議の場でその事実を初めて知った。
こういった行き違いが何度も起これば、「頑張っても報われない」「無駄なことをしている」と感じてしまい、仕事へのモチベーションは確実に下がっていきます。
希望する業務に携われない
エンジニアであれば多くの場合、入社時に「〇〇の開発を手掛けたい」「〇〇の製品に関わりたい」など、具体的な希望を持っているはずです。とはいえ、入社後しばらくの間は、まず自分の開発スキルを高めるためにも、会社からの要請に従ってアサインされた仕事で成果を上げていく努力が必要です。
一定の実績を重ねたうえで、ようやく自分の希望を伝え、業務内容について相談できるフェーズに入ります。しかし、いくら成果を上げても希望がまったく考慮されず、繰り返し伝えても受け入れてもらえないようであれば、次第にやる気は失われていってしまいます。
もちろん会社側には会社側の事情があります。たとえば「この分野は彼が一番の適任で、他に代われる人材がいない」など、合理的な理由があるのかもしれません。だからこそ、双方の考えをすり合わせたうえで、どうすれば本人の希望を踏まえたキャリア形成ができるのか、具体的な話し合いが必要です。そうでなければ、せっかくの優秀なエンジニアを失ってしまう可能性もあります。
常に残業が多い状態が続く
開発プロジェクトの納期間際や商品リリース直前など、明確な理由がある場合に一時的に残業が増えるのは、ある程度やむを得ません。その場合でも、納品後に残業を減らすなどして、トータルで調整できれば大きな問題にはなりにくいでしょう。
問題なのは、特に理由もなく慢性的に長時間労働が続いてしまうケースです。このような状況が続くと、エンジニアのプライベートな時間が削られ、ワークライフバランスが崩れてしまいます。結果として、趣味や休息、家族との時間など、仕事以外の大切な活動が十分にできなくなり、心身の余裕が奪われていきます。
こうした状態が積み重なれば、当然ながら仕事に対するモチベーションは大きく低下してしまいます。
昇給がない
入社から数年間は、仕事の進め方を覚えたり、専門スキルを身につけたりする「修業期間」と捉えれば、すぐに給与が上がらなくても大きな問題ではないかもしれません。しかし、仕事に慣れ、着実にスキルを身につけ、一定の成果を安定して出せるようになっても、給与がまったく上がらないとなると、やる気を保つのは難しくなってきます。
また、給与や賞与の話題は、他社に入った同期や同年代の友人たちとの間でも出るものです。「この4月、予想以上に給与が上がって驚いた」「特に目立った成果はなかったけど、ちゃんとボーナスが出て嬉しかった。これからもっと頑張ろうと思う」
そんな声を聞く中で、「自分はこれだけ頑張っているのに、なぜ昇給も賞与もないのか」と感じてしまえば、モチベーションの低下は避けられません。
体調不良
エンジニアならずとも全ての働く人にとって、働くための活力の源は「健康であること」です。肉体的な健康が精神的な健康を支え、前向きな考え方で仕事に取り組んでいくことができ、仕事の成果を出していくことができるものです。
そのために、自身の健康管理をしっかり行っていくことがエンジニアに求められる大切なことの1つです。
エンジニアがモチベーションを上げるためにすべきこと
モチベーションが上がらない場合に、モチベーションを上げる方法について説明します。
- 原点に戻って考える
- 自身の長所を再確認
- 成功時のことを思い起こす
- 上司や先輩と話してみる
- 新たな技術習得を目指す
原点に戻って考える
「原点」とは、エンジニアになろうと決めたときの気持ちを指します。大学や専門学校の卒業時、自分の意思でエンジニアの道を選んだはずです。たとえば、
- 小さい頃からプログラミングが好きで、ゲーム作りに没頭していた
- 「将来は自分の作った○○を世の中に出して、多くの人に使ってもらいたい」と思っていた
そんな原点に立ち返ることで、初心を思い出し、「今は大変だけど、あの時の夢を実現するためにもう一度頑張ってみよう」と気持ちを前向きに切り替えられることがあります。
自身の長所を再確認する
モチベーションが下がっているときは、自分の欠点ばかりが気になり、自信を失いやすくなります。そんな時こそ、自分の強みや良いところを書き出してみることが効果的です。たとえば、
- 結果を出すのに時間はかかるけれど、最後までやりきる粘り強さがある
- チーム内で良い雰囲気を作るのが得意で、メンバーと円滑な関係を築ける
こうした「書いて整理する」習慣は、感情の整理や自己理解につながる方法として知られています。いわゆる「ジャーナリング」に近いアプローチでもあり、日々の感情や考えをアウトプットすることで、気持ちの整理がしやすくなるとも言われています。
落ち込んでいるときに読み返せば、「自分はちゃんと積み上げてきたんだな」と思えるきっかけになるはずです。ネガティブな気分に引っ張られがちなときこそ、自分の長所に目を向ける時間をとってみてください。
成功体験を思い起こす
モチベーションが下がっているときは、「今の自分にはうまくできる気がしない」と感じがちです。そんなときこそ、過去に自分が成果を出せた場面=成功体験を具体的に思い出すことが、前向きな気持ちを取り戻す助けになります。
- ○○開発プロジェクトでトラブルが発生した際、率先して対応にあたり、結果的にスケジュール通りに完了させることができた
- 社内で○○開発計画についてプレゼンを行い、合意を得て、計画通りにプロジェクトを進めることができた
こうした体験は、自分の行動や判断が成果につながった「確かな証拠」です。気持ちが落ち込んでいるときこそ、過去の自分の実績を思い出し、「やればできた」経験を確認することで、前を向く力が湧いてきます。
「自分の長所を再確認する」ときと同様に、思い出すだけでなく書き出しておくのがおすすめです。言葉にすることで、当時の状況や努力、達成感がよりリアルに思い出され、自信の回復につながります。
「あのプロジェクトのときも、ちゃんと乗り越えられた。今回だって、自分なら大丈夫」
そんなふうに、過去の自分が、今の自分を支えてくれる感覚が得られるはずです。
上司や先輩、同僚と話してみる
モチベーションが下がっているときほど、つい一人で抱え込みがちですが、信頼できる上司や先輩、同僚に話してみることで気持ちが軽くなることがあります。悩みや不安を口に出してみるだけでも、頭の中で堂々巡りしていた考えが整理され、気持ちのモヤモヤが緩和されるものです。
また、自分では行き詰まっていると思っていたことでも、第三者の視点から見ると意外とシンプルな対処法がある場合もあります。信頼できる人だからこそ、「ちゃんと見てくれている」「理解してくれる」という安心感が生まれ、それが前向きな気持ちや行動の一歩につながっていきます。
モチベーションを自力で立て直すのが難しいと感じたときは、「話すこと」自体をリセットの手段として使うのも有効です。
新たな技術習得を目指す
日々の業務がルーチン化し、「このままでいいのか?」という閉塞感を覚えることは、モチベーションの低下につながりやすいものです。
たとえば「開発の仕事はこなせているけど、毎回同じような内容で成長している実感がない」「新しいことに触れていないせいか、自分が止まっている気がする」そんな感覚に陥ったときは、これまで触れてこなかった技術や知識の習得にチャレンジしてみるのがおすすめです。
新しい技術に取り組むことで、知的好奇心が刺激され、「もっと知りたい」「やってみたい」という気持ちが自然と湧いてきます。それが日々の業務にも前向きなエネルギーとして作用し、停滞していた気持ちに風を通してくれるような感覚を得られるはずです。
資格取得や新技術のキャッチアップ、興味のある分野の勉強会に参加してみるなど、小さな一歩でいいので、自分の成長を実感できる行動を取り入れることが、モチベーションを取り戻すきっかけになります。
モチベーションを上げる最後の手段は転職
ここまで、モチベーションを取り戻すために自分自身でできる工夫やアプローチを紹介してきました。ただ、それでも気持ちが前向きにならないとき、原因は自分の中だけではなく、今の仕事環境にある可能性もあります。
たとえば、
- 担当業務に変化がなく、成長実感を持ちづらい
- 頑張っても評価や待遇が変わらない
- 長時間労働や非効率な仕組みが常態化している
- 組織の風土が自分に合わず、提案や相談が通りづらい
このような状況では、どれだけ工夫をしてもモチベーションを維持するのは難しくなっていきます。そんなときは、自分の考え方や努力を変えるだけでなく、働く場所そのものを見直すこともひとつの選択です。


環境が変われば、仕事内容や評価のされ方、人との関わり方も変わります。それが結果として、「もう一度挑戦したい」「前向きに仕事に向き合える」と思えるきっかけになることもあります。今の延長線上では解決が難しいと感じたら、一度立ち止まって「この先どう働きたいか」「どんな環境なら前向きに働けそうか」を考えてみるのも良いタイミングかもしれません。
社内SEの求人なら社内SE転職ナビ


もし「今の環境ではモチベーションが上がらない」「前向きになれない」と感じているなら、新しい働き方を選ぶタイミングかもしれません。社内SE転職ナビは、落ち着いた働き方を望むエンジニアに向けた転職支援サービスです。
取り扱う求人は10,000件以上(※2024年2月時点)あり、その64%が非公開求人。経験や希望に合ったポジションを、エージェントが厳選してご提案します。「このままでいいのか」と感じたとき、その違和感を放置しないことが、次の一歩につながります。まずはお気軽に、情報収集の感覚でエージェントと相談してみませんか?
まとめ
エンジニアのモチベーション管理の重要性を説明し、そもそもなぜモチベーションが低下してしまうかの原因とモチベーションを上げるための方法について説明しました。
モチベーションは、仕事を進める場合においてエンジニアの原動力となるとても大切なものであるということ、このモチベーションを自身で制御していくことが可能であるということを理解して頂けたと思います。
さらに、それでも改善が見込めない場合には、環境を変える(転職を検討する)ことも1つの手段として提案させて頂きました。
エンジニアの皆さんのキャリアが充実したものになることを願っています。


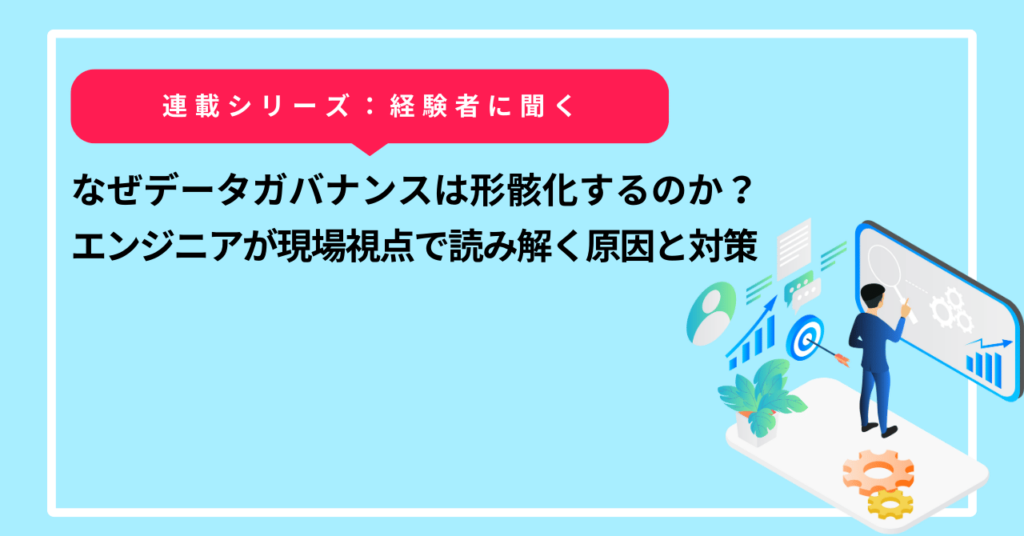

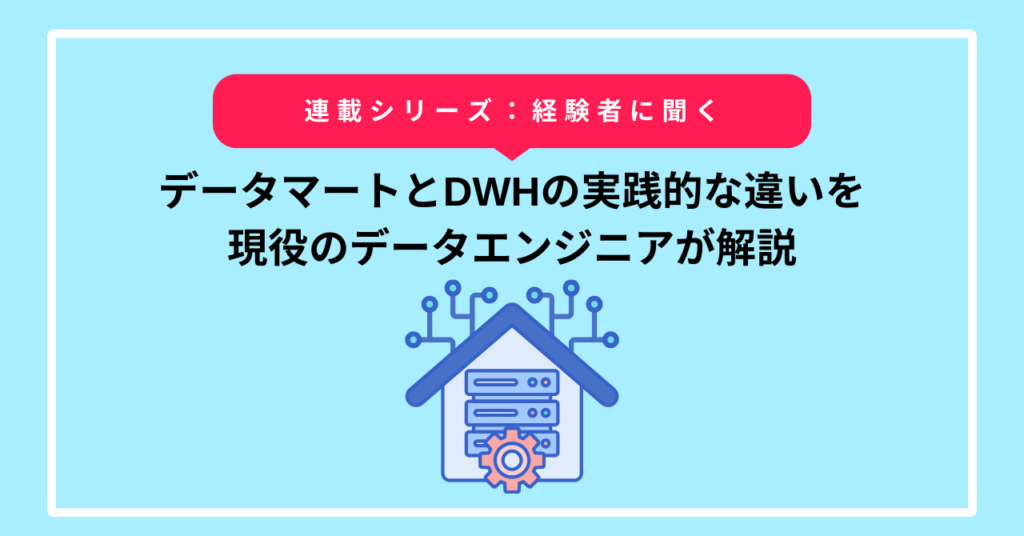


-13-1-300x157.png)








