古代から現代に至るまで、いつの時代にもエンジニアは存在してきました。エンジニアのいなかった時代はありません。しかし時代によって、求められるエンジニア像は変わってきています。ITエンジニアは現代が求めるエンジニアです。
「今後はどのようなエンジニアが時代のニーズにマッチするのか?」これを読み解くための指標のひとつが、教育の変化を把握することです。教育の変化が社会の変化を映している可能性もあります。特に大学入学共通テストはその時代を映す鏡のように、時代とともに傾向が変わっていきます。
ITエンジニアに限らず、これからの時代の社会が求める人材を知るために大学入学共通テストの問題を解析してみました。

ライター:青田ちひろ
エンジニア出身のキャリアカウンセラー。理系の大学院修士課程を修了後、電機メーカーに20年以上勤務。職業訓練校にて、求職者ならびに在職者のエンジニアに対して、セミナー講師を務める。エンジニアを取り巻く環境を考慮し、様々な視点からエンジニアとしてのあり方をレクチャーする。キャリアコンサルティング技能士、2級ワープロ技士、表計算技士、色彩検定、色彩講師、アロマテラピーインストラクター等、多彩な技能を持つ。

ナレッジコラムシリーズ
大学入学共通テストは社会の変化を映す鏡
大学入学共通テストは、ただの受験の通過点ではありません。そこには「今の社会が若者にどんな力を求めているか」が色濃く反映されています。近年は特に、「知識を持っているか」ではなく「課題を読み取り、判断し、他者に説明できるか」を問う出題傾向が強まってきました。これは高校生だけでなく、今まさに働く私たちにも無関係ではありません。
なぜなら、テストが変わるということは、5年後、10年後に社会に出てくる人材の「当たり前」が変わるということ。そしてその“当たり前”が、チームに合流してきた若手の価値観として、私たちの日常に入り込んできます。
つまり、教育の変化はゆるやかに、でも確実に、エンジニアの採用や評価の基準も動かしていくのです。
こうした前提のもと、今の共通テストでは何が問われているのか。ここからは、文系・理系を問わず浮かび上がる「データ活用力の重視」に注目し、その背景と現場への示唆を読み解いていきます。
共通テストに見る、これからの社会が求める力
大学入学共通テストの出題傾向からは、「これからの社会がどんな力を若者に求めているか」が見えてきます。特に近年、あらゆる教科で次の2つの能力が強く問われるようになってきました。それが「データ活用力」です。これは決して高校生だけの話ではなく、私たち社会人、特にITエンジニアにも無関係ではありません。
文系でも当然のように求められる「データを読む力」
特筆すべきは、暗記科目と見なされがちだった「日本史」や「地理」においても、グラフや表を前提とした読解型の出題が明らかに増えている点です。
たとえば日本史では、明治期の産業構造における日本・イギリス・スペインの違いを折れ線グラフから読み取り、それをもとに背景を考察させる設問が登場しています。複数国のデータを比較し、その関係性や意味を導き出す力が問われているのです。
地理では、人口推移、貿易量、自然災害の被害規模などの統計資料を分析させる問題が中心になりつつあります。もはや「知っていれば解ける」というアプローチでは通用しない設計です。
こうした出題の広がりは、知識偏重の学力観から「情報を読み解き、論理的に考える力」へと重心が移りつつあることを示しています。いまやデータリテラシーは、教科を超えて機能する“思考の土台”として、高校教育の中に根付き始めていると言えるでしょう。
理系では“実務に直結する”統計・波形・情報活用
数学の出題構成を見ても、データ分析の重要性は明らかです。2025年の共通テストでは、数学I・Aの約4割が確率・統計に関する問題でした。常用対数表や正規分布表が配布されるなど、実務での分析に近い形式です。
また、物理ではオシロスコープの波形やパルス、正弦波などが登場し、測定値から意味を読み取る力が問われる傾向にあります。単に計算できるだけではなく、実際にどう活用するかが重視されているのです。
象徴的な例として、ネット上では公園の噴水を題材にした放物線の問題が話題になりました。二次関数をもとに水の軌道を計算する出題で、単なる公式暗記ではなく「現象をどうモデル化し、意味ある結論を導くか」が問われていたのです。
さらに、2025年から新設された「情報」科目では、プログラムやデータ構造、ネットワークなどを扱いながら、データを扱う前提知識と活用能力そのものがテストされるようになりました。このように、データリテラシーは文理問わず“全員が持っているべき力”へと変化しているのです。
ITエンジニアに求められるスキルも変化している
教育現場で問われている「データ活用力」は、実は今のITエンジニアにも欠かせないスキルです。開発や運用の現場では、数値を根拠にした意思決定や、論理的な課題整理が求められるようになっています。
たとえば「どの機能を改善すべきか」といった判断も、ログデータや利用動向の分析結果をもとに行われるのが当たり前になってきました。A/BテストやKPIのモニタリングも含めて、“勘や経験”に頼らない改善プロセスを回せるかが、技術者としての信頼にもつながります。
現場でも広がる「数値起点」の意思決定
開発現場やグロースチームでは、施策の優先順位やプロダクト改善の判断を「数値を根拠に説明できるかどうか」が重視される場面が増えています。なかでも、SQLでの簡単な集計やBIツールでの可視化を通じて、自ら仮説検証まで行えるエンジニアは、より上流の議論にもスムーズに関与しやすくなっています。
もちろん、必ずしも全員がデータ分析の専門家である必要はありません。ただ、「データを見る習慣があるか」「施策や提案に数値的な裏付けを持てるか」は、日常のやりとりや意思決定のスピードに大きく影響します。
ログの設計やダッシュボードの更新といった地道な業務も、チーム内での動きやすさや信頼構築につながる重要な要素です。いまやデータは、開発チーム全体にとっての共通言語になりつつあります。


「ツールを動かせる」だけでは不十分に
ただし、ツールを扱えるだけでは一歩先の貢献にはつながりません。BIツールやSQL、可視化されたダッシュボードの活用が広がるなかで重要なのは、「その数値が何を意味するのか」を読み取れる力です。
たとえば、「なぜこの集計方法を選んだのか」「その結果はどれほど信頼できるのか」といった問いに答えられるエンジニアは、議論の場でより強い説得力を持ちます。これは操作スキルではなく、統計やデータ設計に対する理解があってこそ得られる視点です。
実際、共通テストでも出題されている正規分布・偏差・割合といった基本的な統計の概念は、現場で数値の“使い方”を考えるうえで欠かせない基礎知識です。数式を並べるよりも前に、「この数字をどう読むか」という姿勢こそ、データ活用の本質だと言えるでしょう。
これからのエンジニアに求められるスキル
共通テストの出題傾向から見えてきたのは、「知っている」だけではなく「使える」力の重視です。併せて、近年ITエンジニアに求められるスキルは「実装力」だけでは語れなくなってきています。
技術とビジネスの橋渡しを担い、データをもとに自ら判断し、改善に関わる力が問われています。ここでは、これからのエンジニアに必要とされる3つの観点を解説します。
プログラミング × 分析 のハイブリッド化
最近では、実装した機能の“使われ方”を観察し、ユーザー行動を踏まえて次の打ち手を考えられるエンジニアが、プロダクト全体の信頼を得るようになっています。
たとえば、SaaSプロダクトの開発現場では、「新機能の利用率が想定より低い」といった課題に対し、単に「UIを直してみよう」とあたりをつけるのではなく、「直近30日での利用頻度分布」「離脱ポイントのヒートマップ」などの定量データを自ら抽出し、仮説と照らして原因を探る、という動きが必要とされます。
SQLで自らユーザーテーブルをJOINして、セグメントごとに比較してみる。Google AnalyticsやBigQueryの数字を週次レポートとしてまとめ、PdMやデザイナーと改善案をすり合わせる。こうしたアプローチができるエンジニアは、仕様策定段階でも議論の中核に入りやすくなります。
開発スキルと分析スキルを横断的に持つことで、実装だけでなく「プロダクトの成長」に貢献できる立場に変わるのです。
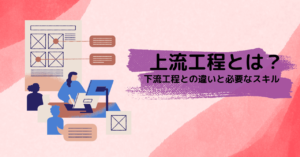
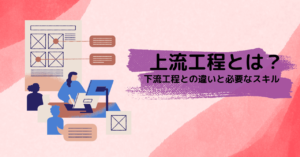
統計知識が “設計” や “評価” の共通言語に
A/Bテストの結果をどう評価するか、KPIの上下が本当に有意なのか。こうした場面では、統計知識があるかどうかがそのまま発言の説得力に直結します。
たとえば、「新しいサインアップ導線を試した結果、CVRが1.4%から1.6%に上がった」と聞いたとき、それが偶然か有意な差かを判断するには、統計的な検定や標準偏差の考え方が必要です。p値を理解しないまま「増えました!」と報告しても、意思決定の材料としては弱いのです。
また、障害対応の現場でも、「平均応答時間が300msを超えた」→「ピーク時の95パーセンタイルで見ると500ms近い」など、状況を説明する際の切り口に統計的視点が求められます。
設計でも「どこまでモニタリング対象にするか」「異常をどの閾値で検出するか」など、定量的な根拠が設計に埋め込まれるようになっており、統計はコードの外でも通用する“共通言語”になっているのです。
AI・クラウドといった技術の変化に向き合う姿勢
日々進化するクラウド環境やAIツールに対して、「わからないから触らない」という姿勢では、役割が限定されてしまいます。
たとえばインフラ領域では、TerraformやCloudFormationといったIaCツールが標準化され、環境構築や変更管理をコードで扱うのが当たり前になっています。フロントエンドエンジニアであっても、CI/CDやAPI Gatewayの設定を理解していないと開発がスムーズに進まないケースが増えています。
また、ChatGPTやGeminiのような生成AIを活用したドキュメント生成やコード補完なども、活用できる人とできない人の生産性には明確な差が出始めています。たとえばAI APIを使った機能実装時、「入力プロンプト設計をどうするか」「レスポンスにどこまで信頼を置くか」といった判断には、AIへの理解と実装上の経験が不可欠です。
新しい技術が出てきたとき、「まず触ってみる」「PoCとして試してみる」そうした初動の早さこそが、長く求められるエンジニアの共通項と言えます。
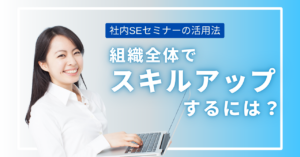
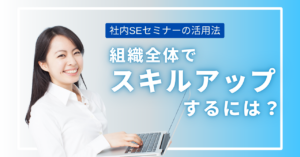
今後、特に重要になるスキル領域
以下、今後のITエンジニアにとって重視されるスキル領域を、実務との接点を意識しながら簡潔に整理しました。
・プログラミングスキル + データリテラシー
コードを書くだけでなく、ログや指標をもとに機能改善・障害対応ができるエンジニアは重宝されます。
特にSQLやBigQuery、LookerなどのBIツールを扱えると、開発と分析の垣根を越えて動ける存在になれます。
・確率・統計の基礎理解
A/Bテストの設計、KPIの異常検知、ユーザー行動の相関分析など、日常業務の中でも統計の知識は求められています。正規分布や信頼区間といった基本用語を理解し、分析結果の意味合いや信頼性を判断できることが重要です。
・クラウド・AIを含む技術の変化に適応する力
クラウドインフラ(例:AWS/GCP)や生成AIのAPIを使った機能開発が急増しています。環境構築やマネージドサービスの選定、AIとの責任分界点など、最新技術の運用を自ら試しながら吸収できる姿勢が評価されています。
どの手段が本当に必要か、再現性あるやり方かを言語化できる力は、設計レビューや施策選定の場面で求められます。単なる「技術の知識」ではなく、「文脈を読み取った技術選定」ができる人材こそ、上流にも呼ばれる存在です。
社内SEの求人なら社内SE転職ナビ


この記事を読んで「これからの時代に合ったエンジニアを目指したい」と感じた方には、社内SE転職ナビの活用をおすすめします。10,000件以上の豊富な求人の中から、あなたのスキルや志向に合ったポジションを厳選して提案。
技術力に加え、データ活用やユーザー視点を大切にする企業とも多くつながっています。転職後の定着率は96.5%と高く、キャリアの棚卸しから面接対策まで徹底サポート。時代が求める社内エンジニアとして、次のステップを一緒に描いてみませんか?
まとめ
大学入学共通テストの出題傾向は、データを扱う力が文理を問わず求められる時代になったことを示しています。これは教育だけでなく、実務の現場でもすでに当たり前になりつつある変化です。
ITエンジニアにとっても、技術力に加えて、データから課題を発見し、改善につなげる力がますます重視されています。単に実装するだけでなく、数値を根拠に判断し、チームや事業に貢献できる力が問われているのです。
これからのエンジニアには、プログラミングスキルだけでなく、データリテラシーや統計の理解、そして実務視点での思考力が求められます。技術と論理を土台に、意味のある提案ができる人材が、これから評価されていくでしょう。


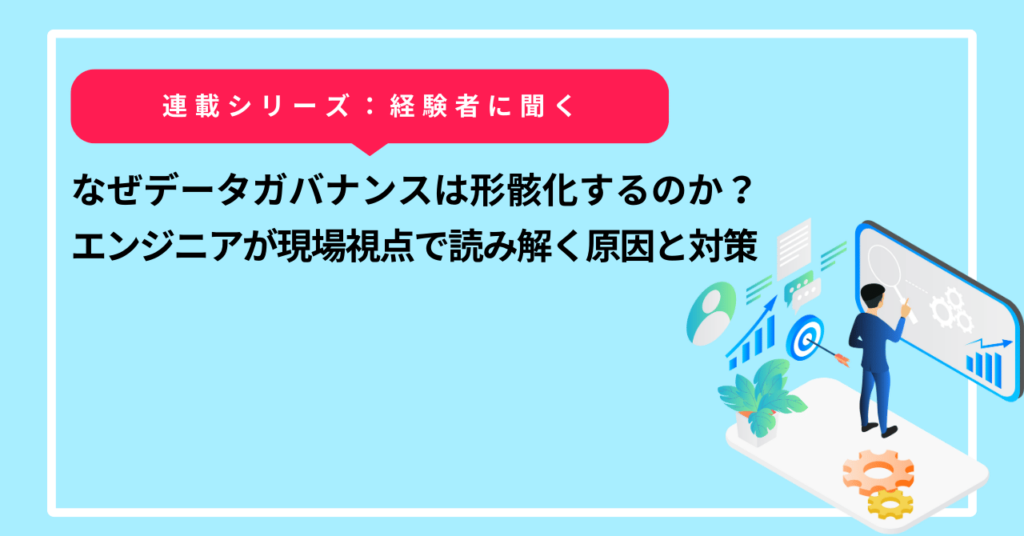

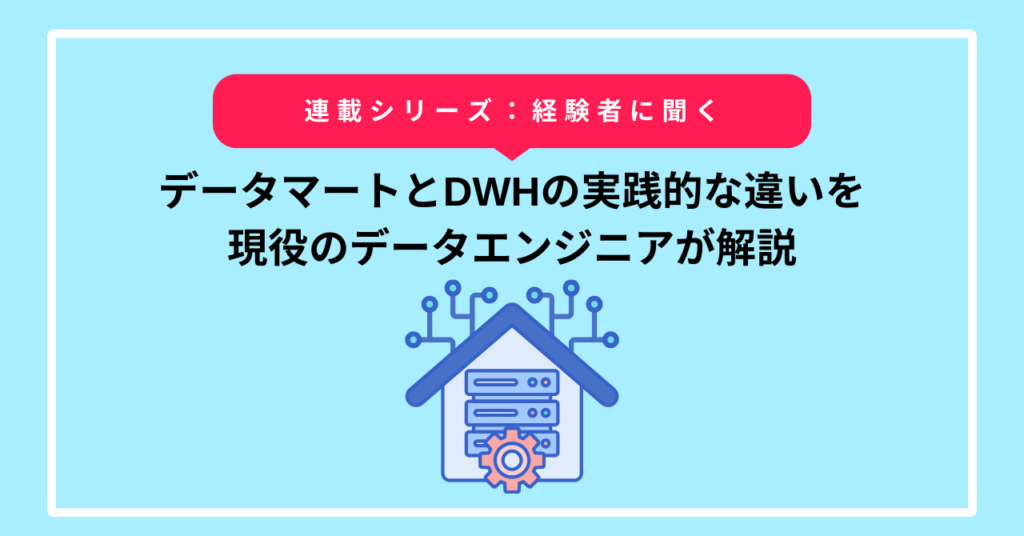



-13-1-300x157.png)







