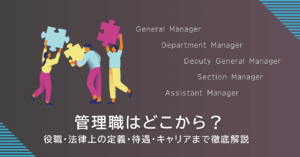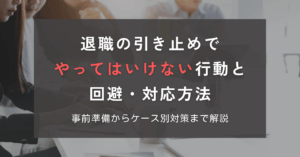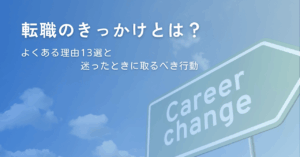「転職活動を進める中で、自分の転職の軸が定まらず迷っている」「面接で転職の軸を聞かれたときの答え方がわからない」
このような悩みを抱えている方も少なくないと思います。
転職の軸とは、転職活動において自分が重視する価値観や求める条件を指します。自分の軸をはっきりさせることで、ミスマッチを防ぎ、後悔のない転職が実現しやすくなるでしょう。
本記事では、転職の軸の作り方から面接での答え方、実際の回答例まで丁寧に解説します。記事を読むことで、転職の軸をはっきりさせ、企業選びや面接対策をスムーズに進められるようになるでしょう。ぜひ最後まで読んで、あなたの転職活動に役立ててください。
【この記事のポイント】
- 転職の軸=「自分が重視する価値観や条件」、転職理由との違いは「過去」か「未来」か
- 軸があると企業選び・面接でブレない
- 見つけ方は「過去の不満」「強み」「市場動向」から整理
- 面接では価値観ベースで伝えるのがコツ

転職の軸とは
転職の軸とは、転職を考える際に自分が最も重視する価値観などこれだけは満たしたい条件のことです。例えば、「年収アップ」「ワークライフバランスの向上」「スキルアップ」などが挙げられます。
IT業界では特に、使用する技術や開発手法、リモートワークの可否、チーム構成など、他業種とは異なる特有の軸が存在します。例えば「クラウド技術を中心に扱える環境で働きたい」「アジャイル開発を実践している組織で経験を積みたい」といった技術的な軸が重要になることも少なくありません。
このような転職の軸をはっきりさせることで、応募企業の選定基準が定まり、転職後のミスマッチを防げます。転職の軸が定まっていないと、内定が出ても決断に迷い、入社後に「想像していた環境と違った」と後悔する可能性もあるでしょう。
転職市場では、企業ごとに求めるスキルや待遇、働き方が異なります。そのため、転職活動を始める前に「どのような職場で働きたいのか」「何を優先すべきか」を明確にすることが重要です。
転職理由との違い
転職理由と転職の軸は、一見似ていますが異なる概念です。転職理由は「なぜ現在の職場を辞めたいのか」という過去の出来事を指し、転職の軸は「転職先で何を実現したいのか」という未来に焦点を当てた考え方です。
例えば、「残業が多く、プライベートの時間が取れない」というのは転職理由に当たります。一方で、「ワークライフバランスを大切にできる環境で働きたい」というのが転職の軸です。この違いを意識することで、面接時の回答も前向きなものになり、企業側に好印象を与えられます。
例えば、「レガシーシステムしか扱えない環境が不満」という転職理由があれば、「クラウドネイティブな開発環境で最新技術に触れながら市場価値を高めたい」という軸に昇華させることで、ポジティブな印象を与えられます。
転職の軸を持たずに転職活動を進めると、「今の職場を辞めたい」という理由だけで企業を選びがちです。しかし、それでは転職後も同じ不満を抱える可能性が高くなります。理想の職場環境を手に入れるためには、「なぜ辞めたいのか」ではなく、「どのような環境で働きたいのか」を意識して転職活動を進めることが大切です。
就活の軸との違い
就職活動と転職活動では、軸の考え方に違いがあります。就活の軸は、社会人経験がない学生が企業選びをする際に基準とするもので、「目の前の人を直接幸せにできる仕事がしたい」「研究分野を活かせる会社に入りたい」といった抽象的なものが多いです。
これは、新卒採用がポテンシャル採用であり、配属先が決まっていないことが多いため、具体的な職務内容よりも企業のビジョンや社風を重視する傾向があるからです。
一方、転職の軸は、これまでの職務経験やスキルをもとに、より具体的な視点で設定されます。転職活動では、「この企業でどのように自分のスキルを活かせるのか」「今の職場と比較して、どのような点に魅力を感じるのか」を説明する必要があります。
そのため、「年収を上げたい」「開発リーダーとしてマネジメント経験を積みたい」など、具体的なキャリアプランを軸にすることが重要です。
面接では、企業の採用担当者が「なぜこの会社を選んだのか」を重視します。就活と違い、転職では「なぜ他の企業ではなく、当社を選んだのか」を説明する必要があるため、転職の軸を明確にし、自分のキャリアビジョンと応募企業の方向性が一致していることを伝えることが大切です。
転職の軸が重要と言われている理由
転職の軸をはっきりさせることは、IT業界での転職成功において非常に重要です。軸が定まっていることで、企業選びから面接対策、そして入社後の適応まで、一貫性を持って転職活動を進められます。
特にIT業界では、企業ごとに技術や環境が大きく異なるため、自分の譲れない条件を事前に整理することで、ミスマッチを防ぎ、長期的な満足度を高められるでしょう。ここでは、転職の軸を持つことの重要性について、3つの側面から詳しく見ていきましょう。
- 企業選びでミスマッチしない
- 面接の回答準備にもつながる
- 自分の価値観がわかる
企業選びでミスマッチしない
転職の軸をはっきりさせることは、自分の価値観や希望に合った企業の効率的な選択に繋がります。例えば、「最新のクラウド技術に携わりたい」という軸があれば、AWSやAzureを積極的に導入している企業に絞って応募できます。
また、「ワークライフバランスを重視したい」という軸があれば、残業時間の少ない企業やフルリモートワークを採用している企業を優先的に検討できるでしょう。
軸が定まっていないまま転職活動を進めると、給与や立地など表面的な条件だけで企業を選んでしまうでしょう。そのような場合、入社後に「思っていた技術環境と違った」「開発文化が自分に合わない」といったミスマッチを感じる可能性が高くなります。
転職の軸をはっきりさせることで、こうしたミスマッチのリスクを大幅に減らせます。軸を持つことは、単なる企業選びの効率化ではなく、転職後の満足度や定着率を高めるためにも大きな意味があるのです。
面接の回答準備にもつながる
転職の軸が明確であれば、面接での受け答えに一貫性を持たせることができます。企業は応募者の「考えの有無」を見ているだけではありません。その人がどんな価値観を持ち、どんな環境で力を発揮できるのか、そしてそれが自社の方向性や文化とマッチしているかを見極めようとしています。
たとえば「自分の手でプロダクトを育てていきたい」という軸を持っている人が、「上流から関われる環境」「長期的にサービス改善に関わる体制」を求めていると話せば、それは単なる志望動機ではなく、本人の価値観と企業の姿勢がどこで重なるかを示す材料になります。
逆に、軸が曖昧なままだと、選考の場で「なぜこの会社を選んだのか?」「この人は何を大事にして働いてきたのか?」といった本質的な問いにうまく答えられず、企業側からも「文化や方向性が合うかどうか判断できない」という印象を持たれる可能性があります。
面接で軸を語ることは、単に「筋が通った話をする」ことではなく、相手に「あなたと一緒に働く意味がある」と感じさせるための対話なのです。
 エージェント・Matsumoto
エージェント・Matsumoto面接では「一貫性」も重要です。企業ごとに話を変えるのではなく、共通する自分の軸を語れるよう、言語化しておきましょう。
自分の価値観がわかる
転職の軸を見直すことで、仕事において自分が何を重視しているのか、どのような環境で働くことが理想的か再確認できます。転職はただの会社選びではなく、今後のキャリアや働き方を考える大きな転機です。
例えば、「スキルアップの機会を重視したい」という軸があれば、教育制度が整っている企業や技術的チャレンジができる現場を候補にすることで、満足度の高い転職につながります。こうして転職の軸を深掘りしていくことで、自然と自分の価値観や人生観までクリアになるでしょう。
IIT業界は特に選択肢が多様で、技術志向からビジネス志向まで、さまざまなキャリアパスが存在します。価値観が明確になることで、選考過程でも自信を持って判断でき、結果として納得のいく転職が実現します。転職の軸は、企業選びのためだけでなく、自分自身の将来像を描くための大切なヒントになるのです。
転職の軸の見つけ方
転職活動を成功させるためには、転職の軸をはっきりさせておくことが不可欠です。なぜなら、軸が定まっていないと企業選びや面接対策に一貫性がなくなり、結果としてミスマッチを招くリスクが高まるからです。
転職の軸は、これまでの経験や働き方に対する考え方、自分が今後どのようなキャリアを描いていきたいかをベースに作っていきます。そのため、過去と未来の両方をしっかりと見つめ直すことが大切です。
ここでは、転職の軸を作るために必要なステップを4つの視点から紹介します。順を追って整理することで、誰でも納得感のある軸を見出せるはずです。
- 転職理由を明確にする
- 転職理由に優先順位をつける
- 転職希望先の市場動向を調べる
- 転職の軸を具体的に考える
①転職理由を明確にする
転職の軸を作る第一歩は、なぜ転職したいのか明らかにすることです。これは過去を振り返り、自分が職場で何に不満を感じ、どこに課題を感じているかを洗い出す作業でもあります。
例えば、「評価制度が不透明で成果が正当に認められない」「裁量が少なく、やりがいを感じられない」「働き方に柔軟性がない」といった思いがあるかもしれません。こうした不満をリストアップしていくと、自分が職場に何を求めているのか、自然と見えてきます。
不満やモヤモヤを書き出すことは、ネガティブに聞こえるかもしれませんが、自分の希望を逆算的に探る上で非常に有効です。「上司との関係がうまくいかない」→「自律的に働ける環境が欲しい」といったように、現状の“違和感”が次の職場に求める条件を浮かび上がらせる材料になります。
このように、自分の過去の不満や希望を言語化することで、転職活動の軸を考えるうえでの出発点ができます。今後の職場に何を期待したいのかを明確にすることが、軸作りの第一歩となるのです。
- 日々の業務で何に違和感を感じているか?
- 今の働き方と、理想のキャリアにどんなギャップがあるか?
②転職理由に優先順位をつける
転職の理由を洗い出したら、それぞれに優先順位をつけることが大切です。すべての条件を満たす企業はなかなか存在しないため、どの条件を最も重視するかを決めておく必要があるからです。「絶対に譲れない条件」と「あれば嬉しいが妥協できる条件」を区別するのが良いでしょう。
例えば、「テレワーク可能な環境で働きたい」「今よりも年収を上げたい」「チームでの開発に携わりたい」といった複数の要望があった場合、それらをすべて重視すると選択肢が極端に狭まってしまいます。しかし、「スキルアップを最優先し、年収は現状維持でも構わない」といったように優先度を決めておくと、選択肢の幅を広く保ちながらも自分に合った企業を見つけやすくなります。
このように、条件に優先順位をつけることで、企業選びが効率的になり、結果的に納得度の高い転職を実現しやすくなるのです。
- 「絶対に譲れない条件」と「妥協できる条件」を区別できているか?
- あとから取り戻せる条件、今のフェーズで優先すべき条件を整理できているか?
③転職希望先の市場動向を調べる
転職の軸を現実的にするためには、業界や職種の市場動向を調べておくことが重要です。自分の希望が今の市場で通用するのか、どのようなスキルが求められているのかを把握しないまま軸を作ると、実現困難な転職目標を掲げてしまうリスクがあるからです。
例えば、「AIや機械学習の分野で働きたい」と考えているなら、どの企業が積極的に採用を行っているか、どのような開発経験やスキルが求められているのかを事前に調査する必要があります。業界動向や求人傾向を理解しておけば、現実と理想のギャップを埋められ、実現性のある転職の軸を作れます。
こうした情報は、求人サイトや業界レポート、転職エージェントの情報などから収集するのが効果的です。市場の状況を踏まえた軸の構築で、採用されやすく、満足度の高い転職が目指せるでしょう。
- 希望している職種やスキルが、今の市場でどれくらいニーズがあるか?
- 自分の経験やスキルで、どの程度実現可能か?
④転職の軸を具体的に考える
転職の軸を言語化する際には、できるだけ具体的な表現を用いることが大切です。なぜなら、抽象的な軸は企業側にとって伝わりづらく、面接でも説得力が欠けてしまうためです。
例えば、「新しい技術に挑戦したい」と漠然と伝えるよりも、「Go言語を使ったWebアプリ開発に携わりたい」「CI/CD環境を構築できるインフラ案件に関わりたい」といったように、具体的なスキルや業務内容を挙げたほうが、説得力があります。具体性があることで、企業も「この人は自社の業務にマッチしそうか」判断しやすくなります。
また、転職の軸を明確にしておくことで、求人の見極めや応募先の絞り込みもスムーズです。自分の希望と合致する企業を探す効率が上がり、結果として面接の通過率や内定後の満足度も高まるでしょう。
- やりたいこと・関わりたい技術・理想の働き方を具体的に言えるか?
- 「技術 × 役割 × 働き方」のように複数の視点で整理できているか?
転職の軸が思いつかない時の対処法
転職活動を始めたものの、「自分の転職の軸がよく分からない」と悩む方は少なくありません。特にIT業界では選択肢が多いため、自分が何を大切にしているかを見失いやすい傾向があります。
しかし、軸がないままでは企業選びも面接対策も不透明なものとなり、結果としてミスマッチの可能性が高まります。
ここからは、転職の軸が思いつかないときに試したい具体的な方法を3つ紹介します。これらのアプローチを通じて、自分らしい軸を見つけるヒントが得られるはずです。
- 現職の不満から考える
- 自分の強みから考える
- Will Can Must の法則で考える
現職の不満から考える
転職の軸を見つける際は、まず現職で感じている不満を振り返ることが効果的です。なぜなら、今の職場で満たされていない点こそが、次に求める環境を示すヒントになるからです。
例えば、「上司の評価基準が曖昧で納得できない」「毎日同じ作業ばかりでやりがいを感じられない」など、働く中で感じているストレスや違和感を具体的に書き出してみましょう。そうすることで、「公平な評価制度がある会社がいい」「新しいことに挑戦できる環境が必要」といった、自分にとっての重要な軸が見えてきます。
このように不満をポジティブに転換し、理想の働き方を探ることは、転職軸の発見に繋がります。今あるネガティブな感情を放置せず、軸作りの材料としての活用が大切です。



「不満をそのまま話していいのか」と心配される方もいますが、実は不満は次のキャリアを考える大きなヒントになります。大切なのは「不満をどう前向きに変換するか」であり、ここを整理すると面接の説得力も高まります。
自分の強みから考える
自分の強みや得意分野を活かせる環境を探ることも、転職の軸を定める上で非常に有効な方法です。まずは自分のスキルや経験、性格的な強みを客観的に分析してみましょう。
例えば「チームでの開発作業が得意である」「フロントエンド開発に関する深い知識がある」「新しい技術の習得が早い」「コミュニケーション能力が高く、顧客との折衝がスムーズにできる」といった点です。
これらの強みを最大限に活かせる環境はどのようなものか考えてみましょう。チーム開発が得意なら、アジャイル開発を重視している企業や、チームワークを大切にする社風の会社が合っているかもしれません。フロントエンド開発が得意なら、ユーザー体験を重視するサービスを展開する企業が自分の技術力を活かせる場所かもしれません。
自己分析を通じて自分が最も活躍できる環境を見極めることで、単なる条件面だけではなく、本当に自分が力を発揮できる転職先を選ぶ基準ができます。IT業界では特に、技術スタックや開発手法、プロジェクト規模など、自分の強みと相性のよい環境を見つけることが、長期的なキャリア構築につながります。
Will Can Must の法則で考える
Will(やりたいこと)、Can(できること)、Must(やるべきこと)という3つの視点から自分のキャリアを整理する「Will Can Must の法則」は、転職の軸を考える上で非常に効果的なフレームワークです。
-4-1024x536.png)
-4-1024x536.png)
まず「Will」は自分が本当にやりたいことを表します。例えば「AI開発に携わりたい」「グローバルなプロジェクトに参加したい」「自社サービスの開発に関わりたい」といった、情熱を注げる分野です。
次に「Can」は自分の持つスキルや強みを指します。「Pythonが得意」「クラウドインフラの構築経験が豊富」「UI/UXデザインのセンスがある」など、現時点で提供できる価値です。
最後に「Must」は市場ニーズや将来性を考慮した、キャリア形成上必要な要素です。「将来性のある技術を学ぶべき」「業界知識を深めるべき」「マネジメントスキルを身につけるべき」といった点が含まれます。
これら3つの要素が重なる部分が、あなたにとって最適な転職の方向性となるでしょう。
例えば「AI開発に携わりたい(Will)」「Pythonプログラミングが得意(Can)」「データサイエンスの知識を深めるべき(Must)」と整理したとします。その場合、AI関連の開発プロジェクトがある企業を軸に転職活動を進めるといった具体的な方向性が見えてくるでしょう。
面接での転職の軸の答え方
面接では、「なぜ当社を志望されたのですか?」「転職先に求めていることは何ですか?」といった形で、あなたの“転職の軸”を探る質問が必ず出てきます。これは企業が、あなたの価値観や方向性が自社とフィットしているかを見極めるための重要な問いです。
だからこそ、ただの志望動機ではなく、「自分がどんな環境で力を発揮できるのか」「どんな働き方にこだわりたいのか」など、自分の判断軸を率直に言語化することが求められます。次のようなポイントを大切にして答えましょう。
① 「条件」ではなく「価値観」で語る
NG:「フルリモート希望です」「年収を上げたいです」
OK:「自律的に働ける環境でアウトプットに集中したい」「成果に見合った評価を得られる環境で挑戦したい」
→ 単なる条件の羅列では、企業との関係性が見えてきません。“なぜその条件を重視するのか”という背景にある価値観までセットで語ることが鍵です。
② 自分だけのストーリーになっているか
企業は「軸がある人」を探しているのではなく、「その軸がどんな経験から生まれたか」を知りたがっています。
「今の会社では技術選定に関われないことに違和感があった」
「チームの空気が受け身で、もっと提案できる環境に行きたくなった」
こうした経験ベースの話が入ることで、軸の説得力と信頼性が一気に増します。
③ 志望企業と重なる部分をちゃんと伝える
自分の軸がどんなに立派でも、その会社で実現できるイメージが伝わらなければ、評価にはつながりません。
「自律性を重視したい」という軸があるなら「貴社が取り入れているスクラム開発では、各メンバーが企画段階から関われる点に強く惹かれました」など、企業の特徴と自分の軸がどう接続するかを明確に伝えることが大切です。



面接官は「この人の軸は当社で叶えられるのか?」を見ています。ですから、自分の軸と企業の特徴を必ずつなげて話すことが重要です。私たちも求人を提案する際には、候補者の軸に合致する部分を一緒に確認しています。
転職の軸は「正解を言う」ための時間ではない
面接で軸を話すとき、かしこまって“好印象”を取りに行こうとする人は多いですが、採用担当者が見ているのはそこではありません。あなたの判断軸がどこにあるのか。それが自社とズレていないか。その確認のために聞かれている、という視点を忘れないことが重要です。
だからこそ、ありきたりな正解ではなく、「自分はこういう働き方がしたい」「こういう状況では力を発揮できない」といった本音ベースの軸のほうが、結果として信頼されます。



理想の職場を見つけるためには、「辞めたい理由」を並べるのではなく、「どんな環境であれば成長でき、安心して働けるか」を基準に考えることが大切です。
【IT転職者向け】転職の軸の回答例
IT転職の面接では、「転職の軸」について具体的に聞かれるケースが多くあります。その際、あらかじめ自分の軸を整理し、説得力のある伝え方ができるかどうかが合否を左右します。特にIT業界では、技術力だけでなく、仕事に対する姿勢や価値観も重視されるため、自分がどのような目的で転職を考えているのかを明確に伝えることが重要です。
ここでは、実際の面接でも活用できる転職の軸の回答例を5つ紹介します。
技術志向「最新技術に挑戦したい」
IT業界で働く多くの方が「最新技術に関わる仕事がしたい」と考えているのではないでしょうか。しかし、面接でこの軸を伝える際には、どの技術分野に興味があり、なぜその分野で働きたいのかを具体的に伝えることが重要です。
こんな人向け
・保守業務から抜け出したい
・AI、機械学習、クラウドなどに関心がある
・変化を楽しみたいタイプ
【最新技術に挑戦したい場合の答え方例】
私の転職の軸は、AIや機械学習といった最新技術に携わることです。現職は基幹システムの保守が中心で、新しい技術に触れる機会が限られています。日々の業務の中で、技術の進化スピードに取り残されている実感がありました。エンジニアとして成長を続けるには、変化の早い分野での経験が必要だと考えています。御社は自然言語処理や生成AIを活用した開発を推進されており、まさに成長機会がある環境だと感じました。
スキル活用志向「特定の技術力を活かしたい」
これまで積み重ねてきた技術を活かしたいという軸は、即戦力としてのアピールにつながるため面接官の関心も高くなります。重要なのは、自分の得意分野を具体的に示したうえで、どのような形で会社に貢献したいのかまで言及することです。
こんな人向け
・明確な得意技術がある(例:Python、インフラ、自動化など)
・即戦力としてアピールしたい
・スペシャリスト志向に近い
【特定の技術力を活かしたい場合の答え方例】
転職において重視しているのは、自分の得意分野で即戦力として貢献できるかどうかです。私はPythonを使ったデータ処理や業務自動化の経験があり、前職では社内の可視化ツールを構築しました。今後は、こうしたスキルをプロダクト開発やサービス改善にも活かしたいと考えています。貴社のデータドリブンな開発方針は、まさに自分が力を発揮できる領域だと思い、応募いたしました。
働き方志向:「自分に合った環境で生産性を上げたい」
働き方や環境を重視する転職軸は、現在のライフスタイルや生産性向上への意識と直結しており、面接でも共感を得やすいテーマです。ただし「働きやすさ」だけを強調すると消極的な印象を与えることがあるため、業務効率や成果につなげたい意図をセットで伝えることが大切です。
こんな人向け
・リモート・フレックスなど柔軟な働き方を求めている
・集中できる時間帯や場所を大切にしたい
・効率やアウトプット重視の働き方を志向している
【自分に合った環境で生産性を上げたい場合の答え方例】
私が転職で最も重視しているのは、自分の能力を最大限に発揮できる働き方と環境です。具体的には、リモートワークを活用したフレキシブルな勤務体制と、自律的に業務を進められる組織文化を求めています。実際に前職でリモート環境が一時的に導入された際、開発効率とコード品質がともに向上した経験があります。貴社が成果ベースで働き方を選べる文化を持っていることに共感し、自分のスタイルに合うと感じました。
キャリア転換志向「技術だけでなくビジネス視点も持ちたい」
エンジニアとして手を動かすだけでなく、「なぜこの機能を作るのか」「どうすればユーザーに届くのか」といった視点も持ちたいと感じていませんか?単に技術を追求するだけでなく、事業の成長やユーザー体験といった“その先”を見据えたキャリアを目指す人にとって、この軸は強い説得力を持ちます。
こんな人向け
・上流工程や企画にも関わりたい
・将来的にPMやPdMに進みたい
・開発だけでなく事業に貢献したい思いがある
【技術だけでなくビジネス視点も持ちたい場合の答え方例】
私の転職の軸は、エンジニアリングだけでなく、ビジネス視点でも価値を出せる環境に身を置くことです。技術的な課題だけでなく、顧客視点や事業成果を意識した開発に取り組みたいと考えるようになりました。現職では、仕様が決まった後の実装フェーズが多く、上流や企画に関わる機会がほとんどありません。御社はエンジニアがプロダクト戦略やKPI設計にも関与されていると伺い、まさに目指したい働き方だと感じました。
成長志向「長期視点でスキルを積みたい」
毎回異なる案件で経験を積むよりも、一つの領域にじっくり取り組み、着実にスキルを積み上げていきたいと考える方に適した軸です。自分のペースで学びながら、技術力だけでなく、業務知識やプロダクト理解も含めて深めていきたいという思いを持つ方にフィットします。
こんな人向け
・腰を据えてスキルを伸ばしたい
・一つの分野で専門性を深めたい
・短期的なプロジェクトの多さに違和感がある
【長期視点でスキルを積みたい場合の答え方例】
転職の軸として重視しているのは、腰を据えてスキルを伸ばせる環境があるかどうかです。私は継続的な学習を重視しており、一つの分野で専門性を深めながら、周辺領域にも広げていきたいと考えています。前職ではプロジェクトの入れ替わりが早く、習熟する前に次へ移ることが多く、課題を感じていました。御社のように中長期でプロダクトと向き合える環境で、技術力と業務理解を両立させていきたいです。
社内SEの求人なら社内SE転職ナビ


転職の軸がはっきりしてきたら、次に大事なのは「どんな環境でなら、その軸が叶えられるのか」を見極めることです。社内SE転職ナビは、ITエンジニアのための転職支援サイト。技術志向、働き方、キャリアパス──あなたの軸に合った求人を、業務内容まで丁寧に確認して提案します。
「自社内で腰を据えて開発に携わりたい」「ユーザーとの距離が近い現場で上流工程に関わりたい」「働きやすさとスキルアップ、どちらも両立したい」そんな希望にマッチする社内SE・情報システム部門の求人を多数掲載中。定着率96.5%と、転職後の満足度が高い点も魅力の一つです。まずはお気軽に相談ください。
まとめ
本記事では、IT転職者向けに転職の軸の作り方や面接での答え方について解説しました。
転職の軸とは、転職活動の基準となる価値観や希望条件のことを指します。これを明確にすることで、企業選びでのミスマッチを防ぎ、面接での説得力も増すというメリットがあります。
転職の軸を作る際には、転職理由を明確にし、優先順位をつけ、市場動向を踏まえて具体的な軸を考えることが重要です。また、転職の軸が思いつかない場合は、現職の不満や自分の強みを振り返ったり、「Will Can Must」のフレームワークを活用したりすることで、軸を見つけやすくなります。
IT業界は日々変化しており、転職市場も常に動いています。納得のいく転職を実現するためには、自分に合った企業を選び、面接での適切な自己アピールが大切です。