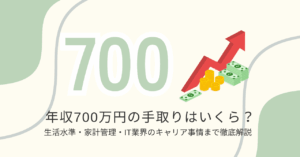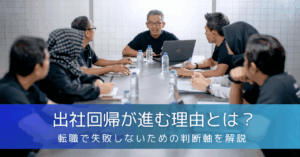「業務効率化のためにナレッジを整備したいけど、どうすればよいのか…」 「ナレッジを構築しても利用してもらえるんだろうか…」 とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
ナレッジの活用が業務効率化に重要だと聞いても、具体的にどうすればよいか分からず、漠然としたイメージしか持てない方も多いはず。
本記事では、ナレッジの重要性から具体的な作成方法、そして最大限に活用するための秘訣までを徹底解説します。ぜひこの記事を参考に、効果的なナレッジの管理と運用を実現してください。

ナレッジとは
企業などの組織内で蓄積・共有され、活用できる状態になっている知識や情報を「ナレッジ」と呼びます。これは、特定の顧客への対応方法や、過去のトラブル解決策など、業務遂行に役立つあらゆる知識を含みます。
これらの知識は、一部の社員の経験や勘に基づく「暗黙知」として、個人の頭の中に留まりがちでした。しかし、暗黙知のままでは知識の共有が難しいため、組織全体で共有することができず、人材の入れ替わりや部門間の連携を阻害する要因となります。
そこで求められるのが、「暗黙知」を「形式知」に変換することです。形式知とは、マニュアルやデータベースなど、誰でもアクセスできる形にまとめられた知識のこと。暗黙知を形式知に変換することで、組織全体の知識共有を促進し、業務効率化やミスの削減に繋げることができます。
特にコロナ禍以降、テレワークが普及し、社員間のコミュニケーションが制限されるようになった今、ナレッジの重要性はますます高まっています。直接対面して教わる機会が減った分、ナレッジを共有する仕組みを構築することが求められています。
ナレッジを活用するメリット
ナレッジを活用することで、会社全体の業績向上につなげることが可能です。
そのメリットは主に以下の3つに集約されます。
- 業務効率の改善につながる
- 属人化を防止できる
- 新人育成に活用できる
一つずつ見ていきましょう。
業務効率の改善につながる
ナレッジを活用することで、業務効率を大幅に改善することができます。
「去年起こったトラブルの解決方法が文書化されておらず、一から調べなくてはならなかった」といった経験はないでしょうか。あるいは、「頑張って仕上げた成果物が、すでに他の社員が作成していた」というような無駄な作業を経験された方もいるかもしれません。これらの問題は、社内のナレッジが適切に共有されていないことが原因の一つです。
ナレッジがない環境下では、社員一人ひとりが独自のやり方で業務を進め、ノウハウや作業の成果は個人の頭の中に留まりがちです。しかし、自己流に作成していた資料や、何度も同じことを繰り返し口頭で伝えていたことなどをナレッジ化することでこのような無駄を削減し、業務効率を大幅に改善することができます。

属人化を防止できる
特定の個人に業務が集中し、その人がいなくなると業務が滞ってしまう状態を「属人化」といいます。ナレッジの活用により属人化を防止し、組織全体の安定化を図ることができます。
例えば、特定の業務プロセスに精通した従業員が、経験やスキルをナレッジ化しないまま退職し、経験の少ない人が業務を引き継ぐ場合、業務効率が低下し、ミスやトラブルが発生する可能性は高いです。しかし、ナレッジを事前に蓄積し、共有する文化を整えておけば、スムーズに業務を遂行できるようになります。
新人育成に活用できる
ナレッジの蓄積は、新人育成の強力な武器になります。まず、業務に必要な知識やノウハウを体系的にまとめたナレッジを共有することで、新入社員や中途採用者は業務の手順をスムーズに理解し、短期間で戦力となることが期待できます。また、文書化されたナレッジは、新人がいつでもどこでも自分のペースで学べる教材となります。これにより、新人は効率的に知識を習得し、業務に早く適応できるようになります。
さらに、現役社員の経験や知識を体系化されたナレッジとして構築することで、新人研修ではナレッジの活用方法を教えるだけで、新人は自ら学習し、業務に適用できるようになります。つまり、ナレッジを活用することで、新人育成にかかる時間を大幅に削減し、会社全体の業務効率化に貢献できるのです。
効率的なナレッジ作成方法
ここからは、効率的なナレッジ作成方法について、代表的な方法を4つ紹介します。
- ドキュメント
- 社内Wiki
- FAQシステム
- チャットボット
それぞれの作成方法のメリット・デメリットの両面をあわせて解説していきますので、どの方法を取り入れるかの参考にしてみてください。
ドキュメント
ナレッジを蓄積・共有する方法として、ドキュメントの活用はシンプルながら効果的な手段です。WordやExcel、Googleドキュメント、Googleスプレッドシートなどのツールは、多くの人にとって馴染みがあり、導入のハードルが低いのが特徴です。
さらに、追加のコストがかからず、特別なスキルがなくても簡単に作成できるため、すぐに運用を始められるというメリットがあります。一方で、ドキュメント形式のナレッジ共有には、いくつかの注意点もあります。
まず、情報が増えるほど必要な内容を探しづらくなるという課題があります。また、誰でも手軽に作成できる反面、管理が煩雑になり、情報の整理に手間がかかることもデメリットとして挙げられます。
それでも、経験豊富な社員の知識やノウハウをドキュメントとして蓄積することは、組織全体のスキル向上につながる有効な手段です。活用しやすい仕組みを整え、適切に管理することで、ナレッジ共有の効果を最大化できます。
社内Wiki
社内Wikiとは、社員が自由に知識やノウハウを書き込むことができるツールです。社内Wikiを活用することで、ナレッジ作成者はツリー構造を簡単に作成でき、部署単位や施策単位で情報を体系化しやすくなります。
また、編集権限を付与すれば誰でも簡単に情報の追加や修正が可能となり、常に最新の情報を保つことができます。社内Wikiを利用する側も、キーワードで検索することで必要な情報にすぐにたどり着けます。
ただし、社内Wikiを構築するには初期コストがかかる点に注意が必要です。また、文字ベースの情報が多いため見づらい部分もあります。さらに、一定の記述ルールを設けないと情報が散逸しやすくなるという問題もあるでしょう。
とはいえ、社内Wikiは効率的にナレッジを蓄積し、共有するための非常に有効な手段です。適切に運用することで、社員全員が簡単にアクセスできる豊富なナレッジを構築でき、組織全体の業務効率化に貢献するでしょう。
FAQシステム
FAQシステムを活用して社内FAQを作成することは、効率的なナレッジの作成と共有に非常に有効です。社内FAQを作成することで、社員は業務中に生じる疑問を検索・参照するだけで、すぐに解決できるようになります。
さらに、FAQシステムでは文字だけでなく、図や動画も掲載できるため、視覚的に分かりやすい情報提供が可能です。FAQの作成者側もHTMLの知識がなくても編集ができ、直感的な操作でFAQの更新ができます。
一方で、FAQシステムの導入やFAQの作成には、ある程度の時間と手間がかかります。また、FAQサイトの専用の管理者がいない場合、情報の更新や管理が滞る可能性があります。そのため、FAQシステムを効果的に運用するためには、専任の管理者を置くことが望ましいでしょう。
社内FAQを適切に運用すれば、社員が自己解決できる力を養い、業務効率を大幅に向上させることが可能です。
チャットボット
チャットボットは、企業のナレッジ共有を革新する強力なツールです。あらかじめチャットボットにFAQや業務マニュアルなどの情報を登録しておくことで、社員はいつでもどこでも、簡単な質問を入力するだけで必要な情報にアクセスできます。
さらに、チャットボットにアンケート機能を盛り込むことで、ユーザーからのフィードバックを効率的に収集・分析でき、ナレッジの質を向上させることができます。
ただし、チャットボットのシステム構築には専門知識が必要であり、初期設定に時間がかかることがあります。また、チャットボットに登録された情報が正確でない場合、誤った情報が拡散される可能性もあります。そのため、チャットボットの適切な運用には、継続的なメンテナンスによる情報の更新が必要です。
チャットボットを適切に導入・運用すると、社員の疑問を即座に解決し、業務効率を大幅に向上させる強力なツールとなります。
ナレッジを最大限に活用する方法
ナレッジを構築できた後は最大限に活用する方法もあわせて知っておきましょう。
以下に紹介する方法を上手く活用が出来ていないと、ナレッジ作成にかかったコストが無駄になってしまうかもしれません。
存在を周知する
せっかく貴重な知識やノウハウが蓄積されていても、社員に知られていなければその価値は半減してしまいます。ナレッジを最大限に活用するためには、社内全体にその存在を周知し、活用を促す活動が不可欠です。具体的には以下のような活動が効果的でしょう。
| 社員教育の実施 | ナレッジの重要性や活用方法を学ぶ場を設ける。 |
| 管理者の積極的な働きかけ | 管理者自身がナレッジを積極的に作成し、ナレッジの有用性を示す。 |
| 社内イベントや研修での周知 | 社内イベントや研修の場で、ナレッジの活用事例を紹介する。 |
| コミュニケーションツールの活用 | 社内メール、掲示板、チャットツールなどで定期的に発信する。 |
| 部門別・プロジェクト別の情報提供 | 各部門やプロジェクトで必要なナレッジをピンポイントで紹介する。 |
これらの方法を活用して社内全体にナレッジの存在を周知し、社員がナレッジを最大限に活用できる環境を整えましょう。
目的を明確化する
ナレッジを最大限に活用するためには、その目的を明確にすることが重要です。知識やノウハウを言語化する作業には時間がかかりますが、ナレッジがどのような意図・目的のもとに作られたかを社員が理解していなければ、使われることはありません。
そのため、ナレッジリーダーという役割を設けて組織に必要なナレッジを定義し、その目的を明確にすることが重要です。この役割を設けることで、ナレッジを共有する目的を丁寧に伝え、組織全体や社員一人ひとりにとって有意義な試みであることを理解してもらえます。また、有意義な試みであると実感してもらうためには、ナレッジ共有によって成功した事例を周知することが効果的です。
これにより、目的が明確になり、ナレッジを活用しようという意識が高まり、結果としてより多くの社員が活用するようになります。 目的を明確にすることを心がけ、最大限に活用してもらいましょう。
ナレッジの活用失敗例
ナレッジを有効に活用することで、企業の生産性や効率は大きく向上します。しかし、うまく活用できない場合、その価値は大きく損なわれます。以下に、ナレッジ活用の失敗例とその原因を挙げます。
情報が古い
ナレッジを活用する上で、情報が古いことは非常に大きな問題です。古い情報に基づいた判断や行動は、思わぬミスやトラブルを引き起こし、企業にとって大きな損失に繋がる恐れがあります。
また、ナレッジが古いと、社員はそのナレッジを使っても無駄だと感じ、誰も利用しなくなります。これでは、せっかく作成したナレッジが活用されず、企業全体の効率や生産性が低下する恐れがあります。
ナレッジの情報の鮮度を保つためには専門部署と連携し、社内の仕様や手続きが変更された際にナレッジの更新が必要かどうかを確認することが重要です。また、各ジャンルのナレッジ担当者を明確にすること・責任を持って更新を行う体制を整えることも必要です。定期的な見直しと更新は、ナレッジの信頼性と有用性を維持し、社員が安心して利用できる環境となります。
情報が整理されていない
ナレッジを効果的に活用するためには、情報が適切に整理されていることが重要です。どこに何があるかが分かりづらい場合、社員がナレッジの利用を止め、貴重な知識が有効に活用されず無駄になってしまいます。
例えば、ドキュメントの場合、フォルダ構成やファイルの中身が伝わりやすい内容になっているかを留意する必要があります。明確なフォルダ構成と分かりやすいファイル名を使用することで、社員が必要な情報に迅速にアクセスできるようにしましょう。
また、FAQサイトであれば、特定ジャンルのリンクをまとめたサイトを作成することが効果的です。これにより、ユーザーは関連する情報に簡単にアクセスでき、時間を節約できます。ただし、リンクの更新があった場合は、適切なリンクが張られているかを適宜チェックすることが重要です。
古いリンクや不正確なリンクがあると、利用者は混乱し、ナレッジの信頼性が損なわれます。
情報が整理されていないと、社員はナレッジの利用を避けてしまいます。そのため、情報の整理とメンテナンスを怠らないことが、ナレッジを最大限に活用するための鍵となります。
検索しづらい
ナレッジを効果的に活用するためには、必要な情報に迅速かつ正確にアクセスできることが不可欠です。しかし、検索性が低いと蓄積されたナレッジが宝の持ち腐れとなり、組織全体の生産性を阻害しかねません。
そのため、頻繁に検索されるであろうキーワードを予測し、そのキーワードで検索した場合に関連性の高いナレッジが上位に表示されるように設計することが効果的です。また、同義語や関連性の高い言葉も検索キーワードとして設定することで、より多くの検索パターンに対応させることが可能です。
さらに、ナレッジをジャンルやテーマ別に分類し、階層構造を明確にすることで、ユーザーは目的の情報にスムーズにたどり着けます。よくある質問とその回答をFAQとしてまとめておくことも効果的です。
これらの対策を講じることで、ナレッジの検索性を改善し、社員が効率的に情報を活用できるようにナレッジを設計しましょう。
社員のレベルに合っていない
ナレッジを効果的に活用するためには、その内容が社員のレベルに合っていることが重要です。ナレッジが社員のスキルや知識レベルに適していない場合、理解や実践が難しくなり、その価値が損なわれてしまいます。
例えば、新入社員や経験の浅い社員にとって、専門用語や高度な技術内容が多すぎるナレッジは理解しづらいものです。逆に、熟練した社員にとっては、基礎的すぎる内容が退屈で役に立たないと感じることがあります。そのため、ナレッジはユーザーのレベルに応じた内容で提供されるべきです。
ナレッジを作成する際には、対象となる社員のレベルを考慮し、分かりやすい言葉遣いや具体的な例を用いることが効果的です。また、社員のフィードバックを活用し、ナレッジの内容や形式を適宜調整することも重要です。
社員が理解しやすく、実践しやすいナレッジを提供することで、業務効率と生産性の向上を図りましょう。
《社内SE転職ナビが選ばれる5つの特徴》

- 一人あたりの提案求人数、平均25.6社
- 登録者数38,000名以上(2024年7月現在)
- 入社後の定着率96.5%
- 多様な職種の社内SE求人保有
- エージェントとの無料面談可能
社内SE転職ナビでは、業界に特化したキャリアアドバイザーが、あなたのスキルや経験に合った求人を厳選してご提案。求人数の多さよりも、本当にマッチする案件を効率よく見つけられるのが強みです。
社内SEの役割は、システム運用にとどまらず、技術ナレッジを蓄積し、組織全体の生産性を向上させることにもあります。開発経験を活かしながら、事業成長に直結する業務に関わりたいなら、社内SEという選択肢は魅力的です。
提案求人数の平均は25.6社と、厳選した案件をご紹介するからこそ、忙しいエンジニアでも無駄なく理想の職場を見つけられる。ナレッジを活かしてキャリアアップを目指すなら、まずは社内SE転職ナビをチェック!
まとめ
ナレッジの「見える化」は、企業にとって今や必須の取り組みと言えるでしょう。ナレッジを効果的に活用することで、業務効率の向上、属人化の防止、そして人材育成の加速など、多岐にわたるメリットが得られます。
しかし、ナレッジの作成・共有は、一朝一夕にできるものではありません。ドキュメント、社内Wiki、FAQシステム、チャットボットなど、様々なツールや手法が存在する中で、組織の状況に合った最適な方法を選択し、継続的に運用していくことが重要です。
また、ナレッジの質を保つためにも、定期的な見直しや更新が不可欠です。社員からのフィードバックを積極的に取り入れ、常に最新の情報を提供できるようにしましょう。
ナレッジの「見える化」は、単なる情報共有の手段ではありません。組織全体の成長を促し、企業の競争力を高めるための戦略的な取り組みなのです。本記事を参考に、ナレッジ活用を始めてみませんか。

ライター:やころ
コールセンターで培ったコミュニケーションスキルを活かし、ヘルプデスクの立ち上げやSVとしてチームを率いた経験を持つ。その後、エンジニアとしてシステム運用保守に携わり、IT業界でのキャリアを積む。現在は、SEO記事作成を通じて、ITに関する情報をわかりやすく発信中。



-14-300x157.png)
-10-300x157.png)